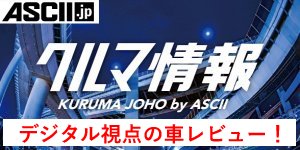●米国ですらクルマを持たない生活もありえた
筆者は米国で初めてクルマを手に入れるまで、東京で過ごしている限りにおいては自家用車を持っていませんでした。しかしUber普及以前にカリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアに引っ越したこともあり、クルマのある生活を送ってきました。
筆者はテクノロジーを中心に記事を書いていますが、こどもの頃からクルマが大好きで、高校時代「自動車部」なる部活に所属し、高校1年生の頃からキャンパス内のコースで乗用車に乗っていました。そんな私ですら、もしも2012年以降に引っ越していたら、確実に自家用車を持たない生活をしていたと思います。
日本の半分以下の金額とはいえ、駐車場の費用もバカになりませんし、そのコストで10回は街中を移動できるわけで……。また別にお酒がそこまで好きではない方ですが、お酒を飲んだら運転できないわけで、せっかくナパバレーなどのワインどころが近いのに、雰囲気を楽しんで帰ってくるだけじゃ、さすがに切ないですよね。
それぐらい、Uberが普及した米国のクルマ社会は、「クルマを持たなくてもなんとかなる社会」に変貌してしまったわけです。
米国から東京に戻った後も、結果的には引き続きクルマを持つ生活をしているわけですが、日本と米国では、道の広さを筆頭に、一度の移動距離の長さ、そして代替手段の有無など、自動車事情の違いがありました。
日本の場合、一度の移動距離が長い場合に自動車が登場し、短い場合は徒歩や自転車、電車、バスなどで用事が済みます。日本では車が使えなくてもなんとかなりますが、米国ではどうにもならない場面が少なからずあるわけです。
たとえば果樹園のある街のど真ん中では、タクシーはもちろん、Uberをつかまえることも難しく、動けなくなることもありえます。代わりに、道端に止めてある自動車を利用できるインスタントなカーシェアサービスも存在していて、代替手段については一長一短です。

この連載の記事
-
第314回
Apple
アップル「iPhone SE(第3世代)」隠れた最大のイノベーション -
第313回
自動車
「10年後にはみんなEVになるんだから」と人は言うけれど -
第312回
自動車
スマホから自動車を買う テスラのユーザー体験 -
第311回
自動車
Tesla Model 3をポチるまで 決め手は航続距離と乗り心地 -
第310回
自動車
テスラを買ったワケ 最大の動機は「リスク回避」 -
第309回
ビジネス
Twitterジャック・ドーシーCEO退任 理由は「創業期を脱するため」 -
第308回
トピックス
忙しすぎてカオスな予定を量子AIに調整してもらいたい -
第307回
Apple
なぜiPodは成功したのか 20年経った今あらためて考える -
第306回
トピックス
大学オンライン授業、教室との「ハイブリッド化」は複雑怪奇 -
第305回
トピックス
トランプ大統領が巨大ITに締め出された事態の重み - この連載の一覧へ