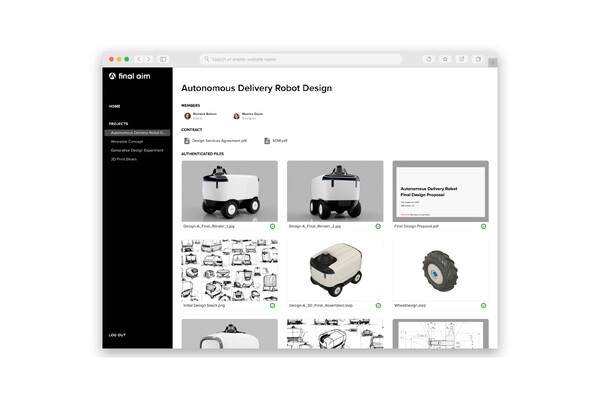次なる社会の実現に向けスタートアップや国内外の企業、研究機関がCEATEC 2023で展示、交流
CEATEC 2023 テーマ「次世代」
学生と業界リーダーや若手人材の対話と交流を促進、「Future Hub」
「次世代」の特色が濃かったもうひとつのステージが、展示会場中心のパートナーズパーク内に設置された「Future Hub」だ。「Future Hub」では未来を担う学生や若手のキーパーソンが登壇し、対話を通じてデジタル産業の魅力やキャリア選択に役立つ情報などがシェアされた。
具体的なプログラムの例としては、学生と各界のリーダーが対話する「Leader's Talk」やキャリアや働くことに焦点が当てられた「Cross Talk」のほか、業界動向やトレンドに焦点を当てたセッションなどが実施された。
19日に開催された、Cross Talk「電子部品業界で働く」には慶応義塾大学、筑波大学、東京大学から学生パネリストと、電子部品メーカーのTDK、アルプスアルパイン、村田製作所から若手社員が登壇。Q&A形式で、電子部品企業で働く魅力や電子部品業界の将来性などについて、学生が若手社員に質問した。
19日には、Leader’s Talk「学生とリーダーとの対話」も開催され、次世代を担う学生とJEITA半導体部会長の亀渕丈司氏がトークセッションを展開。若者に向けて、半導体産業で働く魅力がシェアされた。
20日には、学生を対象とした「電子部品技術の基礎知識」が開催。JEITA 部品技術ロードマップ専門委員会 幹事の高崎哲也氏が、普段、目にすることがない電子部品が社会にどのように貢献しているのかについて、「電子部品技術ロードマップ」をベースに解説した。
また、IoT機器やロボット、AIなど次世代ハードウェア、ソリューションを展示するスタートアップの展示エリア「IoT H/W BIZ DAY 2023 by ASCII STARTUP」から4社が登壇した「スタートアップショーケース」や、スタートアップの起業を目指す高校生や大学生による事業アイデアピッチコンテスト「学生起業家 事業アイデアピッチコンテスト」などが行われた。
学生と半導体業界の若手による「次世代人材クロストーク」
20日の「Future Hub」では、学生と半導体業界の若手人材による「次世代人材クロストーク」が実施された。東京理科大学大学院MOT教授の若林秀樹氏がモデレーターを務め、半導体業界で働く魅力が学生に伝えられた。
工学部の学生は「半導体メーカーにおいて、AIや機械学習が今後どのように活用されていくのか」と質問。これに対して企業の若手人材は「IT/IoTに関連して最近では、工場で稼働するロボットが故障する前に不具合を察知することで、故障期間中にラインがストップしてしまう課題を解決できないかと議論されている。メーカーの場合、顧客を熟知したうえで、新技術をどう活用できるのか検討することが重要になる」と答えた。
経済学部の学生からは「半導体不足のニュースを目にして、半導体が生活に必要不可欠であると認識しており、興味も持っている。文系の経済学部の学生として、半導体メーカーで文系人材がどのように活躍しているのか知りたい」との質問が挙がった。
これに対しては「半導体メーカーといっても全員が技術職ではない。素材の調達部門から生産工場、技術部門、マーケティング部門、営業部門など、さまざまな職種のメンバーが力を合わせて製品を販売している。とくに営業やマーケティング部門では、顧客に対して自社の技術をわかりやすく説明できる文系人材も多く活躍している。興味があるならぜひ半導体メーカーを志望してほしい」とのコメントがあった。
別の経済学部の学生は「半導体業界におけるSDGsの取り組みにはどのようなものがあるのか」と質問。企業の若手人材は、「半導体を通じた持続可能な社会の実現という観点でいえば、例えば、パワー半導体で自動車のモーターを効率的に稼働させることでエネルギーの使用効率を高められる。SDGsと半導体は目にみえる形では結びついてはいないが、半導体の性能を向上させることが持続可能な社会の実現にもつながっている」と回答した。
CEATEC史上初の試み、出展者交流ネットワーキングイベントも実施
CEATECにおける初の試みとして、共創を生み出すきっかけを提供する「ネットワーキングイベント(出展者交流会)」が、17日から19日の展示会終了後に開催されていた。
17日はスタートアップ、18日はグローバル(海外からの出展者)、19日は若手エンジニアを対象にした交流会が実施され、自社の展示で忙しい出展者同士の交流が促進され、これまでのCEATECにはなかった新しい共創が促進される場となった。