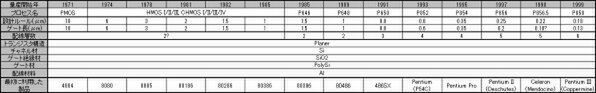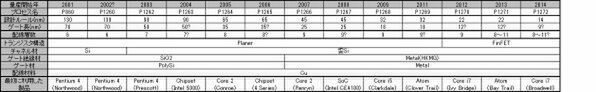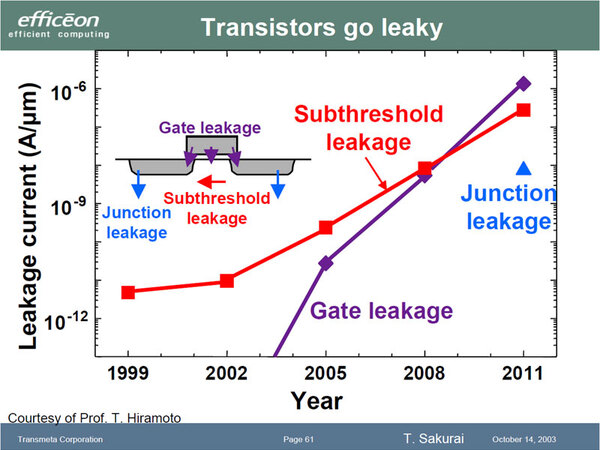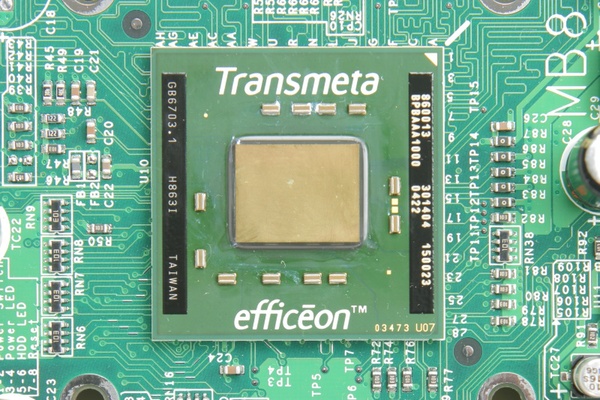90nm世代のプロセス「P1262」を採用したPrescott。非常に難産だった
各社のロードマップ アップデートを挟んだため1ヵ月ほど間が空いてしまったが、再びプロセッサーのプロセスについて解説していく。今回は2003年にインテルが導入した90nm世代の「P1262」の話である。
銅汚染問題の次は
リーク電流対策
配線を銅に切り替えたことで高速化の障害が1つ減ったものの、相変わらずトランジスタの高速化は難しく、よりゲート長を短縮する必要があったのだが、これにあわせてもう1つ懸念事項が出てきていることは業界でも広く知られていた。それがリーク電流だ。
上のグラフは東京大学の桜井貴康教授が2003年10月に示したものだが、トランジスタが動作する際には、リーク電流と呼ばれるものが一定量発生する。蛇口をきっちり閉めても、ほんのわずかながら水が漏れるようなものだ。
大きな水栓ならあまり問題にならないが、水栓というかパッキングが小さくなると、どうしてもわずかに漏れることは避けられない。同様にトランジスタも、小型化によってあちこちから電流が漏れ出てくる。このリーク電流には3種類ある。
- 意図せずにドレインからソースに漏れてしまう、サブスレッショルド・リーク電流(Subthreshold Leakage)
- ゲートから漏れてしまうゲート・リーク電流(Gate Leakage)
- Drain/Sourceの電極から直接漏れてしまう、ジャンクション・リーク電流(Junktion Leakage)
グラフからもわかる通り、これまでリークといえばサブスレッショルド・リーク電流が主であった。このグラフ、縦軸が対数になっていることが肝である。
例えば2005年に予定されているトランジスタであれば、ゲート・リーク電流はサブスレッショルド・リーク電流の10分の1でしかないが、2008年頃にはこれが同等になり、2011年には10倍になると予測しているわけだ。実際には、ゲート・リーク電流はこの予測より早期に問題になってきている。
Transmetaはこの対策として一種のBody Biasを利用した「LongRun 2」という技術を開発し、NECやSONY、富士通/東芝/NVIDIAなどにライセンスを供給するものの、結局自社のプロセッサー「Efficeon」はLongRun 2を実装しないまま会社が終了してしまった。
最近ではSuVOLTAというメーカーが、やはりこのBody Biasを利用した「DDC(Deeply Depleted Channel)」なる技術を開発、いくつかのベンダーにこれをライセンス供与している。
話を戻すと、このゲート・リーク電流はトランジスタの性能との相反関係にある。なぜゲートから電流が漏れるのか。それはゲートの厚みが薄いためだ。したがってゲート・リーク電流を減らすにはゲートの厚みを増せばいい。
ところがゲートを厚くすると、スイッチングの速度が遅くなる。トランジスタを高速化するためには、ゲートは薄い方が有利なのである。2003年頃は、どのくらいの厚みでバランスを取るか、各社頭を悩ませていた時期でもある。

この連載の記事
-
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -
第763回
PC
FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -
第762回
PC
測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -
第761回
PC
Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -
第760回
PC
14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -
第759回
PC
プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -
第758回
PC
モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ