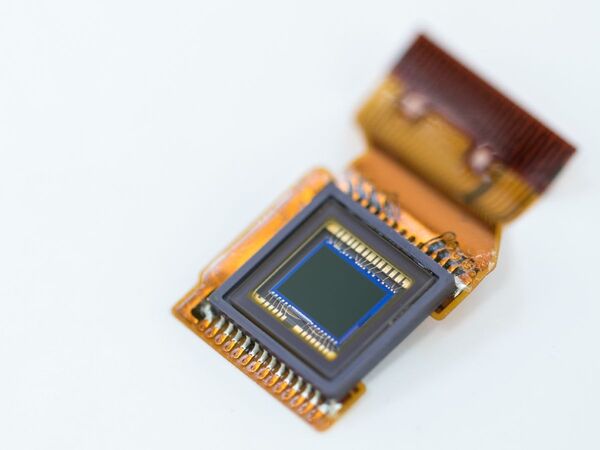日本人ノーベル賞受賞から見える日本の科学と世界経済の接点
世界中の製薬企業までも巻き込んでしまった免疫チェックポイント阻害剤のインパクトと、日本での評価のズレを考える
本庶先生の発言の裏にある日本の医薬品産業の構造的限界とは?
さて、本稿の本題はライフサイエンス系のノーベル賞にまつわるトリビアだけではない。今回の受賞後、関係者やその周辺では受賞理由となった研究と、その成果を実用化するにあたっての製薬企業の貢献についての議論が巻き起こった。
実用化のパートナーを探す時の苦労話は本庶氏から語られたが、この研究に「製薬企業は一切関与していない」という発言ばかりが強調されているように感じる。
本庶氏ご自身が日本の製薬企業の不甲斐なさを各方面で強調されてきているので、マスコミとしても取り上げやすいのだろう。ただ筆者は、これは欧米ほどの規模を持たない日本の医薬品産業の構造的な限界ではないかと感じている。
オプジーポ開発の元となった研究成果は、すでに世界的に著名な研究者であった本庶氏の努力をもってしても日本国内の製薬企業を動かすことはできなかった。しかし、米国のBiotechであるMedarex社(後にブリストル・マイヤーズ・スクイブ社により買収)が開発に興味を示したことから、基本特許の出願人にも名を連ねている小野薬品が共同開発を決めた。
メディアなどでは、「なぜ日本の製薬企業がこんな有望な研究成果に手を出さなかったのか?」という視点で語られることが多いが、「なぜMedarex社は巨額の費用をかけて開発する決断ができたのか?」という疑問が出ていない。このような課題設定を発信者に頼った目線では、本質を考えることは難しい。
そもそもMedarex社は米国の有名大学であるダートマス大学の免疫学研究者らによって設立されたBiotech企業であり、免疫学の研究成果を活用してリウマチ薬の開発などを行なっていた。
免疫チェックポイント阻害剤についても、オプジーポの開発に先行してもう1つの免疫チェックポイントの重要因子であるCTLA-4をターゲットとする免疫チェックポイント阻害剤をすでに開発していた。本庶氏や小野薬品工業と共同開発を開始した2005年時点(小野薬品工業発表資料より)では世界でも限られた、ある意味では大きなリスクを背負って、免疫チェックポイントの阻害によってがん治療を行う判断が可能な企業だったとも言える。
ちなみに同時期に米国の巨大製薬企業Merck社(日本での商号はMSD社)がPD-1分子に対する抗体を作成し、同じ戦略で猛追してきたわけだが、それでも当時は片手程度の企業しかこの分野に参入していなかった状況だ。数多ある世界の製薬企業の規模やバラエティーから考えても、また製薬業界における日本企業のプレゼンス(日本の製薬企業の総売上は世界の製薬市場の約10%、日本マーケットの規模は全世界の7.6%、日本製薬工業会 Data Book 2017より抽出)を考えると、日本国内の企業がたまたまこの研究成果に注力し、リスクをとらなかったことは、確率論的にはそれほど違和感はない(日本企業の特性を鑑みると、自国が世界に誇る免疫学権威のプレッシャーに打ち勝ってまで共同開発を拒否した決断力は、むしろ驚くべきかもしれないが……)。