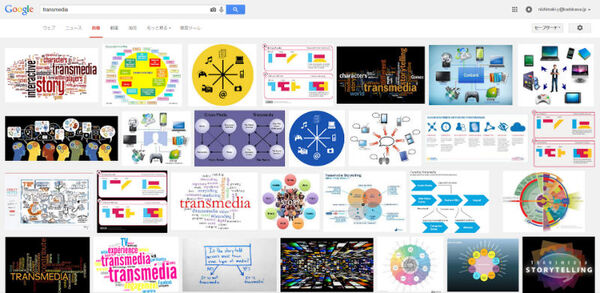ソーシャルメディアとマスメディアが混ざっていく「メディアの液状化」が起きている
SNSをやめる人が続出? なぜTwitterは面白くなくなったのか
2015年06月10日 10時00分更新
トランスメディアという新たなメディア環境
「トランスメディア」という言葉がある。定義としてはさまざまあるが、私の中ではひとつの物語が複数のメディアを横断しながら展開されるメディアデザインの手法およびその様態ととらえている。
トランスメディア環境の中では物語を構成する各モジュール(小さな物語)がそれぞれ最も適したメディアを通して表現され、その断片の総体が物語の全容となる。
このとき、使用される各メディアのあいだには上下関係や優劣関係はなく、すべてがフラットである。そして小さな物語は相互に共鳴しつつ、絡み合い、溶け合っていく。
このトランスメディア的な状況がもはやわれわれの日常的なメディア環境になりつつあるとは言えないだろうか? つまり、実はマスメディアとソーシャルメディアの対立関係などもうとっくになく、マスメディアの中にソーシャルメディアのネタが流入し、ソーシャルメディアはある部分でマスメディア化してしまっている。
「メディアの多様化」と言うよりは、「メディアの液状化」と呼んだほうがしっくりくるような事態である。
既存のメディアから離れていくコンテンツ
現在のメディア環境がこんな具合であると考えると、多くの人たちがソーシャルメディアに求めていた「ソーシャルメディア性」が、いつの間にかもう別のメディアに転移してしまっているという可能性も考えられる。
「Twitterが面白くなくなった」のは、かつて面白かった「Twitter的なもの」がTwitterというメディアから剥がれ落ち、どこかとんでもないところに逃げ出してしまったのではないか?
この、メディアとコンテンツの乖離はいよいよ加速しているように思う。たとえば「新聞紙」というメディアと「News(新聞)」というコンテンツはもはや最良のコンビとは言えず、現状、Newsは新聞紙ではない別のメディアでこそ輝きを放つものになっている。
音楽もまた然りで、すでにかなり以前から「音楽」というコンテンツは「CD」というメディアと決裂し、ほかのメディアに吸着しているわけだが、状況はさらに進展しており、音楽が新たに身を寄せた先はネットの中ですらないような気配さえある。
雑誌も同様。「雑誌的なもの」は依然として必要とされてはいるものの、雑誌的なコンテンツがパートナーとするのは、決して紙の雑誌ではなく、もしかするとウェブマガジンですらないのかもしれない。
今回はこれくらいにしておくとして、西牧氏のモヤモヤを解消するためにはまだまだ考えなければいけない問題はたくさんある。次回以降、「では、そんな時代にどうやって情報と付き合っていけばいいのか?」ということも含め、より深いところに潜っていくつもりだ。
著者紹介――高橋 幸治(たかはし こうじ)

編集者。日本大学芸術学部文芸学科卒業後、1992年、電通入社。CMプランナー/コピーライターとして活動したのち、1995年、アスキー入社。2001年から2007年まで「MacPower」編集長。2008年、独立。以降、「編集=情報デザイン」をコンセプトに編集長/クリエイティブディレクター/メディアプロデューサーとして企業のメディア戦略などを数多く手がける。現在、「エディターシップの可能性」をテーマにしたリアルメディアの立ち上げを画策中。本業のかたわら日本大学芸術学部文芸学科、横浜美術大学美術学部にて非常勤講師もつとめる。

この連載の記事
-
第15回
トピックス
ネットの民意がリアルに反映されないケースはなぜ起こる? -
第14回
トピックス
電子書籍がブレイクしない意外な理由とは -
第13回
トピックス
国民半分の個人情報が流出、情報漏えい防止は不可能なのか -
第12回
トピックス
Apple WatchとGoogle Glassは何が明暗を分けたのか? -
第11回
トピックス
誰も教えてくれない、ウェアラブルを注目すべき本当の理由 -
第10回
トピックス
ドローンやウェアラブル、Netflixから見る情報のもどかしさ -
第9回
トピックス
PCと人間の概念を覆しかねないシンギュラリティーの正体 -
第8回
トピックス
PCが売れないのはジョブズが目指した理想の終了を意味する -
第7回
トピックス
ビジネスにもなってる再注目の「ポスト・インターネット」ってなに? -
第6回
スマホ
アップルも情報遮断の時代、情報をうまく受け取る4つのポイント -
第5回
スマホ
僕らが感じ始めたSNSへの違和感の理由と対処を一旦マトメ - この連載の一覧へ