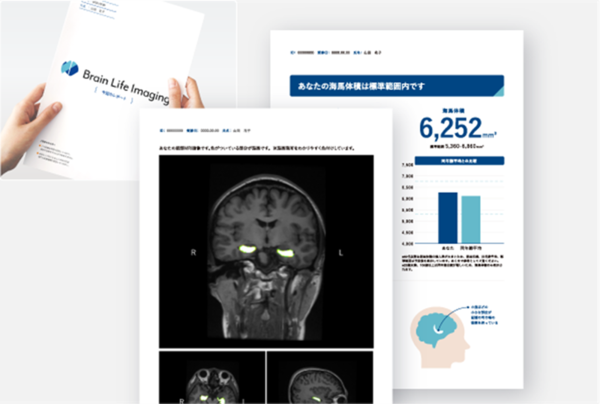医療AIにもプロダクトマーケットフィットを。コア技術、ブランディング、知財のパッケージ化が業界浸透に奏功
【「第3回 IP BASE AWARD」スタートアップ部門グランプリ】株式会社Splink 代表取締役社長 青山 裕紀氏インタビュー
この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」(外部リンク)に掲載されている記事の転載です。
「第3回IP BASE AWARD」のスタートアップ部門で栄えあるグランプリを受賞した株式会社Splinkは、創業初期から知財活動に力を入れ、ビジネスフェーズに合わせた戦略によって、競合への対応や将来の協業を意識したポートフォリオを構築し、医療業界でのポジションを着実に築いている。ビジネスのゴールを達成するための知財戦略、社内の体制づくりについて代表取締役の青山裕紀氏、知財・薬事戦略を担当する経営企画室の成尾佳美氏に話を伺った。

株式会社Splink 代表取締役社長 青山 裕紀(あおやま・ゆうき)氏
2005年に慶應義塾大学法学部を卒業後、株式会社キーエンスに入社。同社北米ビジネスにおける事業開発、ブラジル法人設立、メキシコ法人マネジメント等に従事。その後、シリコンバレーVCにてEiR(Entrepreneur in Residence:客員起業家)を経て、2017年1月に株式会社Splinkを設立、代表取締役に就任。ダートマス大学経営大学院(MBA)修了。聖路加国際大学大学院公衆衛生研究科(MPH)修了。
AIで脳の健康状態を見える化
認知症の予防や患者のQOL向上を目指す
株式会社Splinkは、認知症など脳疾患の発症前から発症後までの脳の状態を可視化し、予防や診断精度の向上を目指す、ブレインヘルスケア領域のAIスタートアップ。プロダクトとしては、脳ドック用AIプログラム「Brain Life Imaging」、脳画像解析プログラム「Braineer」(ブレイニア)を中心に、医療機関向けのビジネスを展開している。
「Brain Life Imaging」は、脳ドックを提供するクリニックや健診センターなどの医療機関を対象に提供している脳ドックの延長線上のサービス。通常の脳ドックの場合、脳動脈瘤や脳梗塞といった疾患が対象であり、認知症および認知機能低下の発見は難しい。しかし、「Brain Life Imaging」は脳の測定データを健常な脳のデータベースと比較することで相対的に可視化し、わかりやすいレポートとして提供する。受診者自身が自分の脳の状態を知ることで、脳に良い生活の啓発を促進できるという。
「Braineer」は、脳の萎縮を定量・数値化することで、医師の診断を支援するエキスパート向けの製品。従来は専門医の知識や経験といった暗黙知に頼っていた診断に再現性をもたせることで、疾患見落としの防止にもつながる。
各ソリューションの背景にあるのは、脳科学分野での画像処理の掛け合わせでの比較的よくあるアルゴリズムだと青山氏。同社としては、人工知能(AI)技術自体が特殊であるというよりも、脳画像の処理・取り回しがノウハウとしてあるという。
創業から3年間、2020年までのフェーズはこうしたノウハウの蓄積やネットワークづくりに専念し、脳科学スタートアップとしてのフロントランナーという業界内でのポジションを築いていった。いよいよ市場へ投入というタイミングで、転機となったのがコロナ禍の医療機器業界への影響だった。
コロナ禍での市場凍結タイミングでプロダクトマーケットフィットを検証
青山氏は法学部の出身。ライフサイエンス関連領域では、そのバックグラウンドがない中での参入は珍しい。起業時から勝算はあったのだろうか。
「事業立上げの基本としてPSF(プロブレム・ソリューションフィット)、またその先のPMF(プロダクト・マーケットフィット)については、シリコンバレーのVCに在籍していた時に、さまざまなスタートアップの動きを見る機会があったので、創業の半年ぐらい前から一定の想定のもと、仮説検証をして臨んだのですが、実際にやってみるとそう簡単ではありませんでした。
ひとつは市場参入が早すぎたこと。2017年の創業当時、競合他社がいない中で研究開発や事業立上げを進めることができた一方、本当に市場があるのかは慎重に検討を進めていきました。アーリーアダプターの先生が製品を採用して使ってくださったので、そこでプロダクト検証の機会を早い段階から得られたことが財産になっています。
もうひとつは、2020年頃のコロナ禍で、医療機関が新たなイノベーションどころではなくなり、市場がほぼ凍結していたこと。当時は新規営業に進めていくことが極めて難しかったです。その間に既存導入先の先生方にご協力いただき、PMFを固めていくことに作戦を切り替え、多くの先生方とディスカッションして製品の改良を重ねました。現在、ようやくコロナが明け始めたタイミングに市場と事業がフィットしはじめたと感じているところです」
マーケット・インが多少遅れたものの、おかげで業界内でのネットワークを築き、2022年には日本神経学会のシンポジウムにて登壇する機会を得るなど、当該領域の企業として少しずつ認知してもらえるようになってきた。コロナ禍の戦略シフトが企業ブランディング、商品ブランディングに効いてきているという。
「コア技術、ブランディング、知財をパッケージ化して訴求しないと医療業界は難しい。コロナがなかったら事業のタイミングが早すぎて暗中模索を極めていたかもしれません。現実は仮説よりもはるかに厳しかったけれど、確信をもって真っすぐに進んだことが良かったですね」
薬事認可の必要な脳画像解析プログラム「Braineer」ではなく、自由診療である脳ドック用AIプログラム「Brain Life Imaging」を先にローンチしているのも、プロダクトマーケットフィットの考え方が根底にある。
「いったん薬事認可を得てしまうと仕様変更が難しくなります。SaMD(Software as a Medical Device:医療機器プログラム)は米国では市民権を得ている分野ですが、日本ではまだこれから。医療の場合、国ごとに法律や診断方式が異なり、タイムマシン型のビジネスは通用しません。
また、MRIが普及している日本ではSaMDの活用方法も変わってきます。まずは自由診療の領域から市場参入し、業界の中でのポジションを築いていくことから始めました。メーカー側が創りたいものが、必ずしも現場のオペレーションの最適化につながるとは限らないので、現場が運用しやすいように、デザインの力を使って顧客体験を設計していくことを重要視しています。プロダクトとデザインだけでは後発企業の模倣リスクがあるので、知財戦略には創業時から力を入れていきました」
ゴールから逆算して、事業戦略・知財戦略を立てる
全社的な知財活動は、弁理士の成尾佳美氏が入社した2020年1月から薬事戦略を含めて始動した。ただし、成尾氏の入社前から、青山氏と創業メンバーであるAIエンジニアの2名で十数本もの特許を出願している。
「米国VCは特許も含めた知財、技術のデューデリジェンスが詳細にあります。グローバル市場を見据えてディープテック・スタートアップを発展させていくためには、技術的な優位性だけでなく、知財戦略も並行して取り組む必要があると考えていました。それを実現するためには、社内にプロフェッショナルを置いて自社に合った戦略を立てる必要があると考えました。まずは自分たちで核となる知財を確立して、社員20人目までにはフルタイムの弁理士を入れて、知財を整備して周辺知財を固め、さらに知財法務の組織を作っていこうという目論見です」(青山氏)
このような組織戦略の実現に向けて、青山氏は自ら、転職支援サイトをチェックしては、専門家を探し続けていたという。
「条件は、知財と薬事を両方みてくれて、サイエンスがわかること。成尾さんは弁理士で薬事もできるので、初めて出会った瞬間にこの人だと思いました。会社に何もない時期だったので、大手企業や事務所とのギャップに戸惑われるのでは、と心配もしていましたが、何度か会って話をするうちに、この人なら信頼して任せられると思いました」と青山氏。
ジョインした成尾氏がまず着手したのは、既存知財の整理だ。それぞれの権利がどのビジネスに紐づいているのか、担当した研究者からヒアリングして細かく見直して、どのように知財活動を進めていくかを考えていった。
Splinkの事業戦略・知財戦略は、ゴールからの逆算型にある。「事業としてのゴールを達成するための手段として、システム開発や研究開発があります。この中間プロセスから生まれたアルゴリズムなどの成果のうち、どこを権利化すれば他社が真似できないのかを考えるのが戦略。ゴールから逆算して、各ステップでの研究開発段階を切り分けて、それぞれで知財を含めたやるべき方針を立てていきます」と成尾氏。
例えば、計測技術を作ったら、次はいくつかの要素技術を組み合わせて測定されたデータを使いディープラーニングをする、などの棚卸しをすることで、どのタイミングでどの知財を取っていくのかが見えてくる。また、未来に出す知財だけでなく、過去に出した知財がどこにプロットされて、どこが手厚く、どこが薄いかがわかるようになったという。
大手企業の知財部などが取り組んでいるIPランドスケープと同じ考え方だが、スタートアップの強みは経営者と弁理士の距離が近いことにある。
「事業戦略に基づき、出願するべきか、ノウハウとして秘匿すべきかの判断を厳密にしています。知財をうまくコントロールすることで、競争優位性や協業が作り出せる。こうした戦略を高速に回せるのがスタートアップならではだと思います」と青山氏。
脳画像解析プログラムはすでに薬事認可を取り、医療機関にトライアル導入されている。導入環境も含めて、製品としてのPMFをしっかりとっていく段階である。
「私は『神経画像診断AI 2.0/3.0』という言葉をよく使っていて、社内外に向けて技術開発ビジョンを発信しています。医師の先生方にこの言葉が通じる世界を作っていきたいですし、神経画像という領域におけるAIの利活用やその適応課題を社内外の研究者と共に見出していきたいと考えています」
知財・法務・薬事を合わせた知財戦略チームづくり
現在は、成尾氏が知財と法務、薬事の3つを担当しており、最近2人目の知財担当者を採用したばかり。知財、法務、薬事はそれぞれに高い専門性を持ち、すべてをカバーできる人材は少ない。さらに、連動した知財戦略を立てるのは相当な力量がいる。成尾氏はどのようにこなしているのだろうか。
「私は医薬品関係の知財と薬事の経験はありましたが、医療機器分野は初めてでしたし、入社当時は法務までをやるとは考えていませんでした。ですが、仕事を進めていくうちに、契約もきちんと見られないと知財が意味を持たないものになるとわかってきて、徐々に法務に興味を持つようになりました。もともと専門外なので、社外の専門家の助けを借りながら、知識を吸収させてもらっています」(成尾氏)
Splinkとして今後はメンバーを増やして知財チームをつくり、社内体制を強化していく計画だ。
「求めているのは、知財と法務の両方が見られる方。現時点では知財と法務が両方わからなくても、知財が専門だけど法務に興味のある方、あるいは技術に興味のある法務の専門家の方に入っていただければ」と成尾氏。
2022年には会社の知名度が高まってきたことで、一年前の同時期と比べると採用候補者数は10倍に増え、さらにIP BASE AWARD受賞で知財職への応募数も伸びているそうだ。さらにこういった評価は、共同研究での信頼にもつながっている。
「開発から製品化までの過程で知財と論文を出し、薬事認可を取る、という一気通貫のプロセスは、共同研究先の事業会社からは『社会実装ができそうだ』という安心感を持ってもらえています。医療の世界では、まず土俵に上がるために知財は必須。知財を流通させることで医療に貢献できる。さらに、自社が権利を持つことでいろいろなプレーができるようになります」(青山氏)
今回受賞を果たしたSplinkは、ここからの1年でどのような動きを見せるのか、青山氏に聞いてみた。
「認知症医療における発症前から発症後までのワンストップのペイシェントジャーニーを確立すること。日本の神経領域における、高い医療技術や研究成果を世界に通用するソフトウェアに仕上げていく。それを通じて、日本のみならず世界の高齢化の課題の解決に貢献していきたい。事業戦略や技術ビジョンは明確なので、いかに知財を絡めていくかがこれからの成長の鍵となります」