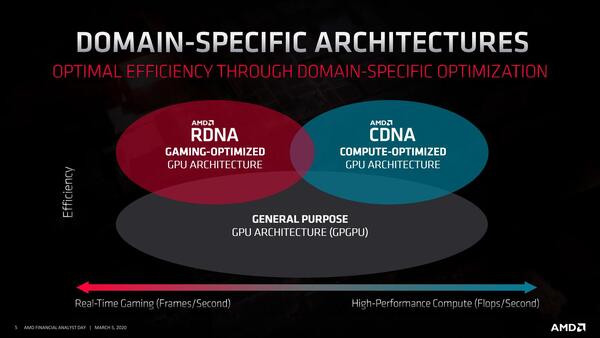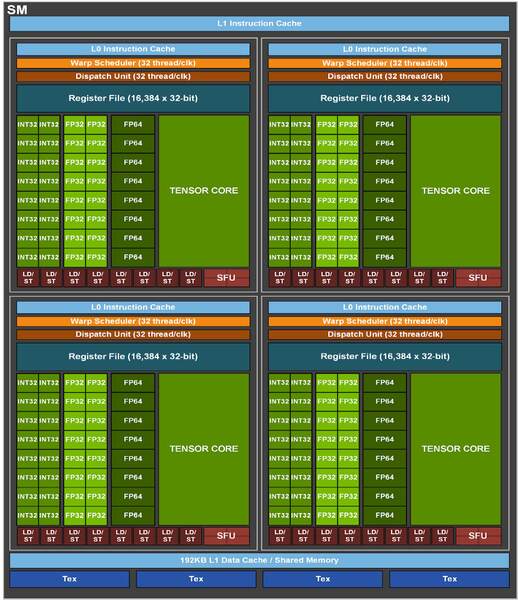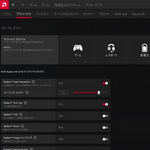ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第590回
Radeon Instinct MI100が採用するCDNAアーキテクチャーの内部構造 AMD GPUロードマップ
2020年11月23日 12時00分更新
11月20日、「Radeon RX 6800」シリーズが無事に発売になった。KTU氏によるレビューをご覧になった方も多いと思うが、おそろしくパワフルな製品に仕上がっており、レイトレーシングを利用しない限りにおいてはGeForce RTX 3000シリーズに十分競合できる。
という話はおいておき、今回解説するのは11月16日に発表されたCDNA第1世代を実装する、Radeon Instinct MI100の話である。が、その前に連載587回に誤りがあったため、まずはこれの訂正をしたい。
Smart Access Memoryを利用するのに必要な
Resizable BAR
こちらでSmart Access Memory (SAM)の正体はCCIXを利用したCoherent Memory Accessではないかと推察したのだが、その後AMD本国の関係者から「そうではなく、PCIeでの接続である」という返事が返ってきた。
その後にSAMを利用するためにはBIOSセットアップでを有効にすべしという注意書きが届いて、やっと正体がわかった格好だ(KTU氏もレビュー記事で触れている)。ついでなので、このResizable BARの話をしよう。
BAR(Base Address Register)というのは、PCI ExpressのConfiguration Space(PCI Expressのデバイスを内部で管理するためのメモリー空間)の中にあり、デバイスのメモリー領域をホスト(つまりCPU側)のメモリー空間にマッピングする際のアドレスを格納している。
もともとはPCI Express(の元になったPCI)が32bitアドレスでの動作を想定していたこともあり、BARの扱えるメモリー領域は最大でも256MBに制限されていた。ところが64bitアドレッシングをサポートしたCPUが登場したことで、BARをもっと広げても良いのではないか? という議論が起こる。
最終的にPCI Express 2.0のECN(Engineering Change Notice)として2008年1月22日に、Resizable BARという仕様が追加された。これはBARのサイズを最大512GBまで拡張できるというもので、オプション扱いとなり、PCI Express 2.1以降では正式に仕様に取り込まれているみ(ただし実装は必須ではなく引き続きオプション)。
マイクロソフトはWDDM v2でこのResizable BARに対応したことを2017年4月に表明している。というわけで、SAMは別にDX12やVulkanだけでなく、DirextX 9/10/11やOpenGLでもその効果が期待できるとAMDの関係者からは返事があった。
余談であるが、筆者もHorizon Zero DawnをSAMありで実施したが、問題なく4Kで完走した。KTU氏との違いは、主にマザーボード(筆者はASUS ROG CROSSHAIR VIII HEROを利用)程度であるが、それが理由とも思えないのだが。
CDNAアーキテクチャーを採用したHPC向けGPU
AMD Instinct MI100を11月16日に発表
さて、Radeon RX 6800の話はこの程度にして、本題に入ろう。もともとRadeon Instinct系、つまりGamingではなくComputationにフォーカスした市場向けに、AMDは従来のGCN(Vega)からRDNA(Navi)とCDNAに分けると今年3月に明らかにした。
これはNVIDIAも同じで、アーキテクチャーこそ共通のAmpereとされつつ、GPGPU向けのGA100とGaming向けのGA102では、SM(Streaming Processor)の構造が異なっている。GA100はFP64の演算ユニットを搭載する一方でRTコアがなく、逆にGA102はFP64を省いてRTコアを搭載しているのがわかる。AMDはもっと大胆に、アーキテクチャーそのものを切り替えた形だ。
さてその中身である。ちなみにAMDはまだ“VEGA”や“NAVI”にあたる、CDNAのコード名を公開していない。“Arcturus”という名前がRadeon Instinct MI100のコード名と言われているが、アーキテクチャーの名前そのものではない。ということで、以下CDNA 1.0として表記したい。
そのCDNA 1.0の構造が下の画像となる。RDNAの構造と比較すると、(CU数はともかくとして)例えばPixel UnitやRasterize、RB(Render Backend)など描画に必要な要素がキレイに消えていることがわかる。また、当然ながらGeometry Processorも搭載されていない。

この連載の記事
-
第769回
PC
HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -
第763回
PC
FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -
第762回
PC
測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -
第761回
PC
Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -
第760回
PC
14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -
第759回
PC
プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ