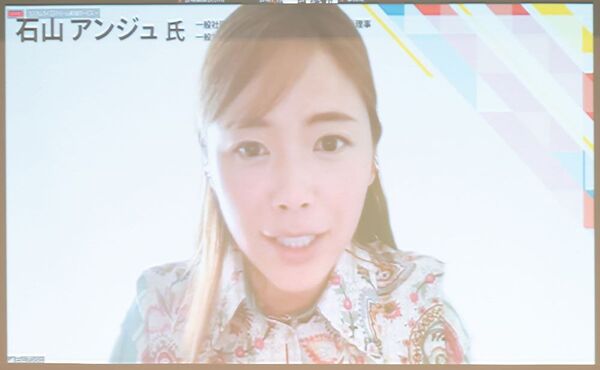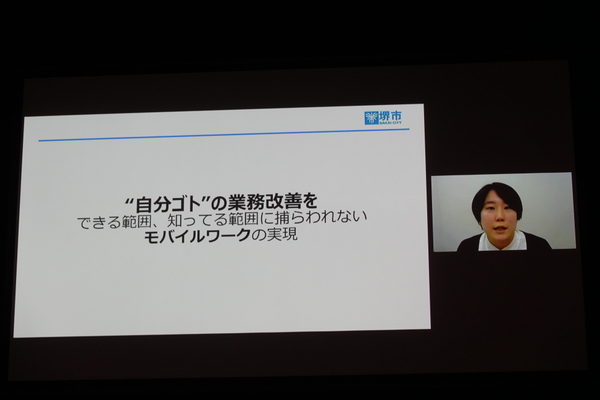地域課題解決と起業家たちの考えるエコシステムの形
堺市「中百舌鳥イノベーションシンポジウム」レポート 後編
エコシステム形成の必須要件
最後に、イノベーションを生み出すエコシステムを創出する際に必要なモノは何か、各氏の想いを語ってもらった。まず三浦氏からは、働く人や企業の価値を高めるという観点から、働く人の流動性を高め、より高い評価を受けるところ、より必要とされるところ、より自分のやりたいところで仕事をできるようにすることが大事だと強調された。
「(働く人の)流動性を高めることが大事。人を切るというネガティブな話ではなくて、その企業が目指しているところと自分が目指しているところが違うなら、違うところに行ったり自分で会社を興したりするなど、いまは選択肢が増えているということ。堺市がエコシステムを回そうとするインセンティブは例えば税収を増やすなどが大きいと思うが、そうするとあまり換金されない(価値が明確でない)ビジネスの延命に合理性を欠いた理由で血税を流し込むのはエコシステムとは呼べない。一方でその仕組み作りを市が行うには民主主義が絡んで非常に大変な説明をしなくてはいけなくなる。そこは民間に流動性を高めていくためのインセンティブを与えていく方が良い」(三浦氏)
三浦氏自身のビジネスであるグラムスでも、社員数が増えてきた結果、方向性の違いが顕在化してくることがあったとのことだ。
「我々はもともと10人足らずの外国人ばかりの会社だったが、最近日本人も増え、いろんな属性の人が入ってくるようになった。そうすると方向性の異なる意見が出てくる。企業は各ステージや外的要因で方向性も方針も変わっていかざるを得ないが、それとは違うと思うなら、その時点で自身の利害が一致する環境に行けば良い。それができるかできないかは個人の問題。利害関係が一致して、そこから一緒に事業をやろうという動きが中小企業から大企業などいろんなところに波及していけば流動性が高まり、そしてエコシステムにつながってくると思う」(三浦氏)
イノベーションを創出するエコシステムは、古い価値から新しい価値への循環と変換であり、そこにそれまでのノウハウの蓄積や複数のステークホルダーが持つリソースの掛け算が合わさって、質と量ともに加速していくものとみることができる。三浦氏はそこに必須のものとして、人材や資本の流動性を挙げたということなのだろう。
大津氏からは神戸市、宝塚市、浜松市など事業を展開している地方都市の観点から、エコシステム創出に対する課題が示された。
「我々は戦略的に自治体と連携させてもらっているが、それらの自治体には共通点がある。スタートアップは創業から数年というのが普通で、『10年間ビジネスをやっていないと一緒にやれない』みたいなことだと連携自体ができない。
そうではなく、いまいいアイデアがあって、熱意があって、ベクトルが一緒だというなら『一緒にやろう』と考えてくれる部門があるかどうかが、スタートアップが自治体と連携する最初のポイントになる。
堺市は十分やっていると思うが、そういうことをどんどんPRや発信したりしていただけたら、地方のスタートアップも一緒にやりたいと思うだろう。そういうところを知らないだけなのではないかと思う。」(大津氏)
「お役所仕事」という言葉があるとおり、どうしても自治体にはスタートアップのスピード感やアグレッシブさについてこられないのではないかというイメージが付きまとう。しかし、それをクリアしている自治体が少なからずあることも確かで、まずそこを強く発信していくことが、自治体によるエコシステム形成の第一歩となるだろう。
「事業にもよるが、我々が目指す中低所得状態にある方々の課題を解決したいというところでは自治体も一緒だし、ビジネスモデル的に従来の方法ではそもそも成り立たないところもある。そこは自治体との連携が大切になってくる。
スタートアップは、最初はブランド力がないので、(共同で)事業を一歩進めるときに、(パートナーから見ると)こいつは本当に大丈夫かとか思うこともあると思うが、神戸市や京都市が一緒にやろうと言ってくれたことで、明らかに(協業が)加速した。そういったところが自治体と一緒にやりたいと思ったポイントだ」(大津氏)
大津氏の指摘する通り、社会課題を解決することを目標とするスタートアップから見ると、自治体との連携には非常に大きな魅力がある。自治体のみならず、参加するステークホルダーすべてがイノベーティブに転換し、その価値を発信していくことが、エコシステム形成のカギになるのかもしれない。
クレシェンコ氏は、より具体的に「エコシステム形成のカギは起業経験者を集めること」だと言う。ただし、起業家だけでなく、自治体担当者や大学の連携窓口、金融機関などすべてが新規事業開発の知見を持つことが必要になってくる。
「エコシステムのカギは起業した経験を持つ人材を増やすことにあると思っている。本当に先進的なビジネスモデルを思いついても、先進だからこそ金融機関の担当者も理解できず、融資が受けられない。日本には投資家にも海外の様子を見ていない人がいるので、投資家にもわかってもらえない。起業経験者でも、10年20年前に上場したという人ではアドバイスができない。
日本では国際的な人材がまだ活躍できていない。海外と比べるとすごく遅れている。まずすべてのステークホルダーの意識を向上させないといけない。金融機関の担当、自治体の担当、大学の担当がスタートアップの最近のトレンドは何か、どうやってスタートアップを成長させることができるのかを理解しなくてはいけない。全員が理解したらエコシステムの形成が軌道に乗ってくると思う」(クレシェンコ氏)
人材の育成には時間がかかる。どこから手を付けるべきかクレシェンコ氏に聞いてみた。
「海外のマーケットトレンドを理解している専門家を呼んできて、一緒にワークショップをやる。それだけでもかなり当事者の意識が深まっていく。日本語で作成された資料だけでなく、英語でヨーロッパはどうなっているか、アメリカはどうなっているかを見る。その情報を全員で理解する必要がある。
日本では未開拓のビジネスでも、海外にはすでにスタートアップができている場合がある。それを参考にして連携は可能。スタートアップの成長ロードマップなどもわかる」(クレシェンコ氏)
英語が苦手だからといって情報収集を怠るということは、自分から成長加速の機会を逃しているということなのだろう。スタートアップ自身がそれを可能にする人材を確保できるなら良いが、それが難しい場合はそれを支援する機能がエコシステム内に必要になるだろう。
多拠点居住を実践している石山氏からは、地方都市の持続性についてコメントがあった。
「政令指定都市とか中核都市にはこれまで利便性で人が住んできた。しかしそういう人たちはシビックプライドを持っているのだろうか。エコシステムをつくるためにも、都市を持続可能にするためにも、多くの市民にいかにしてシビックプライドを持ってもらうかが大事だと思う。
民間は利潤追求で動いているし、行政も財政が無くなったらこれまでやっていたことができなくなる。その循環の立役者になれるのは市民であって、その市民の動機になるのがシビックプライドだと思っている。そうした文化をどうやって形成していけるか。それが中核都市の課題だと思っている」(石山氏)
エコシステム形成の前提として、地方がまず存続していなくては意味がない。効率性や経済性だけで成立する集団には、それが揺らいだ時に人をつなぎとめる動機がない。人同士のつながりや信頼感、地域が持つ文化などがシビックプライド醸成のベースとなる。エコシステム形成はその次のステップとなるのだろう。