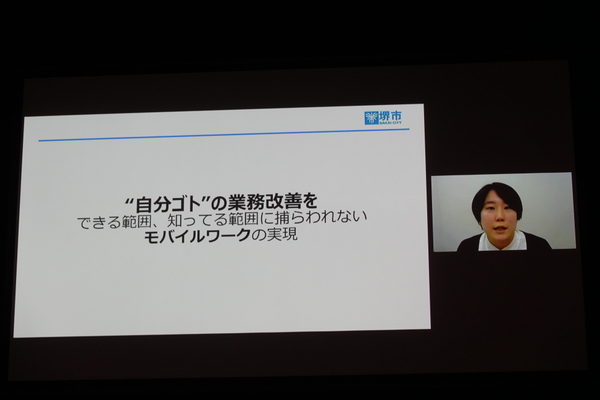地域課題解決と起業家たちの考えるエコシステムの形
堺市「中百舌鳥イノベーションシンポジウム」レポート 後編
エコシステム形成に向けた方法論
人口減少が課題となっている都市は堺市だけでなく日本中にあり、それらの少なくない数でスタートアップによるイノベーション創出を目指した動きが活発化してきている。では、堺市のような地方中核都市において、どのようにしてエコシステムを形成し、発展させていくのか、そのカギとなる要素は何か、パネリストたちに意見を伺った。
「まずエコシステムの定義を、起業家が起業して成功し、資金的またはリソース的なものを後進に伝えていくという循環を起こして経済を回していくものと定義する。その上でエコシステムを形成するには、小さなM&Aをたくさん起こすしかないと思っている。
堺市には小さなビジネスがたくさんある。そこでキャピタルゲインを得た人が、また新たな事業を起こすとか、小さく投資をするとか。小さな雪だるまを転がしながら大きくしていくことが必要ではないか」(三浦氏)
イノベーションとは革新であり、「新しい何か」がすでにあるものよりも大きく成長するのであれば、既存のものは新しいものを生み出すための材料として活用することが、エコシステムを生み出す近道であると三浦氏は語る。
「そういう人たちをたくさんつくって経験を増やしていく。そうすると外からも入ってくる人がいて、お金の出し手も来る。空港も近いので、海外のCVC的な人たちが来てもいい。そうした環境をつくることによってM&Aを増やす。こうした方法が経済合理性からもスピード的にも良いと思う。
恵まれたことに堺市は大企業が結構多い。圧倒的に強いところで世界シェアが大きいところをえこひいきしても良いと思う。スピードが遅ければ、エコシステムがいつまでたってもできない」(三浦氏)
ビジネスは利潤を上げるためだけにあるものではないが、少なくともスピードの無い事業を持続させるためには別の理由付けが必要になるのだろう。
「サステナブルにすることにもコストがかかる。それが経済合理性だけじゃない文化を残していくべきものであれば、ビジネスとは違うところで決めていけばいいと思うが、そこを混同してきれいなことだけを言うのは良くない。どちらか方向性を示して、それに対して最速で行けばいいと思う」(三浦氏)
クレシェンコ氏からはエコシステムを生み出すためには、人と人とのつながりが最低限必要である一方で、日本人はつながりを生むためのコミュニケーションが上手くないと指摘する。
「エコシステムは端的にいえば出会いとつながりだと思っている。ウクライナで事業を行なった経験と比較すると、日本は横断的なつながりが弱い。学校とか大学、職場の同僚などではつながりが深いが、起業家同士とか金融機関の方々などとはあくまで表面的なつながりでしかないと思う。
例えばマーケティングについて1時間話しましょうといった交流会でも、誰も深いノウハウとかを共有しない。自分の得たコツを他の起業家とか投資家に共有したくない人たちが多く、横断的なコミュニケーションが無いと感じている。そういったコミュニケーションが無いとエコシステムは構築できない」(クレシェンコ氏)
クレシェンコ氏の周りには共感から協力へと進んできた人たちがいるとのことだが、自ら発信し、信頼を獲得するのは「言うは易く行うは難し」であるということをクレシェンコ氏も実際に感じている。
「(Floraのある)京都には商工会議所など支援組織がいくつもある。京都大学にもお世話になっている。お世話になっている方々が大勢いるが、(共感や共有は)まだまだだと感じている」(クレシェンコ氏)
大津氏はエコシステムを「新しいビジネスが生まれやすくなる仕組み」と捉え、関西圏ではそうなりつつあると評価している。
「新しいビジネスをつくるとき、従来は資金調達も含めて1から100まで自分でやらなくてはできなかった。いまは自治体、投資家、企業、金融機関などの力を借りて、何億もの資金調達をしてやりたいことをど真ん中でやることができるようになってきている。
社会課題の解決を重視している投資家も増えてきており、私たちはかなり運よくエコシステムに乗れたと思っている。ビジネスが生まれやすくなるという意味ではエコシステムの必要性とか意義を感じているところ」(大津氏)
エコシステムの形成において重要なものとして、ステークホルダー間で共有できる、特にソーシャルなベクトル、インパクト指標を大津氏は挙げている。
「組織には利益とかKPIとか重要な指標があると思うが、それだけを中心に回すというのでは連携は難しい。私たちにはESG投資家も入っていて、ソーシャルインパクトを指標として同じ方向を向いた仲間が集まってきている。自治体と連携する時も、これだけの人が年収をアップしてほしいとか、これだけの人が就労支援を受けてほしいといったインパクトの指標を明確にすることで、それぞれの(ステークホルダーの)目的は違っても安心して手を組んでエコシステムをつくることができる。
私たちがソーシャルスタートアップだといわれているのは利益を出しつつもこれだけのインパクトを出しますということを宣言しているからで、そうでないNPOや自治体とも手を組むことができる」(大津氏)
大津氏の話に続き、石山氏からはステークホルダーで共通する指標を持つことの難しさが指摘された。
「ESGスコアやSDGs指標などがだんだん一般企業の中で受け入れられてきている。資本市場の中でそれらができてきたことによって、皆さんが話すような環境ができてきたと思う。ただ、まだまだ民間と自治体が一緒に何かをしようとするときに、その指標が使えないという感覚がある。世の中の大きな流れとしてはそうだが、どうやって民間とか教育機関とか全く違う業態が一緒に手を取り合うか、そうしたときに何を指標とするかというところが、次のステージで求められていくのだろう」(石山氏)
自治体と連携する時には課題の社会性が連携の助けになることも多い一方、自治体特有の難しさもあるようだ。
「民間と自治体が一緒に新しいイノベーションのモデルをつくるということをやってきた。自治体においては長期的な戦略にそれが組み込まれればできるのだが、単年度で終わってしまったり、担当者が変わってしまったり、続けて行く人が誰もいなくなってしまうということが多い。大きな長期的ビジョンの中で、連携をどう位置付けるかという、最初が大事だと思う」(石山氏)