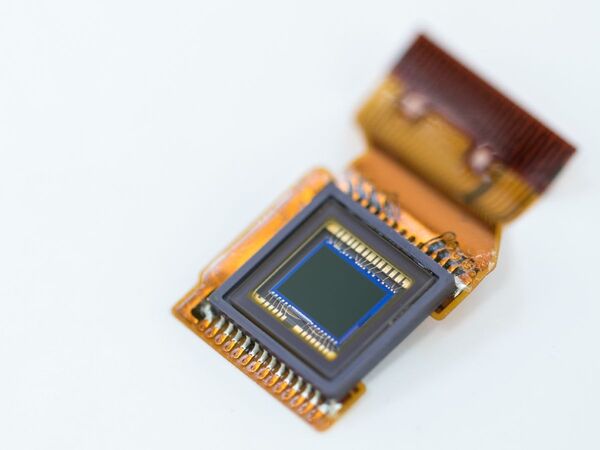企業の新規事業担当者が最低限理解すべきこと
国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。三井不動産の光村圭一郎氏による技術とイノベーションについてのコラムをお届けします。
世の大企業は、ちょっとした“新規事業ブーム”の只中にある。
2016年1月以降の日本経済新聞を検索してみると、内容に“新規事業”という語句が含まれている記事は約920本(2016年9月19日時点。朝、夕刊含む)。毎日数本は、新規事業関連の記事が紙面に掲載されている計算だ。実際、多くの大企業で続々と新規事業部門が立ち上がっている。
ところで、そもそも大企業における“新規事業”とは何か。ひと言で言えば、自社が手がけていない新たな領域でのビジネスということになるだろう。しかし、新規事業部門で働く場合、より詳細な定義を理解する必要があるのではないかと、筆者は考えている。
新規事業はしばしば、イノベーションという言葉とも置き換えられる。筆者は本稿で“5種類のイノベーション=新規事業のパターン”を提示する。そして、その取り組み方は各パターンでまったく異なると考えている。つまり、イノベーションや新規事業をこのレベルの解像度で理解しておかないと、適切なリソース配分ができなかったり、見当外れなアクションに注力して、失敗を繰り返したりするリスクが高まるだろう(そうでなくても、新規事業に失敗は付き物)。
なお、本稿の内容は、筆者が担当する三井不動産のコワーキングスペース“31VENTURES Clipニホンバシ”で得た知見や、Clipニホンバシの運営で提携関係にある“チーム・ゼロイチ”のナレッジに依拠するものだ。Clipニホンバシではこの考え方に基づくプログラムやイベントを各種開催しているので、関心がある方はぜひ参加いただきたい。
顧客の3階層
新規事業について考えるとき、まず整理する必要があるのが“顧客の成熟度”だ。
本稿では顧客が置かれている状態を、“不安”、“問題”、“課題”の3段階で表現する。不安がもっとも漠然としており、課題が一番明確な段階だ。
顧客がもっともサービスを購入しやすいのは課題フェーズにあるとき。顧客が自ら抱えている状況に対し、具体的にどのようなサービスが提供されれば解消されるのかがわかっている状態を指す。問題フェーズはもう一段抽象的。自分の抱えている状況の原因は理解できているが、それがどのようなサービスによって解消されるのかまではわかっていない状態である。不安フェーズはさらに漠然としている。理由は不明だが、自分に良くない状況が起きていることだけはわかっている状態だ。
体調に置き換えてみよう。「最近、体調が悪くて気分が晴れない」とモヤモヤしている状態が不安。それが“太りすぎ”に原因があると気づいているのが問題。そして、肥満を解消するために「自分には運動が向いている」と気づいているのが課題だ。
課題フェーズの人にスポーツクラブを勧めれば、一定の割合で入会に至るだろう。しかし、「肥満が原因で体調が悪い」と考えている問題フェーズの人は、運動以外にもエステや断食などのさまざまな選択肢があるため、スポーツクラブと言われてもピンとこない。不安フェーズの人ならなおさらだ。
課題フェーズにある顧客のニーズは明確だ。ゆえに、企業はそのニーズに応えるサービスを開発しようとする。それは一定レベルで成功するかもしれないが、顧客のニーズが見えているのはライバルも同じ。競合サービスが次々に生み出され、激しい競争にさらされることになる。
逆に、不安フェーズにある顧客にサービスを売ることは極めて難しい。しかし、不安から適切なソリューションを編み出し、それを理解できる顧客を発見し、その市場を育てることができれば、そのマーケットにおいて独占的・優越的ポジションを占めることも可能だ。
真のマネタイズモデルを理解する
新規事業を考える上でもうひとつ重要なのが“マネタイズ”、つまり顧客が「何に対しておカネを払うか」というモデルの確立だ。
顧客がサービスを購入するとき、顧客が真に価値を感じているポイントは何なのか。背景にある顧客の本音を見出し、理解することが重要だ。そしてこの理解は、企業がそのサービスを自ら売り、顧客の声と向き合うことで初めて可能となる。逆説的に言えば、それ以外の企業にはそのサービスの本質的なマネタイズモデルが理解できていないケースが多い。表面的に見えるモデルと、サービスを提供している企業のみが知るモデルとが異なるケースも少なくない。
イノベーションは5パターンある
それでは、顧客の3階層とマネタイズモデルの考え方を用いて、イノベーションをパターンで分け、それぞれの基本的なアクションを整理してみよう。
企業がマネタイズモデルを熟知しているビジネス領域では、その顧客の多くが課題フェーズにあると考えられるが、このような領域でもイノベーションは可能だ。
パターン1:シェア拡大型
パターン2:リプレイス型
いずれのパターンも、顧客のニーズが明確に見えている中、それに応えていくことで売上の拡大を目指す。1の“シェア拡大型”は、既存サービスを軸に、きめ細かく商品のラインアップを拡大する。2の“リプレイス型”は、新しい技術や素材を既存のニーズに掛け合わせることで生み出される。
上述のとおり、顧客のニーズが明確な分、参入する競合も多くレッドオーシャン化する領域ではあるが、1、2のアクションをスピーディーに展開することで優位を占めることも可能だ。
パターン3:ブルーオーシャン型
3の“ブルーオーシャン型”は、企業がマネタイズモデルをまったく理解しておらず、顧客の多くが不安フェーズにある状態におけるイノベーションだ。上述のとおり、このパターンは極めて難易度が高い。アイディアが斬新過ぎて、社外の顧客はおろか社内からも理解されないケースが多いだろう(既存事業とマネタイズモデルが違いすぎて、社内の理解が得られない)。
このパターンに取り組む場合の方法論については別稿に譲るが、仮説、プロトタイプ設計、最初のひとりの顧客の発見、顧客教育による市場の拡大など、さまざまなプロセスを積み重ねる必要がある。
パターン4:新市場ヨコ展開型
既存サービスであっても、それをマネタイズモデルが確立されていない市場に持ち込むことで、売上拡大を実現するパターンもある。日本で売れているサービスを海外の国に持ち込む場合がこのパターンだ。その際、ターゲットとなる市場の成熟度が日本と異なれば、マネタイズモデルも変わってくる。サービスの改良(ローカライズ)や売り方の革新などを通じて、新たなマネタイズモデルを発見しなければならない。
パターン5:オープンイノベーション型
社内でマネタイズモデルを持っていないのは3や4と同様。しかし、特に3と異なるのが、“マネタイズモデルを知っている社外パートナーとの連携”によってイノベーションを実現する“オープンイノベーション型”だ。
自社内にマネタイズモデルがないからといって、世の中の誰もがそのモデルを発見していないというわけではない。ここで注目すべきなのが、ベンチャー企業の存在だ。
ベンチャー企業は、乱暴な言い方をすれば大企業が挑戦できない未知のマネタイズモデルの発見と顧客教育に、いち早く取り組んでいる企業と言うことができる。一方、大企業は、新しいサービスに取り組もうとすると多くのカベに直面する。そのサービスの市場が既存ビジネスに比べてあまりに小さい(小さく見える)、エビデンス重視の既存の意思決定システムでは斬新なアイディアが評価できない、などなど。大企業が知らないマネタイズモデルを、ベンチャー企業が知っているという構図が成立する。
昨今、大企業で注目されるオープンイノベーションの本質はここにある。ベンチャー企業が見出し蓄えたマネタイズモデルを、大企業のリソースを活用して一気に拡大することができれば、オープンイノベーションの効果は大きい。
新規事業部門のマネジメントの難しさ
5つのイノベーションは、それぞれ難易度も方法論もまったく異なる。大企業が新規事業部門を立ち上げるとき、そこで目指すべきイノベーションはこの5パターンのうちどれが主軸になるのか。部門のリソースを、どのパターンにどれだけ配分するのか。この分類に基づき、マネジメントする必要性が問われている。
■関連サイト
31VENTURES
光村圭一郎(こうむらけいいちろう)

三井不動産株式会社 31VENTURESアクセラレーター 1979年東京都生まれ。(株)講談社にて週刊誌編集者として勤務した後、2007年に三井不動産入社。オフィスビル開発、プロパティマネジメント業務、部門戦略策定等の業務を経て現職。主なミッションは「スタートアップと大企業の事業共創の実現」。その実験場として2014年、東京・三越前に「Clipニホンバシ」を自らプロデュースし、開設。KDDI「∞Labo」、青山スタートアップ・アクセラレーション・センター等のメンターを務める。