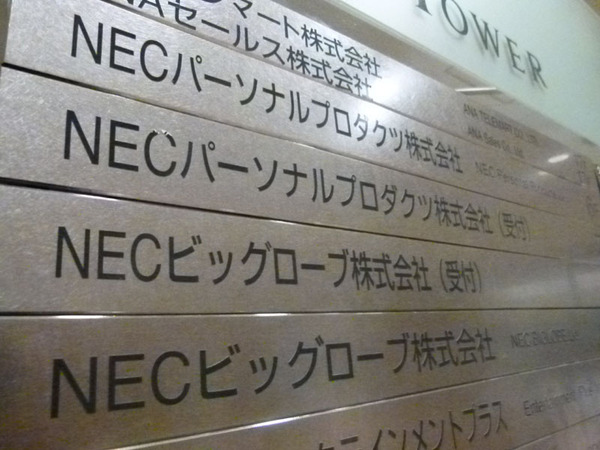NECとレノボの提携は、どんなメリットを生むのか
PC市場において国内最大シェアを誇るNECと、世界第4位の市場シェアを持つレノボが、2011年6月を目標に、NEC・レノボ・ジャパングループを発足し、レノボが51%、NECが49%を出資する合弁会社「Lenovo NEC Holdings B.V.」を設立すると発表した。
合弁会社の傘下には、新たに設立するNECパーソナルコンピュータ株式会社(NECの100%子会社であるNECパーソナルプロダクツからパソコン事業を分離)と、レノボの日本国内でのPC事業を行うレノボ・ジャパン株式会社を収める。国内のPC事業は、それぞれのブランドを維持したまま推進することになる。
NECの遠藤信博社長は「グローバルPCマーケットで第4位のレノボの力と、国内市場ナンバーワンのNECとの戦略的提携により、大きな強い力を生み出すことができる。NECの企画・開発、品質の強みに加えて、レノボが持つワールドワイドのスケールメリットを生かした調達が可能になる。これにより、国内市場における圧倒的なナンバーワンシェアを目指す」とする。
一方、レノボグループのユアンチン・ヤンCEOは「中国でナンバーワンシェアを持つレノボは、今回の提携によって、日本でもトップシェアを獲得することになる。これにより、世界3大市場のうち、2つの市場でトップシェアを得られる。日本におけるマーケットリーダーとしてのポジションが強固なものになる」とした。
さらに今回の提携にあわせて、レノボが新規に発行する1億7500万ドル相当の株式(レノボ発行株式の約2%)をNECが引き受けることについても言及した。「長期的な提携関係を結ぶという意味がある」と語る。
NECにとってパソコン事業は重荷だったのか?
今回の提携は、NECにとって、避けては通れない選択肢のひとつだったといえる。
事業構造の転換を図るNECにとって、収益性の波が大きい事業の再編は早急の課題となっており、ルネサステクノロジーと統合した半導体事業、カシオ日立モバイルコミュニケーションズと統合した携帯電話事業とともに、PC事業の再編も俎上にあがっていたのは事実だった。
同社関係者は、約1年前からレノボと提携の話が進んでいたことを明らかにし、PC事業の再編は、遠藤社長就任後からの重要課題のひとつとなっていたことを裏付ける。
遠藤社長は「今回の提携は、PC事業を譲渡するというものではなく、イコールパートナーとして展開するもの。将来的に、NECのPC事業を、レノボに100%譲渡するといった話は一切ない」とするが、その一方で、レノボには、5年後に合弁会社への出資比率を引き上げることができる条件がつく。
NECにとって、最大のポイントは、収益性の確保だ。
NECのPC事業は、国内トップシェアという位置付けにあることから、フルラインナップの品揃えを余儀なくされる。しかし、同じ条件を持つ国内競合他社が、グローバル展開を強化することで出荷台数を拡大。NECの年間270万台(2010年度見込み)の出荷規模に対して、同じくフルラインナップ戦略をとる富士通は年間580万台と2倍規模の出荷台数を誇る。
さらに、ノートPCに特化している東芝は2010年度見込みで、2000万台以上の出荷計画を掲げており、NECと比較してざっと10倍の出荷規模。収益性に与える影響は歴然ともいえる。
海外勢となるとさらに出荷規模は大きくなる。世界トップシェアを誇る米ヒューレット・パッカードは年間6400万台ものPCを出荷。NECとの差は約24倍にも達する。HPと同じフルラインナップを求められるNECにとっては、調達、開発、物流面において、状況が圧倒的に不利なことは一目瞭然だ。
今回のレノボとの提携が、こうした課題の解決が図れることは大きい。
とくに調達という観点では、レノボの世界第4位という市場シェアを背景としたメリットを享受でき、収益改善への寄与が期待されるからだ。

この連載の記事
-
第35回
ビジネス
首位を狙わないキヤノンのミラーレス戦略 -
第34回
ビジネス
NEC PCとレノボの合弁はなぜ成功したのか? -
第33回
ビジネス
シャープ復活の狼煙、その切り札となるIGZO技術とは? -
第33回
ビジネス
任天堂はゲーム人口拡大の主役に返り咲けるのか? -
第32回
ビジネス
日本IBMの突然の社長交代にみる真の狙いとは? -
第31回
ビジネス
脱ガラパゴス? 国内TOPのシャープが目指す世界戦略 -
第30回
ビジネス
これまでの常識が通じないAndroid時代のインフラ開発 -
第29回
ビジネス
ビッグデータは我々になにをもたらすのか? -
第28回
ビジネス
Macの修理を支える、老舗保守ベンダーが持つ“2つの強み” -
第27回
ビジネス
スマホ時代に真価を発揮する、多層基板技術ALIVHとは? -
第26回
ビジネス
富士通が「出雲モデル」「伊達モデル」を打ち出したこだわりとは - この連載の一覧へ