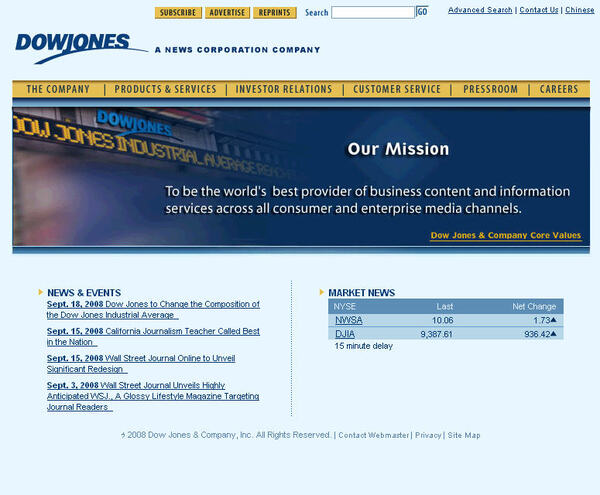サブプライム・ローンの暴落に始まったアメリカの金融危機は、1930年代の大恐慌以来の深刻な事態に発展し、1ドル=100円も、日経平均1万円も、米国のダウ平均1万ドルも一挙に割れる、すさまじいことになった。これを「アメリカ金融資本主義の終わり」と嘲笑し、「これからは、やはりモノづくりだ」と製造業への回帰を主張する向きもある。そうだろうか。
米国はゼロ成長だが日本はマイナス成長
今度の危機の影響で米国はゼロ成長になるといわれているが、日本の今年4~6月期の実質GDP成長率は年率マイナス3%である(関連資料)。株価の下落率も、この1ヵ月でダウ平均が25%下がったのに対して、日経平均は32%下がった。これはOECD諸国の中で最大だ。
日経平均の推移
「震源地」の米国より、デリバティブをほとんど保有していなかった日本のほうが打撃が大きいのは、資金繰りに詰まった外国人投資家が日本から資金を引き揚げたためだといわれている。逆にいうと、海外からの投資が減ったらもたないぐらい日本経済は脆弱なのだ。
さらに円高で輸出企業の採算が悪化し、8月の貿易収支は26年ぶりに赤字に転じた。これまで日本経済の緩やかな回復を支えてきたのは、円安政策による輸出産業の収益だったので、輸出が不振になると、日本経済はまた長い停滞に入るだろう。
技術力はあるのにITは世界市場で壊滅状態
しかし問題は円高ではない。本来は、通貨が強くなるのはいいことだ。個人金融資産が1500兆円もある日本では、ここ数ヵ月で円が10円高くなったおかげで、資産価値は1.4兆ドルも増えたのだ。ところがその半分以上をゼロ金利に近い預金で運用しているのでは、資産は活かせない。
さらに深刻なのは、製造業に代わる新しい産業が育っていないことだ。日本がモノづくりに強いことは確かだが、コストが1/10以下の中国に勝てる工業製品は限られている。製造業で稼げなくなったら、ITやサービスで稼がなければならないが、日本のIT産業はグローバル市場では壊滅状態だ。その原因は、日本人がITに弱いからではない。日本の通信インフラは世界一といわれ、技術力も高い。問題はその技術力を活かせないことである。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ