Rubyを使う野望
―――どういう経緯で、fairyとROMAの構想にたどりついたのでしょうか?
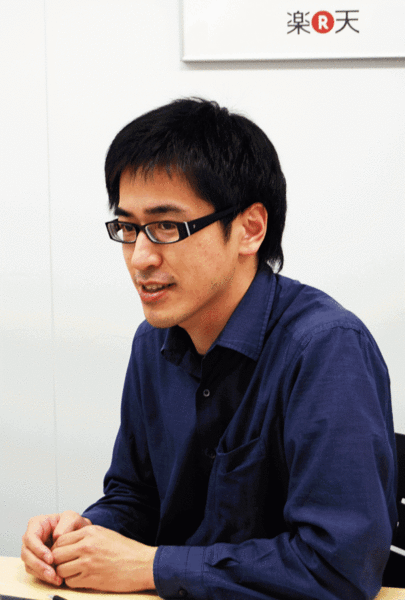
楽天(株)楽天技術研究所 森正弥さん(33歳)
外資系コンサルティング会社に8年3カ月在籍後、2006年9月に楽天株式会社楽天技術研究所へ最初の専任メンバーとして入社
森:最初に「Rubyを使って何を作るか」をブレインストーミングしたとき、いろいろな議論が出ました。その中で、要求の方向が2つあることが分かりました。その1つが「お手軽さ」を追求するという方向、もう1つが「高速性」や「大規模」という方向でした。でも、この2つは無理に融合させると、どちらの機能も中途半端な「どっちつかず」になってしまう危惧もありました。そこで、fairyとROMAの2つのプロジェクトに分けるという結論に達したのです。
「お手軽さ」は、プログラマが誰でも自由に使えるという、まつもとさんが持っているRubyの思想「Enjoy Programming」に近いところを狙ったものです。さらに、大規模なものを作りたいという野望もあり、そこでROMAというわけです。
また、システムをレイヤーとして見たとき、「処理を分散させる」部分と「データを分散させる」部分があります。そこで、それぞれをfairyとROMAに託しました。
技術の楽天を目指す!
──最初に、Rubyを使って何を作るのかをブレストしたとのことですが、なぜRubyに白羽の矢が立ったのですか?
まつもと:楽天代表の三木谷さんには「Rubyで何かを作りたい」という思いがあったようです。一昨年、僕は「師匠筋」にあたる東京大学の米澤明憲教授に頼まれて講演をしました。そこで、米澤教授が楽天技術研究所の技術顧問をされていることを知ったのです。それで、楽天の役員の方々や森さんと話をする機会があり、そこで「楽天は『技術の楽天』というイメージがない。『技術の楽天』というカラーをきちんとアピールしていきたい」と言われました。
──そこで、『技術の楽天』のテーマの1つとして、Rubyを考えたということですか。
まつもと:楽天はもともとJavaとかPHPを使っていて、オープンソースについても理解がある会社です。そのうえ、オープンソース一辺倒でもなく、商用ソフトウェアもいいものは使うという柔軟なスタンスがあります。また、PHPを使っていたことで、言語処理系のパフォーマンスがクリティカルなものではない(言語処理系の処理速度が全体の速度を決めてしまうわけはない)ということも理解していました。
楽天から発信する技術のプラットフォームとして言語に何を選ぶかを考えるとき、「地方」とか「日本」ということを大事にしたいという思いがあると聞きました。そこで、開発者が日本人の僕である国産技術のRubyを扱うことを決めたそうです。楽天でRubyを使いたいという話を受けて、僕は「それでは、何かお手伝いできることがあるかもしれませんね」と返事しました。それで、去年の6月に楽天技術研究所のフェローという肩書きをもらい仕事を始めたわけです。

この連載の記事
-
第68回
ビジネス
『オバマ現象のからくり』(田中慎一) -
第67回
ビジネス
AMN新社長“ブロガー”徳力氏に聞く -
第66回
ビジネス
「完璧な上司なんて、いませんよ」 -
第65回
ビジネス
フランソワ・デュボワ 『デュボワ思考法』 -
第62回
ビジネス
こんなに差が出た! 30代給料の現実 -
第59回
ビジネス
地下巨大施設! プロジェクトは成功した -
第56回
ビジネス
エンジニアの秘められた家族生活 -
第55回
ビジネス
IT業界で10年泥のように働いてませんよ -
第54回
ビジネス
カシオG'zOneのデザインが変わったワケ -
第52回
ビジネス
“変わり種商品”に隠れたビジネス戦略 -
第52回
ビジネス
日本の家電ベンチャー、異例の存在 - この連載の一覧へ

































