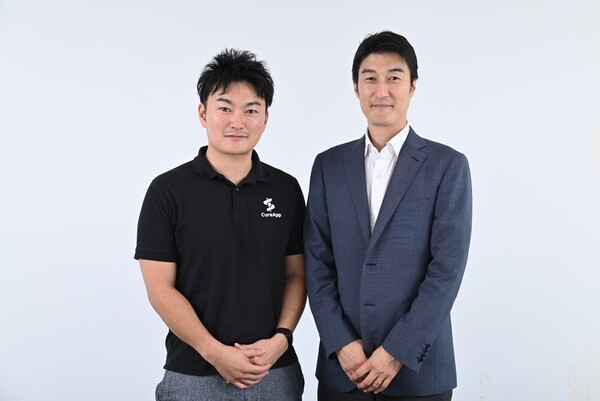新しい概念の治療手法「治療アプリ」を開発 知財体制も充実させ普及と拡大に挑む
【「第5回IP BASE AWARD」スタートアップ部門奨励賞】株式会社CureApp 代表取締役社長 佐竹 晃太氏インタビュー
この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」に掲載されている記事の転載です。
株式会社CureAppは、医薬品や医療機器といった既存の治療とは異なる「治療アプリ」という新たな治療アプローチに取り組む医療系スタートアップだ。知財活動には2014年の設立時から積極的に取り組んできた。大手製薬会社等との共同研究開発提携や、事業展開に向けた交渉に活用している。2023年には専任の知財担当者を設置して社内の知財体制を強化し、市場の拡大を進めている。代表取締役社⻑の佐竹晃太氏と開発統括取締役の鈴木晋氏に同社の事業と知財戦略についてお話を伺った。

株式会社CureApp 代表取締役社⻑/医師
佐竹 晃太(さたけ・こうた)氏
慶應義塾大学医学部卒、日本赤十字社医療センターなどで臨床業務に従事し、呼吸器内科医として多くの患者様の診療に携わる。2012年より海外の大学院に留学し、中国・米国においてグローバルな視点で医療や経営を捉える経験を積む。米国大学院では公衆衛生学を専攻する傍ら、医療インフォマティクスの研究に従事する。帰国後、2014年に株式会社CureAppを創業。現在も診療を継続し、医療現場に立つ。上海中欧国際工商学院(CEIBS)経営学修士号(MBA)修了、米国ジョンズホプキンス大学公衆衛生大学院公衆衛生学修士号(MPH)修了。
医療機器として「治療アプリ」の開発と実用化に挑む
株式会社CureAppは、医療現場で医師が患者に処方する治療アプリを研究開発、提供している。禁煙治療、高血圧症、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)、アルコール依存症、がん、慢性心不全、慢性腰痛症の7つの領域で治療アプリの開発と実用化に取り組み、禁煙治療と高血圧治療の2つのアプリは薬事承認取得および保険適用を受け、医療機関で処方されている。
治療アプリは、薬の処方や手術といった従来の治療法とは異なる、新しい概念の治療手法だ。一般的なヘルスケアのアプリとの最大の違いは、医療機器として開発されており、薬事承認や保険適用を受けている点にある。
「治療アプリは既存のヘルスケアアプリとは開発のプロセス自体から大きく異なります。患者さんの病気を取り扱うものなので、しっかりと品質を担保するような厳格な開発体制を取っています。そのうえでアプリに搭載されるメッセージ、動画、それらを発信するアルゴリズムなど、医学的な知識をもとに専門チームによって開発されています」(佐竹氏)
薬事承認や保険適用には、厚生労働省の厳格なルールに従って臨床試験や治験を行い、効果を証明しなければならない。そのため一般的なソフトウェア開発とは異なり、医療機器としての専門的な体制が必要になるわけだ。
鈴木氏は、医療機器として開発する理由について、こう補足する。
「目的が治療であるため医療機器でなければいけません。例えばナイフとメスの違いのようなものです。どちらも刃物であることは同じですが、治療に使えるのはメス。医療機器としての品質や有効性、安全性が確かめられているからです。同様に我々のアプリも医療現場に実装するために薬事承認の手続きを経ることは欠かせないのです」
同社の治療アプリは医師と患者が二人三脚で使用するため継続率が高いのも特徴だ。
「例えばダイエットのアプリをダウンロードしても、1週間くらいでやめてしまう人が多いと思います。でも、治療アプリは患者さんが自分一人で使うのではなく、通院している病院で医師と一緒に使っていくので継続力が高い。処方薬でも最後まで飲み続けるのは約半数というデータがありますから、お薬以上にきちんと使っていただくことで効果が期待できるのです」(佐竹氏)
創薬×ITをうまく融合させた開発体制が強み
治療アプリは、欧米を中心に海外でも開発が進められており、グローバルでの市場拡大が期待されている。ただし開発においては、臨床試験や治験といった創薬の開発体制とソフトウェアの開発体制の両方の側面が必要であるため、既存の製薬会社やIT企業が単独で参入するのは難しいそうだ。加えて、2017年に成立した臨床研究法によって従来よりも臨床研究のコストがかかるようになったことで、後続企業にとっては参入のハードルが高くなっているという。
「ソフトウェアの開発においては、スピード感や柔軟性などが求められます。一方で、創薬や医療機器の開発では規制や基準への適合、安全性の確認など時間をかけてでもしっかり準備することが求められます。我々も創業当初は、エンジニア側とメディカル側がお互いの文化への理解が追い付かずに戸惑うこともありました。しかしそこをうまく融合させて、開発プロセスを確立できたのが当社の強みです」と佐竹氏は話す。
医師である佐竹氏が治療アプリの事業を思いついたのは、米国留学中に読んだ研究論文がきっかけだったという。
佐竹氏は、「それまではアプリを使った治療の概念すらありませんでした。治療アプリについての論文を読んで、治療に関する視野が広がりました。薬や医療機器だけでなくアプリでも病気を治せる可能性があることを知り、これを普及させることはできないか、事業化できるのではないかと気付いたのがきっかけです。帰国後、鈴木さんに話をしたところ共感を得て、CureAppを共同設立しました」と当時を振り返る。
会社設立から約10年という長い開発期間を経て、現在は禁煙治療と高血圧症の治療アプリが実際に病院で治療法として採用されているという。
「薬のような副作用を気にせずに使え、薬の種類や量を増やしたくないという患者さんに喜んでいただけています。医師からは、アプリを使って患者さんの状態を把握し共有できるので、診察においてもコミュニケーションしやすくなったという声を聞いています」と佐竹氏。
鈴木氏は、「とはいえ、治療アプリは魔法ではありません。アプリの利用を通じて、患者さん自身が生活習慣や意識を変えていくことで治療が進んでいきます。その点を医師にも患者さんにも十分に理解してもらうことが大事だと考えています」と付け加えた。
治療アプリの効果については学会でも発表している。2023年の日本高血圧学会総会では、実臨床の結果として降圧データを公開。全国の医療機関で実際に処方された治療アプリに入力された血圧データを解析し、アプリを使用して12週後の収縮期血圧の変化を具体的な数値を示して発表。65歳以上の患者(最高齢87歳)を含む、幅広い年齢層で治療アプリを用いた降圧療法の効果が示された、とした。
CureAppでは治療アプリの対象領域を広げるために、製薬会社や研究機関とも連携しながら開発を進めている。2020年にはがん領域に知見のある第一三共株式会社と共同開発提携、2022年にはサワイグループホールディングス株式会社とNASH(非アルコール性脂肪肝炎)領域における治療アプリの共同開発とライセンス契約を結んでいるということだ。
専任の知財担当を迎え入れ、知財活動がレベルアップ
IP BASE AWARDでは、同社の事業展開に連動させて知財戦略が練られていることや、治療アプリという新しい領域において医療領域での知財戦略とITソフト領域での知財戦略を融合させた知財活動が評価された。
「後続の競合企業が出てくるのは、これからになるでしょう。産業自体が新しいからこそ、いまはまだ自分たちにしか見えていないものがあります。こうしたポイントを早めに押さえていくことで業界のリーダーであり続けたいと思っています」と鈴木氏。
発明の内容は、治療×ソフトウェア技術のほか、行動変容、処方の仕方、医療システムとの連携など、実際の医療の現場の中で見つかるアイデアも多いそうだ。
創業から5年間は佐竹氏と鈴木氏の2人が主な発明者であったが、2019年以降は職務発明規定を制定し、全社的な発明発掘にも取り組んできたという。さらに2023年には専任の知財担当者として山本也寸子氏が入社したことで社内の発明数が大きく増加しているという。
佐竹氏は「山本さんが専任の知財担当者として入ってからは、これまで以上に組織として戦略的に知財活動を進められるようになりました。この1年では、知財戦略の筋の良さ、確からしさ、またその進め方、特許内容のビジネスとしての価値の出し方などが数段レベルアップしたと感じている」と評価する。
以前は権利範囲などをあまり意識せずに特許出願してしまい、模倣されても証明の難しいものもあったという。山本氏の入社以降は、権利範囲や被疑侵害品の調査可能性を厳格にチェックするようになり、出願件数が増えただけでなく、1件1件の特許の価値が上がっているそうだ。
「1つの単語を抽象化するだけで権利範囲が広がる。この考え方は、ソフトウェア開発におけるオブジェクト指向プログラミングにも通じるところがあると私は思っています。例えば、対象を患者さんではなくヘルスケアを含めた利用者にしたり、治療だけでなく予防も含まれるようにしたり、といったことです。山本さんと出会うまでは、この考え方に気づけなかったのが残念なほど。また、特許を取る意義についてもよく考えるようになり、活用法を意識して特許を検討できるようになったのは大きいです」(鈴木氏)
山本氏の入社後は、社内向けの知財勉強会や研修を開き、知財意識の向上にも取り組んでいるという。以前は一部の社員だけが知財に関わっていたが、山本氏から開発部門にヒアリングして知財を発掘することで、発明者が増えてきているそうだ。
最後に、今後の事業展望について伺った。
「治療アプリそのものだけでなく、治療アプリ処方プラットフォーム『App Prescription Service(APS)』も開発して医療機関に提供しています。『APS』は医療現場で治療アプリの処方や請求の情報を管理するシステムです。このプラットフォームが治療アプリのストアとして機能することで、後続の治療アプリ開発企業の参入が増え、普及が加速することを願っています」(鈴木氏)
「創業当初から“アプリで治療する未来を創造する”というビジョンを掲げ、アプリをつくるだけでなく、ソフトウェアで治療する世界観を臨床の現場につくることを目指して事業を進めてきました。薬と比較するとまだまだ伸びしろがあるので、治療アプリがしっかりと世の中に広まるように力強く推し進めていきたい。世の中には数多くの病気があり、困っている患者さんがいますので、さらに領域を広げてより多くの患者さんの助けになる治療アプリを開発していきたい」(佐竹氏)