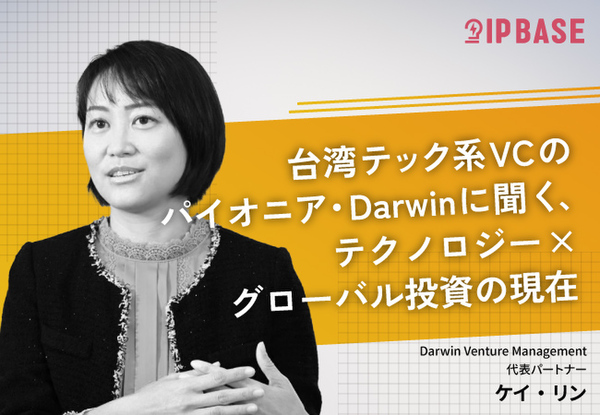iPodを超える発明でも難しい、大学での特許出願の壁
CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長/CEO 山海 嘉之氏インタビュー
この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」(外部リンクhttps://ipbase.go.jp/)に掲載されている記事の転載です。
CYBERDYNE(サイバーダイン)株式会社は、世界初の装着型サイボーグ「HAL」を開発した筑波大学の山海教授が設立した大学発ベンチャーだ。HALは、人の意思に従って動作をする機能を持ち、現在は、医療機器として脳・神経・筋疾患の機能改善治療に利用されている。今でこそ、CYBERDYNEはすべての製品の特許を自社保有しているが、当初は大学を通しての特許出願に苦労したという。大学発ベンチャーにおける知財活動の課題、自分の発明を活かし、世界で成功するために考えておくべきことを山海氏に伺った。

CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長/CEO 山海 嘉之(さんかい・よしゆき)氏
1987年筑波大学大学院工学研究科博士課程修了。2004年に筑波大学発ベンチャーCYBERDYNE株式会社を設立。内閣府F I R S T研究統括、内閣府ImPACTプログラムマネージャー、国際知財戦略委員会委員長(ロボット分野)、国際標準化機構(ISO)のエキスパートなどを歴任。人とロボットを融合する世界初の装着型サイボーグHALの研究開発・実用化、世界初のロボット治療機器HALによるサイバニクス治療・医療保険適用を実現。人・ロボット・情報系を融合する新領域「サイバニクス」で、『人』+『サイバー・フィジカル空間』を扱う革新的サイバニックシステムの研究開発に力を注いでいる。World Technology Award 大賞(2005年)、全国発明表彰(2009)、内閣総理大臣賞(日本ベンチャー大賞、2017年)、紫綬褒章(人間医工学、2019年)ほか多数受賞。
iPodを超える発明でも難しかった大学での特許出願の壁
「SFのようなものを特許にしても意味がない」という差し戻し
装着型サイボーグ「HAL(Hybrid Assistive Limb)」は、装着者の生体電位信号を皮膚に貼ったセンサーで検出し、その情報に基づいてパワーユニットをコントロールすることで、HALが装着者の意思に従った動作を実現する。そして、この意思に従って動作するHALに同期して、筋肉→感覚神経→脊髄→脳へと感覚情報がフィードバックされる。これにより、人の脳神経・筋系とHALとの間でインタラクティブなバイオフィードバックが構築され、脳神経・筋系の機能の改善・再生を促進することができる。
医療用HALは、欧州では2013年から医療機器として認証され、日本でも2015年に医療用下肢タイプが医療機器として承認され、現在は保険適用による治療に利用されているほか、米国でも2017年12月に医療機器としての承認を取得した。現在、治療効果のあるロボット治療機器(機能回復ロボット)の国際プラットフォームとして、10カ国以上で活用されている。
山海氏は、90年代から文科省科研費や経産省NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発プロジェクトの支援を受けながら研究開発を続け、2004年にCYBERDYNE株式会社を設立する。
また、The 2005 World Technology Awardの大賞を受賞。その年にノミネートされた5社のうちのひとつは、Apple社のiPodだ。つまり、iPodを超えるテクノロジーとして評価されたということになる。こうして、CYBERDYNEの技術力自体は世界に広まったが、知財に関してはなかなか簡単にはいかなかったという。
「当時、大学の知財部に特許の取得を申請したら、『特許は製品にするから価値があるもので、こういうSFのようなものを特許にしても意味がない』と差し戻されてしまったのです」
山海氏は大学からの出願を諦め、自分で特許を取ることに。特許を取るための費用はまったくわからなかったそうだが、弁理士を含め約30万円で済んだ。しかしその後、海外展開するには、国際出願が必要と知る。「PCT国際特許出願の手続きに100万円、各国への申請にそれぞれ70~100万円。最終的には、約1500万円かかってしまいました」
資金調達する前の大学発ベンチャーにとっては大きな負担だったが、その4年後の2009年、日本発明協会の全国発明表彰で “サイボーグ型ロボット技術の発明” 21世紀発明賞を受賞。HALの特許には13.7億円の価値があるとの評価を受けたそうだ。
その後、この知財の寄付を筑波大学に申し込むが、どういうわけか譲渡扱いになり、筑波大学は膨大な税金を支払うことになりそうになったが、経緯を説明して一件落着。
「つまり、大学で知財を申請するかどうかを決める際、もし、成功へつながる発明であったとしても、大学の知財担当者がその出口を描けなければ、特許化できないこともあるのです」
大学や政府の研究機関では、業績として特許の数を増やすために、無駄に申請してしまう可能性もある。個人研究であれば、申請自体にかかる国内申請費用の半額は研究者個人の自己負担にするべき、というのが山海氏の考えだ。本当に価値のある知財だと考えているなら、負担する覚悟はあってほしいという。
大学の知財部を通すと、大学や知財担当者の判断に左右され、出願してもらえるまでに1年以上かかるケースもある。
また、山海氏が出願しようとして、大学の知財担当者に『次期尚早だから』と止められた発明が、数年後に改めて出願しようとしたところ、2カ月前に米国で申請されていた、というケースもあったそうだ。申請が早すぎて、特許の期限が残りわずかというケースもあることもある。いずれにしても、国際知財戦略は重要だ。だが、そもそも国際特許を各国へ移行する際の費用規模は、大学が負担できるレベルを超えてしまう。山海氏は、世界展開を目指すのであれば、自己資金を投じてでも適切に各国移行していくことを強く勧める。ベンチャーは、知財がなければ十分な資金調達ができない。知財で最も重要なことは、思う存分に活動するために役立つということにある。
大学発スタートアップのエコシステム形成において、知財とファイナンスは今後より密接でなければならない。経済産業省が「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に手引き」を発表したのは2019年5月になってからだ。
CYBERDYNEと同じく筑波大発のスタートアップである落合陽一氏によるピクシーダストテクノロジーズが、研究室発知財の譲渡対価として筑波大学側に新株予約権を付与する形で研究開発スタートアップとして先を走る取り組みが行われているのは、ここまで山海氏とCYBERDYNEが歩んできた道のりの影響も多分にあるはずだ。
国際知財戦略で、他者に邪魔されず伸び伸びと世界展開する
人体では、体内の細胞膜のチャネルが開閉することで、イオンの流れが起こっている。その微弱なイオン電流を検出し、ハードやソフトに伝え人体とロボット技術を融合するのがHALのコア技術だ。HALを装着するときにセンサーを皮膚に貼るが、じつは、服の上や髪の毛の上からでも検出可能だという。数多くの特許を取得し、多くの学会で論文を発表しているが、技術の基本原理は知財で明確化し、具現化のための裏側の部分は丸めている。例えば、後日、戦略的に分割出願できるようにするための工夫くらいはしておくべきとのことだ。
「91年からプロジェクトをスタートしましたが、研究が未熟な段階での学会発表は控え、原理を創り出し検証できるまで地道に研究し続けました。創設初期の頃は、私と博士課程の学生4人でした。2006年から本格的に資金調達を始めましたが、特許出願は他者に邪魔されず伸び伸びと世界展開するために重要です」(山海氏)
山海氏は、「何かが特許として公開されていれば、ほとんどの技術はコアの部分を回避して突破できる自信がある」という。文書化されていれば、その対象と表現、工夫を読み取り、時間があれば、実現できてしまう可能性はある。アルゴリズムは、簡単に迂回ができてしまう。
大切なことは、自分たちが、思う存分、楽しく挑戦し続けるためには、他者に邪魔されないように先の先を考えて、知財戦略を練り、知財申請を進めておくことだという。
HALを動かすことで新しい特許を生み出し、コアを強くする
2003年は大学TLOが盛り上がり、経済産業省が大学発ベンチャー1000社計画を推進している時代だった。山海氏は、政府が推進するMOTや知的財産マネジメント戦略の一環として、受講生用と講師用のテキストを作成。MOTを学ぶための資料がない時代に、このテキストを作る過程で、技術経営手法を自分なりに色々と発想し、知財戦略も考えるようになったという。
CYBERDYNEでは、HALのコアとなる特許のほか、タイミングを見計って、次々に特許を出願している。
「HALを使うことによって生みだされる新しい特許があります。実際に動かしてみて発見できることが多々ある。こうして先へ先へとすべてが進んでいくわけです」(山海氏)
初期のCYBERDYNEでは、出願した特許はすべて大学に譲渡し、大学からライセンスを受ける形をとっていたが、2014年にCYBERDYNEの社内に知財担当を設置し、大学と連携しつつも、筑波大学と独立した形で知財を運用できるようになった。
「現在は、CYBERDYNEの全製品に関わる知財は、すべてCYBERDYNEが所有しています。大学にもライセンス料を払っています。知財はベンチャーにとっては命。それがあるかないかで企業の価値が決まります。その取り扱いについては慎重に進めてほしい」
企業が生き残るためには知財の発想をもっと柔軟にしなくてはならない
今は、大学における知財活動が促進され、知財の数を競っている時代。また企業では、市場の動向を調べ、有望な領域を探る戦略がもてはやされている。しかし山海氏は、それには懐疑的だ。
「技術をつくり出している研究者であれば、何がその領域のキーになるのか見えている。ライバルが何をしているのかを気にして、周りを見て発想するのではすでに遅いのです」(山海氏)
また、いくら新領域開拓を推進しようとしても、現場ではなかなか別領域へ移行しようとはしないのも現実だ。
「ある技術を推進し事業展開しようとする人たちと、別の技術を推進し事業展開しようとしている人がいる場合、通常、2者は対立します。同じ企業でも、他方の知財戦略は気にも留めないでしょう」
例えば、世界で初めてデジタルカメラのプロトタイプを作った会社はコダックだ。しかし当時のコダックはフィルムで勝負していたため、フィルムを使わないカメラの技術研究に力を入れようとはせず、カメラ分野の知財戦略を推進しなかった。その結果、肝心のフィルム事業は衰退し、別の企業がデジタルカメラの時代の覇者となった。逆に、富士フイルムは、フィルムを捨て、会社の軸足をデジタル系にシフトさせ、さらにフィルム分野で培った知財や技術や企業買収(M&A)で、バイオ・メディカル系に舵取りすることで成功している。
「知財は、必ずしも自分たちだけでつくり出す必要はなく、外から手に入れる方法もある。富士フイルムは必要な技術スタートアップをM&Aすることで、会社を強化している。資金力のある会社はそうすればいい。しかし、ベンチャーは資金力がないので、知財は重要」
知財権は諸刃の剣であることも知りつつ、知財戦略を展開すべき
知財権で勝負できない世界もある。例えば、特許侵害があった場合、国際弁護士をたて、係争する。費用と時間がかさむ。たとえ勝てたとしても、相手の会社は消えてしまって、別の類似の会社が現れ、モグラ叩きが続き、資金は底を尽く。国際特許を押さえたとしても、国によっては効力がなく、その国の裁判では負けてしまうことがある。
また知財が公開されても、類似品ができないほどの技術水準であることも大切だ。その意味では、ハードとソフトが一体化した技術はアドバンテージが得やすい。特に、ソフトの役割は重要だ。
知財権は維持するのも費用がかかる。コストに対してそれほどのメリットはないかもしれない。それでも研究開発スタートアップは知財戦略をを練って、各国移行もすべきだ。国際特許がないと資金調達面でマイナス評価だ。
「創設初期のスタートアップにとっては大きなコストだが、そうはいっても大した金額じゃない。資金調達ができればどうということはないのだから」と山海氏。
最後に、若い世代のスタートアップへの提言をいただいた。
「大切なのは、出口イメージを明確化し、その未来の出口から、今いる位置を見据えてバックキャストさせ、目標達成のための課題を明確化する。そして、その課題がクリアできることが確認できれば、必ず到達できることを意味している。あとはスピードアップ。ひとつひとつ課題を超えていく道は、苦労であっても、楽しくワクワクするものです。とにかく最後までやり抜くのです。そういう熱い人たちには、必ず支援者が現れますから。頑張れ!」