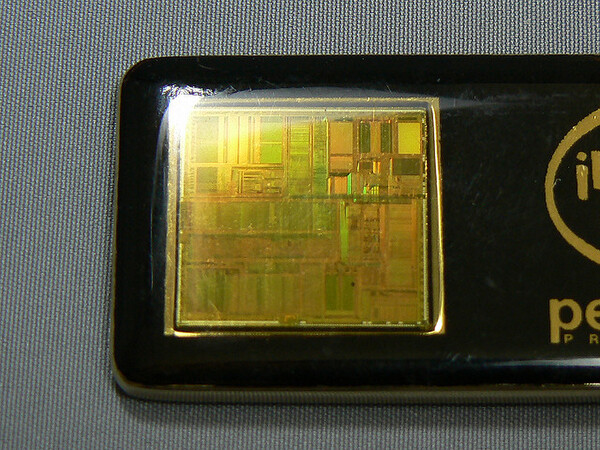今回のCPU黒歴史のネタは、安藤壽茂先生にも指摘された(関連リンク)「バグ付きPentium」の話である。何分18年前という古い話なので、ご存知ない方も多かろうと思う。そのため、まずは歴史的な経緯から説明したい。
NetNewsから火が付き
あっという間に広がったFDIVバグの話題
18年前の1994年10月、米バージニア州リンチバーグ大学のThomas R.Nicely教授が、インテルに対して「Pentiumで非常に小さな値で割り算を行なうと、結果がおかしくなる」というレポートを送ったことに端を発する。インテルはこのエラーが起きたことは認めたものの、「そんな話はこれまでレポートされたことがない」と返答した。
そこで教授は、自身の送った内容とインテルからの返答を添えて、この問題が他のプロセッサー(486や他のPentium、あるいはPentium互換プロセッサー)でも発生するかどうか試してほしい、と複数の知り合いにメールを送り(関連リンク2)、それは直ちにNetNewsに掲載されることになった。
1994年、まだウェブはまったく一般的ではなく、インターネットそのものの帯域ももっと細かった。当時利用されていたのはメール(それもテキストのみ)と、NetNewsと呼ばれるバケツリレー式のテキストデータ配信システム、それとGopherと呼ばれる(やはりテキストベースの)情報検索システム程度である。
この中で、「ウェブページ+掲示板的」な役割を果たしていたのがNetNewsで、筆者の記憶が正しければ、最初に「comp.sys.intel」というNetNewsに投稿されたはずである。この「comp.sys.***」というNetNewsは、インターネットにつながっているマシンを使える多くのユーザーが読んでいた。そして、当時インターネットにつながるマシンを使える人は、圧倒的にコンピューター関係技術者が多かったから、あっという間にこの話はネット中に広まることになった。
ここから事態は加速的に進展してゆく。同年11月7日、「Electronic Engineering Times」(現EE Times、米国で一番歴史が長い電子業界誌)が、これに関する記事を公表。11月21日にはCNNがニュースとして取り上げた。当初インテルはこの問題を認めず、その後には「問題はあるが軽微なもので実害はない」としていた。
インテルは「一般のユーザーでは、この問題に起因して問題が起こる頻度は27万年に一度」と説明したことに対して、米IBMは「一般的な表計算を利用する場合、6時間に1度の頻度で計算が誤りとなる」とこれに反する見解を表明。さらに同年12月12日には、IBMが発売していたPentiumベースのマシンを、この問題が修正されるまで出荷停止にすると表明するに至る。そして、当時Pentium搭載マシンを出荷していた多くのPCメーカーが、これに続くことになった。
12月19日にはNew York Timesがこれに関する記事を掲載。これによって当時は、「Pentium」という言葉が「バグを抱えているもの」の代名詞に使われるほどだった。結局インテルは12月20日に、公式に謝罪を表明。すでに出荷したPentiumにバグがあったこと。そのバグのあったPentiumはすべてバグを修正したものに無償交換すること。およびこの無償交換にともなう費用を4億2000万ドル(後に4億7500万ドルに上方修正)と見込んでいることを発表して、ようやく事態は収束に向かうことになった。
ちなみに、1994年度におけるインテルの売上は115億2000万ドル。純利益は22億9000万ドル(関連リンク3)と発表されていたから、純利益の17%ほどがこれで吹っ飛んだ計算になる。
ここまで騒ぎが大きくなった理由のひとつには、大手PCメーカー、特にIBMの存在が関わっていたことは否めない。IBMは当時、インテルからPentiumやPentium Proを購入してワークステーションやサーバー向け製品を出荷している大手メーカーであったが、同時に競合するCPUである「PowerPC」を推進しているCPUメーカーでもあった。
また、IBMは「Blue Lightning」という486互換プロセッサーもリリースしていたから、インテルとの関係は微妙なものだった。当時からインテル自身と、インテルからコンポーネントを購入してPCを販売しているベンダーの「利益率の違い」は火種になっており、そうしたこともあったためか、IBMはこのバグを過剰に宣伝した嫌いはある。

この連載の記事
-
第781回
PC
Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -
第780回
PC
Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -
第779回
PC
Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -
第778回
PC
Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -
第777回
PC
Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -
第776回
PC
COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -
第775回
PC
安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -
第774回
PC
日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -
第773回
PC
Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -
第772回
PC
スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -
第771回
PC
277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ