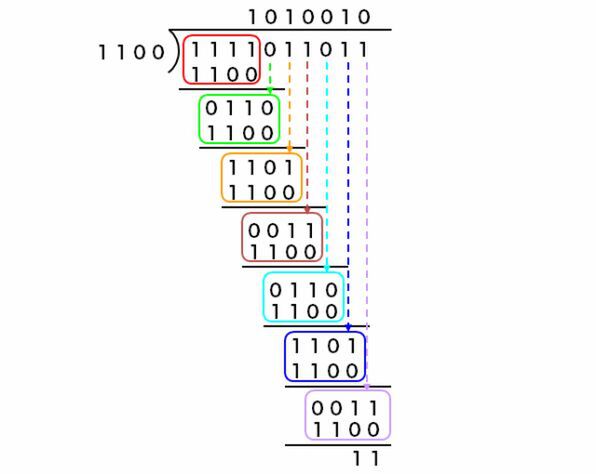インテルのこうした動きは、当然ながら互換CPUメーカーには追い風であった。例えば、問題が露呈してすぐに「Cyrix Instead」という広告を打ったCyrixはなかなか優秀だったと思う(言うまでもなく「Intel Inside」のパロディだ)。他にも当時のNetNewsでは、「Intel Insane」(インテル狂ってる)が流行ったことを筆者も覚えている。
その追い風がそれほど続かなかったのは、一度全量交換を決めてからの、インテルの動きが素早かったためだ。ほどなくIBMなどからの製品出荷も再開されることになった。
Pentiumで採用された割り算の方式
SRT法とは?
そもそもPentiumのバグ問題とは何だったのか? それは「割り算を行なう時に変な結果になる場合がある」というものだ。除算命令である「FDIV」を実行する時のみ発生したので、俗に「FDIV問題」(FDIV bug、FDIV flaw)と呼ばれている。これはPentiumの世代から、計算の高速化を狙って導入した「SRT法」に起因する。
元々インテルでは486まで、「引き放し除算」(nonrestoring divisionとも)という方式を使っていた。例えば「987÷12」を計算する場合、人間は図1のような方法で計算する。
ところがCPUの計算は、当然二進数になる。「987」は「1111011011」で、「12」は「1100」になる。そこで2進数で同じように計算すると図2のようになる。
まず上位4桁(除数の1100が4桁だから)をマッチングすると、商が「1」と出る。ここから1bit右にシフトして、先程のあまりの「011」に次の「0」を加えて、「0110」と「1100」をマッチングし、商が0になる。そんな調子で、1bitずつシフトしながら割り算を繰り返してゆき、最終的に商が「1010010」(82)で、あまりが「11」③と計算できるわけだ。こうして「シフト演算+減算」だけで、除算は構成できる。
言うまでもなく、この方式は時間がかかる。なにせ1回につき1bitずつしか処理できないからだ。例えば32bit同士の演算を考えた場合、最悪なのは非除数(割られる数)が32bitで、除数(割る数)が1bitのケースだ。この場合、減算32回とシフト31回が必要になるから、合計63回の演算をしないと結果がでない。
Pentium以降で採用されたSRT法(SRT Division)とは、一度に2bitを演算する方法である。この方式は開発者であるSweeney、Robertson、Tocherの名を取って、SRT法と呼ばれている。そもそも引き放し除算の場合、1bitずつの処理になるから、商は常に「0」か「1」である。では2bitならばどうかというと、商は0、1、2、3のいずれかになる。そこで、A÷Bを計算する場合には、以下の3つを同時に計算する。
- ①A÷B
- ②A÷2B
- ③A÷3B
この3つの計算により、以下のように判断できる。
| ③の商が「1」 | 商は「3」 |
|---|---|
| ③の商が0、②の商が「1」 | 商は「2」 |
| ③と②商が0、①の商が「1」 | 商は「1」 |
| ③②①の商が「0」 | 商は「0」 |
この方式は一見すると、手間がかかるように見える。だが、2倍は2進数の場合シフト演算1度で済むし、3倍は「1倍+2倍」で、これも比較的容易である。何より、①~③を同時に行なえるから、回路規模こそ増えるものの時間は短縮できる。

この連載の記事
-
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -
第763回
PC
FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -
第762回
PC
測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -
第761回
PC
Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -
第760回
PC
14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -
第759回
PC
プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -
第758回
PC
モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -
第757回
PC
「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ