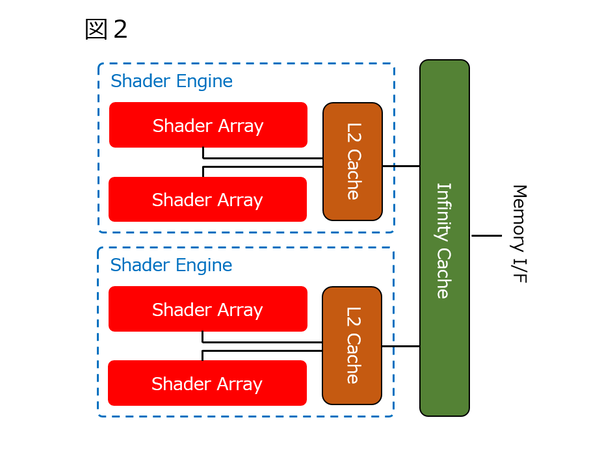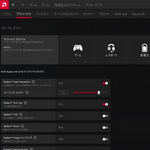ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第653回
RDNA 3は最大10240SPでRadeon RX 6900 XTを遥かに超える性能 AMD GPUロードマップ
2022年02月07日 12時00分更新
RDNA 3は最大10240SPとなり
Radeon RX 6900 XTを遥かに超える性能を確保
シェーダー・アレイを2つまとめたのがシェーダー・エンジンとされる。2560SP構成だが、ラインナップとしてはこの2560SP構成が「当面は」最小構成になるものと思われる。下図の構成が、当面ディスクリートの最小構成になるであろう。
将来的には、シェーダー・アレイが1つという可能性もあり得るが、単にWGP数を減らした2シェーダー・アレイになるのかもしれない。
この上位モデルが、シェーダー・エンジン×2である。ここまではモノリシックなダイでの構成だろう。ちなみにこの2シェーダー・エンジンの構成だと5120SPとなり、Navi 21の最大構成(Radeon RX 6900 XT)と等しいことになる。
この上位に位置すると思われるのが、3ダイ構成で4シェーダー・エンジン構成である。端的に言えば、上図の構成からインフィニティー・ファブリックを抜いて(抜かない、という可能性もあるのだがやや構造的に難がありすぎるので省いた)、それで1つのGPUダイを構成する格好になる。
この構成だと最大10240SPとなり、現在のRadeon RX 6900 XTを遥かに超える性能を確保できることになる。つまり、図1・2はモノリシックダイでの提供になり、図3はマルチダイ構成になると想定している。
| GPU | SP数 | |
|---|---|---|
| 図1 | Navi 33 | 2560SP |
| 図2 | Navi 32 | 5120SP |
| 図3 | Navi 31 | 1万240SP |
1万240SPというのは、NVIDIAのGA102の最大構成(84SM/10752 CUDAコア)にやや劣る程度の規模感になるが、ベンチマークの結果で言えばRadeon RX 6800 XT(4608 SM)とGeForce RTX 3080(8704 CUDAコア)が良い勝負ということを考えた場合、(動作周波数の違いを無視して言えば)1万240SP構成だとAmpereで言えば20000 CUDAコア弱の性能に相当する計算になる。普通に考えれば十分という気もする。
RDNA 3の製造プロセスは
TSMCのN5かN6
ちなみに別な情報もあり、図1に相当するコアは存在せず、図2がNavi 33、図3がNavi 32になり、Navi 31は図3に近い構成だがダイあたり3シェーダー・エンジン(7680SP)、トータル1万5360SPになるという話だ。個人的にはこの案はないだろうと思う。
理由は、利用するプロセスに依存する。RDNA 3世代に関してAMDは現時点で利用するプロセスを明確にしていない(“Advanced Node”という言い方をしており、5nmとは言っていない)。マルチチップ構成を取ることは確実で、その場合は3チップになるのも間違いではないと思うのだが、その製造プロセスが以下の2つがあり得る状況である。
GPU N5/Cache N6
GPU N6/Cache N7
仮にGPU N5/キャッシュ N6だとすれば、確かに3シェーダー・エンジンのダイを作るのは不可能ではない。連載605回でも触れたが5120SP構成のNavi 21のダイサイズは519.8mm2と発表されている。
内部の構造を変更してもそれで大きくダイサイズが変わるとは考えられない(SPの数がどうしても支配的だからだ)ことを考えると、仮に6nmに移行させたところでダイサイズはほぼ変わらないだろう。
N7とN6は、N6がEUV(極端紫外線)を利用するという違いはあるが、設計そのものには互換性があるからで、逆に言えばダイサイズは大きくは変わらない(TSMCの説明では18%の縮小)からだ。ということは、N6で5120SPのGPUダイを作ると、430mm2前後。これを7680SPにすると640mm2近くに達する。
巨大なダイを躊躇なく投入するNVIDIAと異なり、マルチチップ化によりダイサイズを減らす方向に舵を切っているAMDとしては、これは許容範囲から外れるだろう。ただこれがN5で製造できるとなると、TSMCの発表ではロジック密度が83%向上するとしていたから、430mm2近くまでダイサイズを縮小できることになる。
ただしN5の製造コストはN7の1.5倍近くまで跳ね上がるという話であり、ダイのコストそのものはあまり下がらない(むしろ上がってる)ことや、ダイあたり7680SPをフルに動かすためにはインフィニティー・キャッシュを相当積まないと、メモリーがボトルネックになりそうというあたりを考えると、やや無理があるのではないかと思う。
図1がNavi 33、図2がNavi 32、図3がNavi 31という構成の場合、2シェーダー・エンジンのダイサイズはTSMC N6の場合430mm2程度、N5に移行できれば300mm2を切る程度に収まる。N6だとしてもハイエンド向けに許容できる(なにしろすでにもっと大きなダイサイズのNavi 21を量産している)値だし、N5ならかなり競争力がありそうだ。
このあたりがはっきりしないのは、すでにTSMCのN5が激しい取り合いになっていることに起因しており、AMDとしても可能ならN5を使いたかったのだろうが、十分にキャパシティーが確保できないとすれば、N5はRyzenを優先にして、Radeonは当面N6という選択肢は十分あり得る。Radeon Instinct MI200がTSMC N6を利用したあたりもこの案の補強材料になるはずだ。
ところでマルチダイ方式を使う場合の難点がレンダー・バックエンドだという話は連載515回でも説明した通りだ。要するにDeferred Rendering(遅延レンダリング)を多用する場合、煩雑にシェーダーとメモリーの間でやり取りが発生するため、メモリーバスがボトルネックになる。
この対策としてRDNAではレンダー・バックエンドと2次キャッシュの間に1次キャッシュを挟んだ格好になっている。加えてRDNA 2では2次キャッシュとメモリーの間に大容量のインフィニティー・キャッシュを挟んだことでさらに効率が上がった格好だ。
今回伝え聞いている構造では、このインフィニティー・キャッシュが2つのダイで共有される格好になっている。おそらくGPUダイとキャッシュダイの間の接続は、Radeon Instinct MI200で採用されたElevated Fanout Bridge 2.5Dを使った格好であり、加えて言えばRadeon Instinct MI200のようにインフィニティー・ファブリックに一度変換して通信するのではなく、どちらかといえばRyzen 7 5800X3Dの3D V-Cacheに近い、直接キャッシュアクセスの信号線がそのまま引っ張り出されるものに近いと思われる。
このキャッシュダイへのアクセスのレイテンシーがオンダイのレイテンシーとそれほど変わらずに実現できれば、マルチダイであってもレンダー・バックエンドはオンダイのインフィニティー・ファブリックにアクセスするのとさして変わらない性能で処理が可能になる。
スケーラビリティーを考えればインフィニティー・ファブリック経由にする方が効果的だろうが、帯域が減ってレイテンシーが増えることを考えれば、ここはスケーラビリティーは無視していると考えるのが妥当だろう。
こちらも正確な出荷時期は不明であるが、今年中の出荷は間違いないとしている。2020年にRadeon RX 6800/6900シリーズが11月頃に投入されたことを考えると、現実問題としては今年第4四半期あたりではないかと予想する。COMPUTEXの頃までにはそのあたり、もう少し情報が出てきそうである。

この連載の記事
-
第770回
PC
キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -
第769回
PC
HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -
第763回
PC
FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -
第762回
PC
測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -
第761回
PC
Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -
第760回
PC
14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ