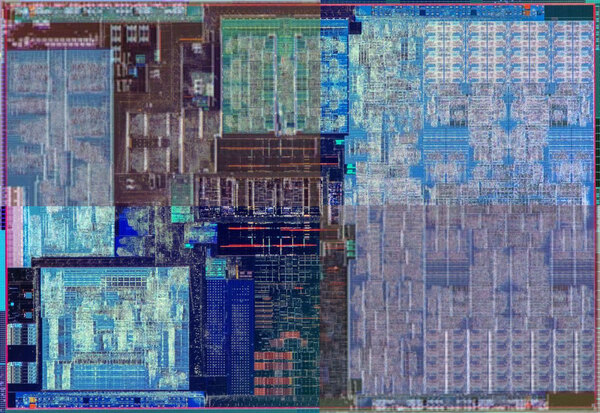今週はAIプロセッサーの話はお休みいただき、Lakefieldを取り上げたい。Lakefieldに関してはジサトライッペイ氏による第一報がすでに上がっているのでご存じの方も多いかと思う。
この連載でも538回でLakefieldのSmall core側であるTremontの内部解説をしているが、今回は発表でわかったこととまだわからないことをまとめて紹介したい。
ダイサイズは82mm2?
通常インテルは製品をリリースするとそのダイ写真なりウェハーイメージなりを紹介してくれるのだが、現時点でLakefieldに関しては公式(News Roomページ)では未公開である。
ただ本国では電話会議の形でプレスブリーフィングがあったらしく、その際に追加でダイ写真が紹介されたというAndreas Schilling氏のツイートがある(同氏はhttps://www.hardwareluxx.de/のエディターの1人)。
Better resolution die shot of the compute die of a #Lakefield processor. pic.twitter.com/U0wv4OjS9g
— Andreas Schilling (@aschilling) June 10, 2020
実はこれ、同じものを入手できないかインテルに掛け合っているのだが今のところ返事がない。なのでいまいち真偽のほどは不明ではある。ただ実は今年5月、imgurにLakefieldのダイ写真が上がっており、これのタイトルが“Intel LKF 82mm2”となっている。
この2枚を試しに重ねた結果が下の画像で、見事に一致しており、おそらくはどちらも正しくLakefieldのものと思われる。
一応このどちらもがLakefieldのダイ写真だと仮定した場合、ダイサイズは82mm2というimgurの数字がわりと信憑性をもつものになる。
仮にこの82mm2が正しいとして内部解析をしてみたい。下の画像はimgurのイメージに、想定されるレイアウトを重ねたものである。
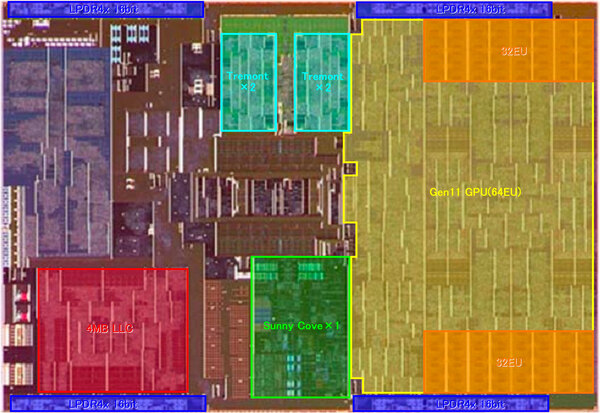
左上のブロックと左下ブロック、どちらがLLCかはかなり悩んだのだが、おそらくダイ左端中央にあるのがPCI ExpressのPHYで、となると左上はPCI ExpressのRoot Complexその他と考えられるため、左下がLLCと思われる
全体の4割近くをGen11 GPUが占め、中央にSunny Cove×1(下側)とTremont×4(上側)が並び、左側にUncoreの4MB LLCその他が集積される、わりと整然とした構成である。この画像からそれぞれのエリアサイズを推定すると、以下の表のようになる。
| Lakefieldのエリアサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Cove | 4.8mm2 | |||||
| Tremont(1コア) | 0.93mm2 | |||||
Sunny Coveのエリアサイズは、Ice Lakeでは6.9mm2と伝えられているが、これはLLCのSliceを混みにした数字で、LLCなしでは4.7mm2程度とされるので、ほぼ今回の推定と一致することになる。
そしてここから今回Tremontコアのエリアサイズが初めてわかったわけだが、1つあたり1mm2未満、4コア合計でも3.7mm2ほどでしかない。
もっとも実際には2つのTremontコアのクラスターの間にインターコネクトが入っており、4コア全体でのエリアサイズで言えば5mm2をやや超えるほどになる。
とはいえ、4コアのTremontと1コアのSunny Coveがほぼ同等のエリアサイズになるわけだ。性能/エリアサイズ比では悪くない結果だと思う。
ちなみにLakefield自身は下の画像のように、Compute DieとBase DieをFoverosで結合し、さらにDRAMをPOP(Package on Package)の形で搭載する構造なので、別にBase Dieが必要になる。こちらのダイサイズは不明だが、おそらく同等もしくはやや大きい程度に抑えられていると思われる。

この連載の記事
-
第864回
PC
なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -
第863回
PC
銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -
第862回
PC
「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -
第861回
PC
INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -
第860回
PC
NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -
第859回
デジタル
組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -
第858回
デジタル
CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ