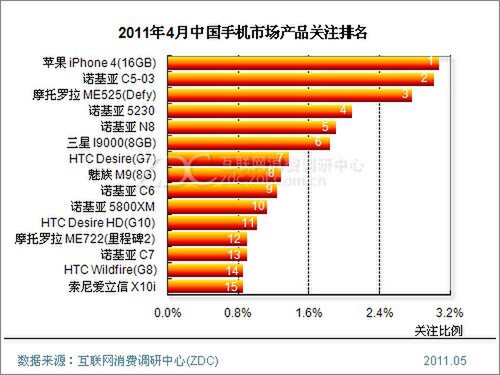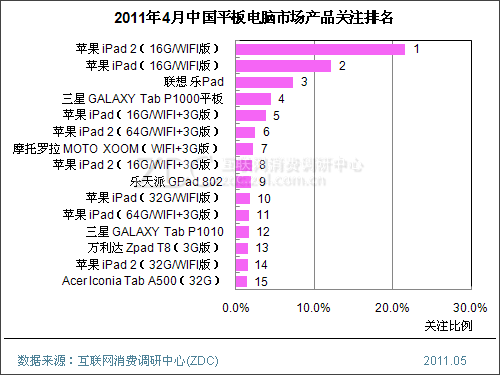若い金持ち中国人は「iPhone」が大好きだ。上海でも北京でも、地下鉄に乗ればiPhone(iPod touch?)ユーザーを多数見かけるし、繁華街にあるお洒落なアップル製品代理店は若い人でごった返す。
四川省の「九寨溝」や、チベット自治区の「ラサ」などの著名な内陸の観光地でも、iPhoneを持ち歩く旅行者をよく見かける。
「ciphone」をはじめとするニセモノが登場するのは、話題性があることの裏づけだ(そういう意味では以前話題を席巻した「威力棒Vii」もまた、Wiiが当時中国で話題だったことを裏付ける証拠ともいえる)。
普段は地下鉄には乗らず、バスなどのより安価な交通手段を使うような(裕福でない)人たちは、金がないので九寨溝にもラサにも行けないわけで、逆に言えば地方都市では今もiPhoneユーザーとは普段出会わない。地方の人々の多くが旅行先とする北京の天安門広場や上海の外灘でのiPhoneユーザーとのエンカウント率は低い。つまり、プチリッチが集まるところに、携えられたiPhoneがある。
Apple製品人気のトリガーはiPhone
若き中国人が好むApple製品が昔からあったわけではない。日本でもiPodやiPhone人気で、Appleが一躍「知る人ぞ知るブランド」から「一般人に認知されたブランド」になったように思うが、振り返るに中国でのトリガーはiPodではなくiPhoneのタイミングだったと思う。
日本におけるiPodの売りのひとつは「日本市場で流通している商品よりも圧倒的に低価格」なことだったが、中国ではさらに激安なノンブランド(山寨機)のmp3プレーヤーがすでに売られていたため、iPodは高価な輸入品であり、貴金属のように独立したガラスケースに入って売られた商品で、認知度の低さから注目を浴びなかった。
中国では「iMac」や「iBook」を含め、Mac本体はごくごく一部のマニアやDTPなどの現場で使われるだけであった。
iPhoneを所有する一番の目的は、多くの人が持っていることから、格差社会の中で「自らが成功者であり、金を持っていること」を示すためである。いくら性能やデザインが良くても話題性、引いては世間一般の認知度がないと多くの中国人には魅力的ではないのだ。
他国でiPhoneに引けをとらないスペック・デザインの「GALAXY S」や「Xperia arc」が話題になろうとも、中国ではステータスの表示こそが大事なのだ。その辺は本連載の過去記事「中国での人のステータスはガジェットで決まる」をご覧いただきたい。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
中国ITの“特殊性”を100回の記事から振り返る -
第99回
トピックス
受注が急増する中国スパコン事情 -
第98回
トピックス
Twitterもどきの「微博」対応に奔走する中国政府 -
第97回
トピックス
検閲厳しく品質がイマイチな中国地図サイト事情 -
第95回
トピックス
中国から学ぶネットリテラシーの上げ方 -
第94回
トピックス
香港電脳街へのいざない -
第93回
トピックス
中国とVPNの切るに切れない関係 -
第92回
トピックス
中国でデスクトップPCを修理する(後編) -
第91回
トピックス
中国でデスクトップPCを修理する(前編) -
第90回
トピックス
中国ネットユーザーが創り出す新しい日本旅行のスタイル - この連載の一覧へ