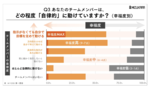ドラフト2.0の誕生、そして標準化
そこで、業を煮やした複数のメーカーが10月にEWC(Enhanced Wireless Consortium)を設立し、TGn SyncやWWiSEとは別の案をTGnに提出。その結果、2006年1月の会議で高い支持を得て、ドラフト1.0の作成に入った。しかし、このドラフト1.0をベースにした投票でも75%の支持を得られなかった。そこで、このドラフトのバージョンを少しずつ上げていく方策を取り、7月に1.02、9月に1.04、11月に1.06、2006年1月に1.10と完成度を高めていった。そして、2007年3月の投票でドラフト2.0が承認されたわけだ。
現在店頭に並んでいる製品は、このドラフト2.0に対応したチップを搭載している。そして、「規格が標準化された際にも、ハードウェアに手を加えることなく、ファームウェアなどのソフトウェアの変更で対応できる」としているメーカーが多い。
そして、2009年9月には、ついに標準化が完了する予定だ。無線LAN製品の相互接続性プログラムを提供するWi-Fiアライアンスによれば、ドラフト2.0と標準化された規格とは、基本的な要件に変更はなく、ドラフト2.0の認証を受けた製品であれば相互接続性は完全に維持するという。
無線LANは比較的新しい技術で、ベンチャーの入り込む余地が多く残されていたことと、マーケットの広がりが大きく期待されていたことから、さまざまなメーカーが規格策定にかかわることになった。船頭多くしてではないが、11nの標準化の遅れには、こういった背景があったことは認めないわけにはいかないだろう。

この連載の記事
-
第9回
ネットワーク
MAC層から改良したIEEE802.11nの仕組み -
第8回
ネットワーク
高速無線LAN「IEEE802.11n」を支える新技術とは? -
第7回
ネットワーク
無線LANの安全を補う認証技術を知ろう -
第6回
ネットワーク
無線LANのセキュリティは暗号化から -
第5回
ネットワーク
有線とは違う、無線独自のアクセス技術とは? -
第4回
ネットワーク
ノイズに対抗する無線LANのスペクトラム拡散とは? -
第3回
ネットワーク
きっちり知りたい無線LANの変調技術の基礎 -
第2回
ネットワーク
数ある無線LAN規格を総ざらいしよう -
ネットワーク
無線LANのすべて<目次> - この連載の一覧へ