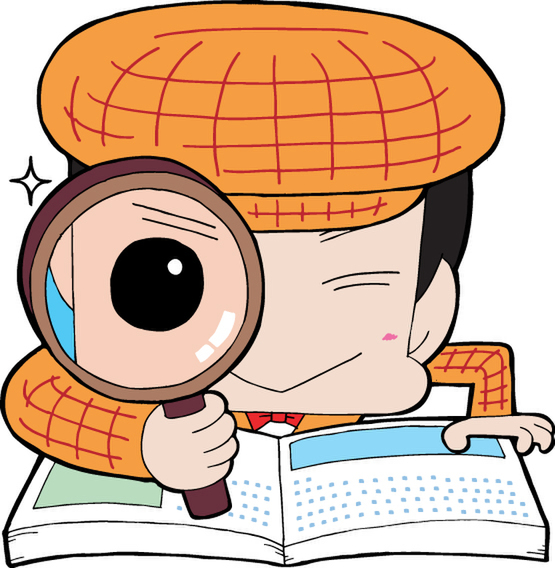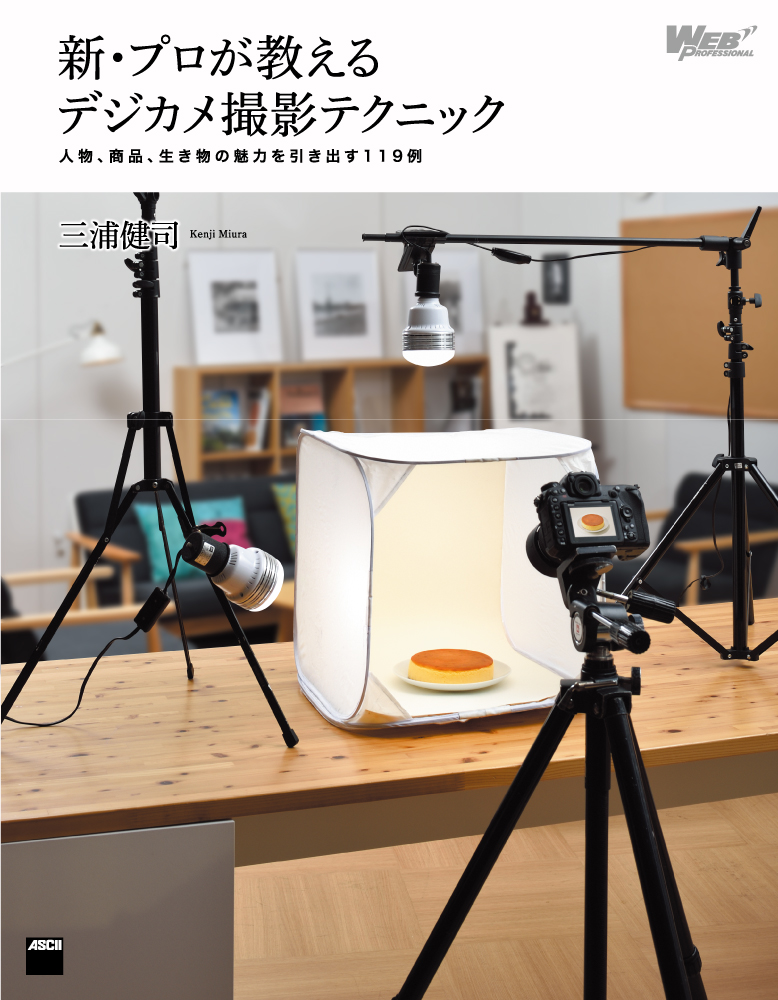紙の辞書の休刊が相次ぐ中、大手出版社が一大決心した。4月22日、朝日新聞社デジタルメディア本部と朝日新聞出版、講談社、小学館とECナビは共同で無料の用語解説サイト「kotobank.jp」を23日にオープンすると発表した。

かつての競合が手を組んだ。写真左から、講談社デジタル事業局の吉羽 治局長、ECナビの宇佐美進典社長、朝日新聞社デジタルメディア本部の大西弘美本部長、朝日新聞出版 開発統括の篠崎 充氏、小学館 ネット・メディア・センターの小室登志和ゼネラルマネージャー
検索エンジン連動型広告で収益化 、目指すは初年度1億円
「ネット上の情報は玉石混交。正式な調査文書や学生のレポートなどで参考にするには支障がないわけではない。我々は信頼性の高い用語解説サイトナンバーワンを目指す」――。朝日新聞社デジタルメディア本部の大西弘美本部長はこう強調する。明言こそしないが、「Wikipedia」に対する危機感が滲み出る。
同社が中心となって立ち上げた「kotobank.jp」は、紙の辞書など、「専門の著者・編集者・版元などによる確かな用語解説」(朝日新聞社)を横断検索できる用語解説サイトだ。23日のオープン時点では「デジタル版日本人名大辞典+Plus」(講談社、収録見出し語は7.4万語)、「デジタル大辞泉」(小学館、同22.5万語)、「知恵蔵2009」(朝日新聞出版、同7600語)など、計44辞書・43万語を揃えた。いずれも、利用は無料。各社とも従来からCD-ROMなどやケータイサイトなどで辞書のデジタル化は進めていたが、すべて無償で公開するのは稀だ。
複数の辞書による解説を1ページにまとめて表示するのが特徴で、関連サイトなどの情報も一緒に表示する。「何か調べたいときにはまず『kotobank.jp』を開く、という具合に、検索エンジン的に使われるようにしたい」(構築を担当したECナビの宇佐美進典社長)。
当面の収益源は、オーバーチュアの検索連動型広告。検索結果ページにキーワードに関連するテキスト広告を表示し、表示された解説記事の版元に収益を分配する“レベニューシェア・モデル”をとる。「各社の分配率は開示できない」(朝日新聞社)が、検索ボリュームのあるキーワード解説を厚く揃えた版元ほど収益を上げられる仕組み。初年度の売り上げ目標は1億円で、「将来的には(バナーなどの)ディスプレイ広告も検討したい」(大西本部長)。
集客手段としては、検索エンジンを重視する。URLを「http://kotobank.jp/word/朝日新聞」のようなキーワードを含むものに、ページタイトルを「朝日新聞とは」といった「とは」を含む形にするなど、SEO対策を意識した施策を打った。また、asahi.comなど、各社のWebサイトからの誘導も順次図っていく予定だ。
初年度は年間3億PV(ページビュー)、3年後は年間35億PVが目標。用語の拡充にも力を入れ、3年後には現在の43万語から200万語まで増やす。1分野1辞書などの制約は設けず、出版社などに広く参加を呼び掛けていく。「オープンなプラットフォームを目指す」(大西本部長)という。ちなみに22日時点でWikipedia日本語版の見出し語は約58万語。「Wikipediaを超える日本語事典サイト」も夢ではない。