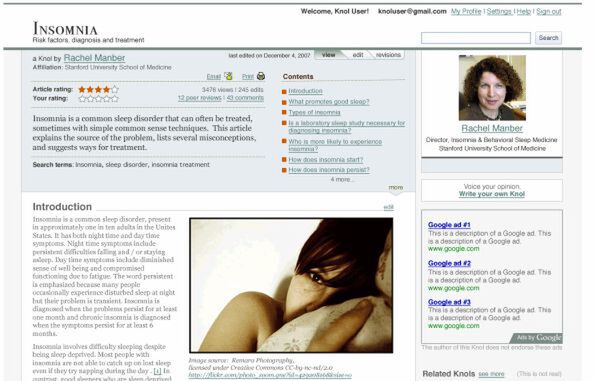今後、実名制をセールスポイントにしたメディアはメジャーになるのか? それとも匿名制がウェブのスタンダードであり続けるのか? これは未来のインターネットに関するホットな論点であり、実際にその動きも着々と進んでいる。
グーグルがテストを始めた「実名制のWikipedia」
米グーグル社は目下、「実名制のWikipedia」とも言えるプロジェクト「knol」(ノール)をテスト中だ。
knolはWikipediaと同じく、歴史や科学、エンターテインメイトなど幅広いジャンルのトピックスに対し、解説を載せるサービスだ。現状では招待制だが、将来的にはグーグルが提供するknol用の編集ツールを使い、誰もが無料で記事(用語の解説)を書けるようになる。ただし、Wikipediaのように複数のユーザーが匿名(やハンドル名)で記事を作る仕組みではなく、個人が実名で記事を投稿する。
グーグルはknolのホスティングをするだけで編集には関与しない。投稿されたコンテンツには別のユーザーがコメントしたり、格付けを行なったりできるが、文責は執筆者自身が負う。また広告の掲載も想定しており、広告収入が解説の執筆者に分配されるシステムになる。
knolは「実名勢力」が集う象徴的存在になる?
ではknolに対するネット界の反響はどうだろう? 上武大学大学院教授の池田信夫氏は、15日付の自身のブログ記事でこう評している(以下、引用部分は原文ママ、リンクに関しては筆者が追加)。
Googleがテストを開始したWikipediaに似たサイト、knolが話題を呼んでいる。以前から書いているように、私は現在のWikipediaは「無法者の楽園」に堕していると思うので、競争が起こるのは歓迎だ。特に注目されるのは、このプロジェクトの責任者であるUdi Manber(技術担当副社長)が、knolのコンテンツが署名入りで書かれる点を強調していることだ
●池田信夫 blog 『匿名ウェブの終焉』
もちろんknolに注目しているのは池田氏だけじゃない。(株)日立コンサルティングの経営コンサルタントである小林啓倫氏は、Wikiscannerなどが明らかにした問題に触れながら、実名制を採用したknolがWikipediaを凌ぐ可能性があると分析する。
Knol が成功するか否か。恐らく「いまさら Wikipedia を超えるコンテンツを生み出せるわけがない」という意見は多いでしょう。しかしたとえ内容が Wikipedia に劣っていたとしても、「実名のオンライン事典」というコンセプトに「乗る」勢力は大きいのではないでしょうか。ご存じの通り、Wikipedia の書き込みをめぐっては様々な問題が起きてきました。政府や政治家などの中にも、Wikipedia の「無責任な」内容を問題視してきた人が多いですから(そういえばこんな問題もありましたね)、実名で責任の所在が明らかな Knol を「反 Wikipedia 勢力」として歓迎する動きが出てくるのではないでしょうか。その意味で、Knol vs. Wikipedia の戦いには Knol 側にアドバンテージがあるのでは、と思います。
●シロクマ日報 『Knol に乗る?』
また、Wikipediaとknolの未来を見れば、匿名と実名のどちらが「有益な情報発信なのか分かるのでは?」という意見(12/16付ブログ記事)さえネット上にはある。両者を二大勢力(実名勢力と匿名勢力)の象徴とみなす見方だ。
匿名と実名のどちらが有益な情報を発信するのか。答えはWikipediaとknolの数年後を見ればわかるのかもしれない。(中略)Googleからこのような理念を持ったサービスが出てくるとは少々意外ではある。(中略)自らコミュニティを主宰するといった思考を全く持っていない珍しい企業だと思っていたのだが、(中略)実名にこだわるknolを分析することで、今後Googleが進もうとしている方向性を垣間見れるのかもしれない。
●Core 『匿名はウェブの質を下げているのか』

この連載の記事
-
第8回
トピックス
ネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか? -
第7回
トピックス
あなたのコメントが相手に火をつけるネットの原理 -
第6回
トピックス
【ブログ文章術】 他人の記事に「反応」することが自分の記事を生む -
第5回
トピックス
「アウトプット」の数だけ「インプット」があるネットの不思議 -
第3回
トピックス
初心者ブロガーが「ブログ青春時代」を卒業するとき -
第2回
トピックス
「ブクマ・ジャーナリズム」はマスコミを屈服させるか?(後編) -
第1回
トピックス
「ブクマ・ジャーナリズム」はマスコミを屈服させるか?(前編) -
トピックス
松岡美樹の“深読みインターネット”〈目次〉 - この連載の一覧へ