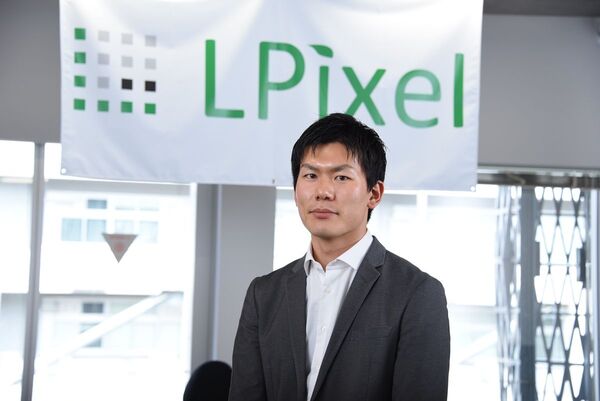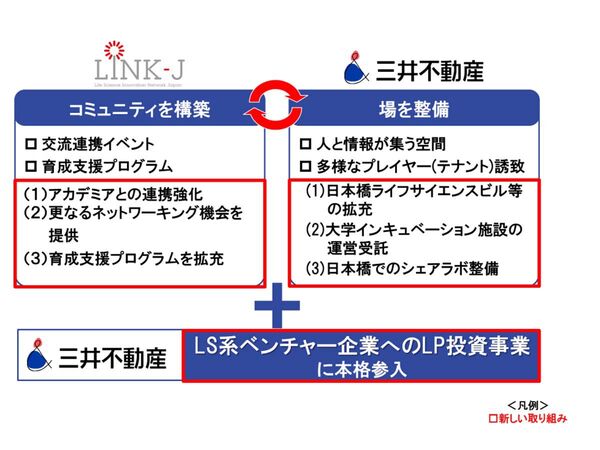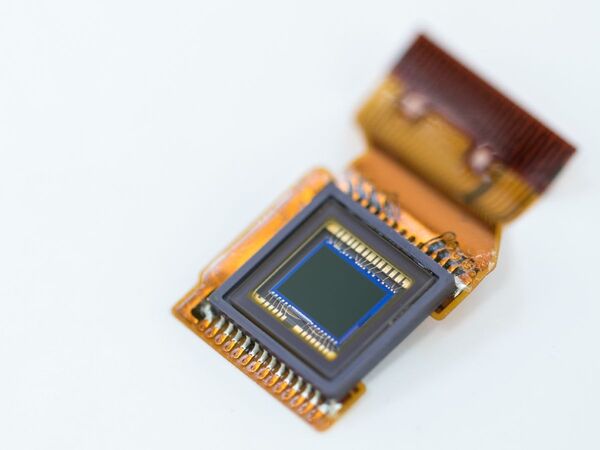Biotechに見るシリコンバレーモデル 米国で生まれる新潮流
米国でのライフサイエンスインキュベーションの仕組みと、「リーン」の関係
国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。京都大学の小栁智義氏によるライフサイエンスにおけるオープンイノベーション最新動向をお届けします。
じつはBiotechもすごいシリコンバレー
筆者は京都大学に赴任して以来、バイオの世界でインキュベーション、アクセラレータープログラムに注目してきた。今回は米国のライフサイエンスにおけるベンチャーエコシステムの状況とともに、そこで行なわれる技術開発手法での違い・共通項についてお届けする。
なお、本題に入る前に少し用語の整理をしたい。
まず「バイオ」と「バイオベンチャー」という言い方だが、英語ではHigh Techと対比していずれも”Biotech”と呼ぶ。「バイオベンチャー」は和製英語なので、海外では通じにくいので注意してほしい。
また、ヘルスケア関係者は「シリコンバレー」より一般的な「ベイエリア」の呼称を使うほうが多い(本記事ではシリコンバレーで統一)。シリコンバレーを含むサンフランシスコ湾岸地域は、Genentech社に代表される遺伝子組み換え技術を中心としたバイオ産業の世界最大のクラスターだ。
その中心はいわゆるシリコンバレーと呼ばれる地域から少し北に位置しており、サンフランシスコ国際空港(SFO)の北のサウスサンフランシスコからスタンフォード大学のあるパロアルト、マウンテンビューあたりまでになっている。Baybioという業界団体もあり、彼らはこの地域を「Biotech Bay」と呼んでいる。
最近ではIT企業を追うように、サンフランシスコのダウンタウン近くにも多くのBiotechスタートアップが出現しており、これら地域差はなくなりつつあるが、言葉としてはまだ健在だ。「男性がITエンジニア、女性がBiotechの研究者」というカップルも多い。
「シリコンバレー」と「Biotech Bay」、ITとBiotechはオモテとウラの関係かもしれない。米国ですでに走っているインキュベーション/アクセラレーションプログラムについて知れば、そのつながりがわかるはずだ。
ライフサイエンス領域でのアクセラレーター、インキュベーター事情
筆者はバイオの世界でインキュベーション、アクセラレータープログラムに注目してきた。ASCII読者のようないわゆるハイテク系の皆さんにとっては「アクセラレーションの手法がバイオまで拡大している」と見えるかもしれないが、バイオ側から見ると、前回筆者が解説した「ライフサイエンスにおけるオープンイノベーション3.0」、つまりは、ここ10数年の間に発展してきた大学などからアーリーステージの技術を取り込みたい大企業が試みている手法の1つだ。
たとえばスタンフォード大学では、2000年から”BioDesgin”プログラムが医学部と工学部の連携によりスタートしており、技術的な「医工連携」だけでないビジネス化に向けた教育プログラムと事業創出プラットフォームを構築している。
医療機器の分野でシリコンバレー同様に突出している中部ミネソタ州でも、州立大学での事業化教育で長い歴史を有しており、同大学のMedical Device Centerでは、2008年より”Innovation Fellows Program”を開始して事業化に力点を置いたプログラムを開始している。
医療機器などの“装置系”でないいわゆる「バイオ(Biotech)」の領域でのアクセラレーター、インキュベーターは、筆者が取材している限りでは、
1)大学内での研究の延長としての事業化支援プログラム
2)企業スポンサーによるアーリーステージのベンチャー企業育成プログラム
3)大学に付属するが、独立採算で事業化前の技術開発を製薬企業と実施する新しいプログラム
の3つのパターンに分けられる。以下、それぞれの具体例を挙げて補足したい。
1)メンタリングが特徴的なスタンフォード大学の「SPARK」
2006年からスタンフォード大学では「SPARK」と呼ばれる新薬創出のためのアクセラレーションプログラムを開始している。
Amazon.co.jpで購入
創始者であるDaria Mochly-Rosenは、2012年にバイオ大手のAmegen社が3億1500万ドルで買収したKAI Pharmaceuticalsの創業者だ(因みに筆者は2002年から2007年までMochly-Rosenラボで研究していた)。自らの創業体験を元に大学で新薬開発をするための、研究者の教育、学内プログラムへの指導を実施しており、その方法論の邦訳も出版されている(「アカデミア創薬の実践ガイド: スタンフォード大学SPARKによるトランスレーショナルリサーチ」2017年、東京大学出版会版)。
SPARKでは事業評価とプロジェクトへの助言・メンタリングを製薬企業OBがボランティアで行なう、いわゆる「プロボノ」であるところが特徴的だ。現役の企業研究員では秘密保持や知的財産についての各種制限があるが、企業OBであれば個人の裁量で参加可能であり、何より彼らの「もっと良い薬を作りたい」という想いに応えるニーズも満たしており、参加者の評判も高い。
ただし、上述の企業OBは各種分野の専門家メンターとして大学の研究プログラムに対して好き勝手に発言するが、そのアドバイスを採用するかどうかは研究者の裁量に任されている。さまざまな角度からの意見を得ることで、技術の一般的な評価を認識し、特定の企業に依存したニッチな技術開発に陥ることを避けている。
日本の大学にも企業OBの方々が多く活躍されているが、「数と多様性」「ボランティアでの参加(プロボノ)」、そして研究者と対等に議論する「フラットな意思決定」において違いが見られる。しかもシリコンバレーではBiotechで成功し、40代や50台前半で既にリタイアした企業OBも多く、現在進行形に近いアドバイスを得ることができることも魅力だ。
日本の大学におけるこのような技術移転でのサポートの質は、コーディネーター個人が有する所属企業、部門での開発経験に大きく依存するが、SPARKではそれを逆手に取って、数多くの多様性のある意見を「安く」「効率よく」「適切に」吸収する仕組みとなっている。
2)数千万円かかる研究室費用をレンタル料だけに抑える大人気プログラムも
企業がスポンサーするパターンもある。
ヘルスケアの総合企業であるJohnson & Johnson社が提供する「J-LAB」(現在サンディエゴ、サウスサンフランシスコなど全米8ヵ所に展開)では、ベンチャー企業に対して実験スペースをベンチ(実験台)1つ分から貸し出しており、多くの共通機器が利用できることから、地元の起業家たちが起業する際の入居第1選択肢となっている。ここではJohnson & Johnsonの研究員との交流もあるので、実際の大企業の開発の動向について知識を得ることもできるし、規制制度など初期のベンチャーが苦手とする部分に対してセミナーなども実施されている。
また、マサチューセッツ州ケンブリッジに拠点を置く「LabCentral」、サンフランシスコのUCSFキャンパス近くに拠点を置く「qb3@953」でも同様にベンチ単位で実験スペースを貸し出しているが、こちらは複数の企業からスポンサーを集めて運営している。通常であれば数千万円かかる研究室の設置費用をレンタル料だけに抑えることができるとあって大人気だ。それぞれ数十社単位で入居企業が新規事業創出にしのぎを削っており、部屋に入るだけで熱気が感じられる。
これらのインキュベーション施設では入居に際して比較的厳しい審査が実施されており、技術の新規性、事業性などの観点で優れた企業のみが選ばれており、入居した時点で投資を得やすい環境を手に入れることができる。厳しい審査によって、中途半端な技術を排除する「早く失敗」する仕組みとも言える。
LabCentral、qb3@953の運営者たちは自らでベンチャーキャピタルも運営している。日々の技術開発に間近で接し、助言することで適切な事業評価が可能となり、成功の確率も上がっている。投資効率を高めるための仕組みとしても価値があることをLabCentrealのCEOであるJohannes Frauhauf博士は強調していた。
3)大学の中に入り込んで“使える“確率を上げる
ニューヨークでは「Tri-I TDI」という組織がロックフェラー大学を始めとする3つの研究機関の成果を武田薬品工業から出向した研究者たちの協力のもと、大学が持っていない「医薬品化学」「非臨床開発」といった分野の開発業務を提供している。
彼らいわく、分野にかかわらず大学の技術は実際に使えるかどうかはやってみないとわからない。であればまず母数を増やすために大学の中に入り込んでとりあえず初期の開発を低コストで実施し、その後に評価をしてみようという考え方だ。
アクセラレーションのスピード感と、使っているツールの違い
ところで、上述のプログラムはスタンフォード大学のSPARKが2年間、LabCentralのようなインキュベーションラボの場合でも滞在期間は12~18ヵ月程度となっている。一般的なアクセラレータープログラムと比べるとこの期間の長さは「そんなに長いの?」と言う印象ではないだろうか。だが、我々ライフサイエンス側から見るとこれでも技術創出の期間としては極めて短く、期間だけでなく昨今のイノベーション創出に関する多くの議論でついていけないところがある。
シリコンバレーで起業を支援するアクセラレーターとしてはY-combinator、500 startups、Plug and playなどが思い浮かぶ。たとえばこれらのプログラムのメニューの1つとしてピッチイベントがある。起業家あるいは起業を考えている人物が事業計画を3~5分間で紹介し、投資家の評価を得るイベントで、一定の起業家育成プログラムの修了にあわせて最終日に“Demo Day”として実施されるパターンや、大型のテック系の展示会の目玉として企画されることが多い。
バイオの世界では長い間、この「短時間のピッチ」での事業評価への疑問の声が多くあった。じっくり時間をかけてその技術の背景から特許の状況、市場性まで調べあげることで適切な評価が下せるという考え方だ。ほかの事業分野と比べると単純にコンサバな意見としか捉えられないかもしれないが、事業形態に起因する課題も存在している。
昨今のスタートアップ界隈で使われているツール、「リーンスタートアップ」「ビジネスモデルキャンバス」といった手法が、ヘルスケア、特にバイオの世界では使いにくいと言われている。
ヘルスケア業界は医療ニーズに応えるためにできており、根本的に規制制度に縛られているので、上述のツールでいうところのValue Propositionは「○○疾患患者の□年後の生存率を改善する」、Customerについては「治療法選択に決定権のある医師」にするか、「その恩恵を受ける患者」とするかで議論をする程度で終わってしまうことが多かった。
Amazon.co.jpで購入
アレックス・オスターワルダーとイヴ・ビニュールの「ビジネスモデル・ジェネレーション(翔泳社刊)」では、大手製薬メーカーグラクソ・スミスクラインのパテント・プール戦略と未来の製薬ビジネスモデルについて言及されているが、実際の創薬開発の現場での発想法や分析に利用されているケースは聞かない。リーンスタートアップに至っては、プロトタイプ試験そのものが創薬開発に於いてはゴールまで行き着くことであり、1500億円を超える開発を繰り返すことはありえない、と言われている。
ライフサイエンス分野には多くの新しいツールはなじまず、他分野の投資家からの評価も得ることはできないと言われている。だが、果たしてその話を鵜呑みにしてよいのだろうか?
ヘルスケア業界も「リーン」への一歩を踏み出し始めている
前回も書いたように過度に肥大した医療費の抑制は大きな課題であり、その中ではICTの活用、予防医療とともに、“Precision Medicine (精密な医療)”と呼ばれる新たな医療が注目されている。
“Precision Medicine”は従来の“平均的な患者”のためにデザインされた医療ではなく、それぞれの患者個人により適した医療を提供するという、医療現場や患者のメリットを考えた医療戦略のことを表している。
従来の臨床検査情報に加えて、ゲノム情報解析や画像診断技術の発展、健康状態のモニタリングにより患者個々人の病態にあわせた投薬が行なわれる、そして必要のない治療を削ることで医療費が削減できる。そんな未来の医療が医療経済の面からでも求められている。
これは診断だけでなく、新薬や医療機器開発の現場でも同様だ。
本稿の前半で取り上げた3つのインキュベーション/アクセラレーションプログラムのパターンでは、いずれも「アーリーステージの技術を安価に次のステップに上げる」という目的は共通している。安く、しかも研究者の近くで開発を実施することで初期のアイデアに接する機会も増え、プログラムも増やすことができるため、多くの失敗も許容できる。そして小さくとも成功を勝ち取った、より対象患者数が絞られたニッチな医薬品や治療法の確立が期待される。これこそ「リーン」な開発ではないだろうか?
これらの調査はいずれも筆者が京都で、日本でのライフサイエンスベンチャーエコシステムを構築するために収集している情報であり、各種連携プログラムも企画している。2017年2月15日にはSPARKプログラムと連携しての”The 1st KYOTO-SPARK Symposium—Construction of a Drug Discovery Ecosystem between Academia-Pharma”を開催した。
ライフサイエンス業界も「リーン」な技術開発が必要となっている。各業界の方法論は適切な見方をすることによって共通性を有していることがわかる。そして今後10年でライフサイエンス業界は大きく変わる。前回の繰り返しになるが、ぜひこの機会にもう一歩ライフサイエンスの世界に興味を持ってほしい。
アスキーエキスパート筆者紹介─小栁智義(こやなぎともよし)

博士(理学) 京都大学大学院医学研究科「医学領域」産学連携推進機構 特定准教授。より健康で豊かな社会の実現を目指し、大学発ベンチャーを通じたライフサイエンス分野の基礎技術の実用化、商業化に取り組んでいる。スタンフォード大学医学部での博士研究員時代にベンチャー起業を通じた研究成果の事業化に接し、バイオビジネスでのキャリアを選択。帰国後は多国籍企業での営業/マーケティング、創薬、再生医療ベンチャーでの事業開発職を歴任。現在は大学の産学連携業務に従事し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構「創薬技術シーズの実用化に関するエコシステム構築のための調査研究事業」分担研究代表者も務める。経済産業省プログラム「始動Next Innovator」第1期生。大阪大学大学院卒。