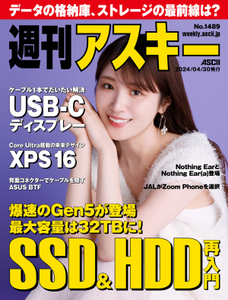ハイレゾはなぜ生まれたのか
すごく単純に言って「音楽を聴く時に“悪い音”よりも“良い音”のほうが幸せでしょう」ということですね。できうる限り生の音に近付いて、いい音で聞きたいという欲求は、人類共通というか、人類の普遍的な夢なんじゃないでしょうか。
Hi-Fiという言葉があります。つまり“High Fidelity”、“高忠実度”という意味です。では何に“忠実”なのか。それは“生の音”です。
例えばビクターはすでに昭和30年代に、生演奏とスピーカーをすり替える実験をやっています。ステージにスピーカーをドーンと置いておいて、そこで演奏家が弾いている。
途中で演奏が止まってスピーカーの音に切り替わるんですが、聴いている人は弾いているそぶりもあり、どこで生演奏からスピーカー演奏に変わったのか、結構分からなかったそうですね。
何でそんな実験をやったのかというと、それはスピーカーから流れてくる音がどれくらい生の音に近づいているかを知りたいという、本能的な願望があるからです。エジソン以来、パッケージ(=レコード)が出てきて、レコードを買えば誰でもスピーカーで音楽を楽しめようになりました。
でも“音楽をその場で楽しむ”という本来の姿とは結構違っているし、“やっぱり生は生だぜ”と感じる人が多かったんでしょうね。だから生の音に「いかに近づくか」という願望が生まれてきたわけです。
ハイレゾは“そんな願望”の一つの帰結なんだろうと思います。
現実の音は柔らかいのに芯がある
アナログのLPレコードが世に出たのは1950年ごろ、その後CDが1982年に登場してデジタル再生の時代が始まりました。ハイレゾが盛んに聴かれるようになったのは一昨年ごろからですかね。そう考えると、だいたい30年の周期でメディアが大きく入れ替わっていることになります。
1980年代の初め、レコードがCDになった瞬間はみんなが感動したものです。レコードは帯域が狭いし、ノイズがパチパチと入るし、針音も大きい。それから左右のセパレーションが良くないとか、低音が薄いとか、色んな問題があった。CDになってそんな問題がすっかり解決したんですね。
例えば、ノイズが非常に少なくなり、セパレーションがすごく取れるとか、低音がしっかり出るとか、音が揺れないとかですね。ただ、これで“生の音”に近づけたかといえば、そうでもなかったなぁと。
生の音はひとことで言うと、しなやかで剛毅なんですよ。オーケストラの生演奏を聴いていると、ソフトで柔らかいな、なんて思うけど、芯はすごくしっかりしています。そんな観点でよく聴いてみると、CDから出る音はリジットに走り、しなやかさが失われている。だから「音が硬いな」とか「生の音に比べてほぐれないな」という感想を持ってしまいがちです。CDの登場で、アナログ時代のレコードとは違うところが気になるようになったわけです。

この連載の記事
-
第10回
AV
麻倉怜士推薦、絶対に失敗しないハイレゾ機器はこれだ -
第9回
AV
ネットワークプレーヤーの利便性を上げるHDD内蔵機 -
第8回
AV
ハイレゾを始めるならUSB DAC? それともネットワーク? -
第7回
AV
PCオーディオという言葉の誕生からハードの変遷を知る -
第6回
AV
ハイレゾ版の松田聖子やカラヤンで、青春時代がよみがえる -
第5回
AV
発展途上のフォーマット、DSDの魅力を知る -
第4回
AV
ヘッドフォンとハイレゾ、手軽な圧縮から本格的な音へ -
第3回
AV
ハイレゾはなぜ音がいいのか? 聴こえない心地よさの秘密 -
第2回
AV
ハイレゾとニセレゾ、規格か宣伝文句なのかという議論 -
AV
麻倉怜士のハイレゾ入門講座 - この連載の一覧へ