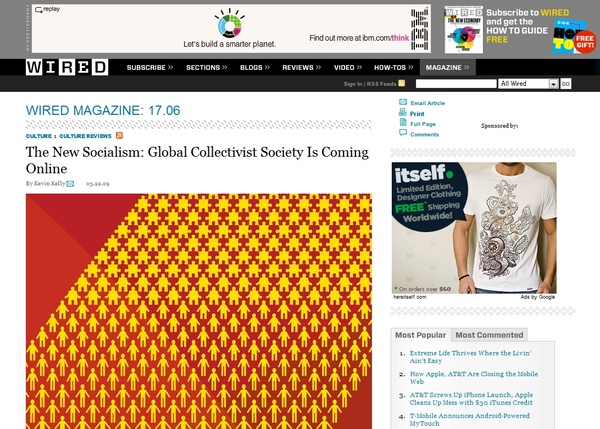よみがえるマルクス?
このごろ本屋に行くと、マルクスの本が目立つ。「大恐慌で資本主義が崩壊する」という彼の予言が実現したようにみえるからだろう。WIREDも"The New Socialism"という特集記事を書いている。しかしそれはマルクスが考えたような資本主義を倒して実現するシステムではなく、資本主義のできなかったことを可能にする補完的なシステムだ。
社会主義というと「国家による経済管理」というイメージが強いが、ここで筆者(ケヴィン・ケリー)が描いているのは「国家なき社会的生産システム」という意味でのソーシャリズムだ(マルクスが目標としていたのも「国家の死滅」だった)。私もかつてWIREDの日本版に「ドット・コミュニズム」という連載を書いたことがあるが、そういうシステムが私の予想を超えて広がっているようだ。
誰でも知っているのは、オープンソース・ソフトウェア(OSS)だろう。その元祖はリチャード・ストールマンの創立したGNUプロジェクトで、この流れの中からLinuxもApacheもMySQLも生まれた。OSSの開発方式は昔の社会主義に似ていて、GNUについてはストールマンの意向が絶対だ。Linuxもリーヌス・トルヴァルスが「啓蒙的専制君主」として方針を決める。Mozillaのコードを書いているのは少数のコア・メンバーだし、MySQLはオラクルより厳格な階層構造で開発されているという。
他方、コンテンツを共有するサイトには階層秩序はあまりない。Wikipediaの管理はよくも悪くもいい加減なので、いつも紛争が起こっている。ブログはもちろん、Digg、Twitter、StumbleUponなどの内容もアナーキーだ。しかしこうしたソーシャル・メディアは既存のマスメディアよりはるかに速く大量の情報を世界に伝える。YouTubeは月間60億回以上のビデオが再生され、Flickrには30億枚の写真がある。イランの状況を知るのに、もっとも便利なのはTwitterだ。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ