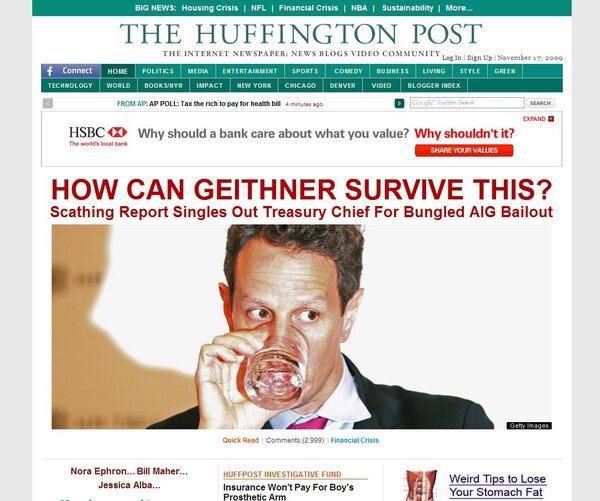政府は滅びゆく新聞社を救済すべきか
アメリカの有名なウェブサイト「Huffington Post」の名前は、もちろんWashington Postのもじりだが、Compete.comの統計によると、今年10月のユニーク・ビジター数で、Huffpostが本家を抜いた。従来型の新聞をそのままウェブに載せたサイトより、ウェブ生まれのメディアのほうが大きなメディアになりつつあるのだ。Huffpostの読者がこの1年で57%増えたのに対して、本家の読者は22%減った。
アメリカでは、経営危機に瀕している新聞業界を政府が税制優遇措置などで救う「新聞再生法案」が議会に出され、論議を呼んでいる。たしかに紙の新聞の寿命は、あと10年ぐらいしかないだろうが、ウェブ上のニュースサイトの比重は大きい。特に日本では、ウェブ上の情報の大部分はブログや電子メールなどの個人的な情報で、資料的な価値があるものはほとんどなく、広告媒体としてもコンテンツの質が保証できないため、有力なナショナルスポンサーがつかない。新聞や雑誌などが質の高い情報を出せば競争できる可能性はある。
ただし広告だけで採算をとるのはむずかしい。まもなくインターネット広告は新聞を抜き、あと数年でテレビを抜くと予想されるが、客単価はテレビの1割ぐらいだといわれる。これはテレビがこれまで電波を独占してきたことによる超過利潤があるのに対して、インターネットの広告単価が競争的に決まるためで、長期的には他のメディアもインターネットの単価に近づいてゆくだろう。逆にインターネット広告の単価は、質の高い情報が増えてメディアとしての価値が上がれば、今より上がることが期待できる。
在来型の広告の売り上げは約5兆円、GDPの「1%産業」といわれる成熟産業なので、あまり大きな成長は期待できない。しかしセールスマンなどによる営業を入れると、広い意味での営業費用は約20兆円ぐらいの市場規模があると推定される。日本ではこうした「ドブ板営業」が主流を占めてきたが、最近は人件費が上がって採算がとりにくくなった。今後はウェブによる低コストのマーケティングが伸びる可能性は高い。イベントなどの収入を組み合わせれば、TechCrunchのように黒字を出すことも可能だ。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ