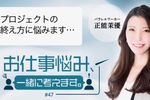仮想通貨(暗号資産)の価値を、日本円などの法定通貨と連動させるステーブルコインを規制する制度ができた。
2022年6月3日の参院本会議で、資金決済法の改正案が可決、成立した。
ステーブルコインをめぐる法整備は、日本が他の国々に先行する形になった。
いまのところ、日本国内でステーブルコインはほとんど利用されていないが、法整備は利用拡大のきっかけになるのだろうか。
仮想通貨業界側からは、規制の方向性をめぐって不満も出ている。
ステーブルコイン規制の中身を詳しく見てみたい。
「デジタルマネー類似型」のステーブルコイン
法改正にあたって、金融庁はステーブルコインを大きく2つに分類した。
1つ目は、デジタルマネーに類似するステーブルコインだ。
この「デジタルマネー類似型」は、その価値が法定通貨と連動する。円と連動する場合、1コインが1円で、払い戻しの際にも1コインにつき1円が戻ってくることになっている。
デジタルマネー類似型ステーブルコインの発行者は、発行したコインの価値に相当する法定通貨を準備しておく必要がある。
そのコインを保有する人たちが一斉に「日本円を払い戻してくれ」と請求したとしても、それに対応できるだけの資産が求められることになる。
Suicaなどの交通系電子マネーや、PayPayなどのQRコード決済サービスと類似する点が多いため「デジタルマネー類似型」と分類したのだろう。
現在、米ドルやユーロなどに連動する「デジタルマネー類似型ステーブルコイン」が国際的に流通している。
発行したコインの価値に対して十分な資産を持っているかどうか疑わしい発行者も存在する。この点が、現行のステーブルコインの課題になっている。
ステーブルコインで最大のシェアを占めるとされるテザーも、準備資産が十分かどうかについては、現在も厳しい視線が投げかけられている。
これに対して「暗号資産型」に分類されるビットコインなどの仮想通貨は、アルゴリズムで価値の安定を図る。
ビットコインなどの場合は、価格が爆上げする期待ができる反面、大きく値下がりするリスクもある。
アルゴリズムで価値の維持を図るステーブルコインとしては、米ドルと連動するテラなどがある。
テラのアルゴリズムは1単位1ドルを維持できるものとされたが、実際にはアルゴリズムが正常に機能しなかった。5月には、1単位1ドルを維持できず、その価値は暴落した。
メガバンクステーブルコインが登場?

この連載の記事
- 第281回 SNS「なりすまし広告」詐欺被害拡大。実効性ある法整備はできるか
- 第280回 データセンター建設ラッシュ 日本への投資が熱を帯びる3つの要因
- 第279回 ラピダスがシリコンバレー拠点を作ったワケ
- 第278回 日本円のデジタル化が近づいてきた
- 第277回 仮想通貨取引所の破たんで起きたこと。「史上最大」の詐欺、FTX創業者に禁錮25年
- 第276回 時価1.5兆円の掲示板サイト「Reddit」のビジネスモデル
- 第275回 仮想通貨が通貨危機の引き金に!?
- 第274回 公取委、アマゾンとグーグルに睨み 巨大IT規制の動き、日米欧で相次ぐ
- 第273回 ビットコインが急騰した3つの理由
- 第272回 サイバー犯罪集団LockBit、手口はビジネスさながら “ランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)”で企業を脅迫
- この連載の一覧へ