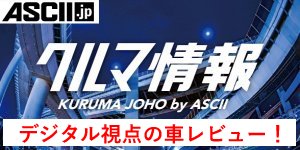ホンダ・青山ビル建築ツアー参加レポート
建て替え前に貴重な内部が見られます
ホンダは、東京・青山にある本社の青山ビルの建て替えを予定しています。青山ビルは、1985年に2代目の本社ビルとして建設され、社会との調和・コミュニケーションを図る場として、1階にはホンダウエルカムプラザ青山を設置。本社としてビジネスの場としてだけでなく、ホンダ・ファンの集う場所として、これまで40年の歴史を築き上げてきました。
そんな青山ビルですが、将来にわたって人々や社会から「存在を期待される企業」であることを目指し、「イノベーションを生み出す変革と発信の拠点」となる本社機能実現のために、ビルの建て替えを実施することになったというのです。
具体的な日程としては、3月末にホンダウエルカムプラザ青山を休館とし、青山ビル内での業務も5月に終了。ビルを解体したあと、2030年を目標に新たな本社となる青山ビルが復活する予定です。
そのクロージングイベントとして、ホンダは「ホンダ青山ビル建築ツアー」を2月23日に一般向けに開催します。ツアーのガイドは、建築の歴史などを研究する大阪公立大学教授の倉方俊輔氏。1985年に建てられた青山ビルに込められた創業者の想いとなるホンダ・フィロソフィーを伝えるのが目的です。
申し込みは2月9日まで行なわれ、一般の方75名の参加が予定されています。そんなイベント開催に先立ち、2月上旬に、メディア向けの先行ツアーが実施され、参加したのでレポートします。
多くの人に門戸を開きたい
防災も兼ねて大量の水が地下にある
ツアーのスタートは、なんと青山ビルの最奥となる地下3階。そこには、コンクリート打ちっぱなしの地下室の高い天井ギリギリまでそびえる2つの巨大な木製の樽がありました。カナダ産のヒバ材を使った大きな樽は、ひとつで最大35トンもの水を溜めます。水道水をいったん、この樽に溜めてカルキ臭を抜き、おいしい水にするのが狙いです。
なぜ、おいしい水が必要かと言えば、ホンダの創業者である本田宗一郎氏の「このビルは誰でも気楽に立ち寄れる場所にしたい。ホンダ・カブに乗った出前の兄ちゃんもおいしい水が飲めるように」という希望があったというのです。実際に、青山ビルの1階のウエルカムプラザには「宗一郎の水」とし無料で提供されています。庶民派と言われていた、本田宗一郎氏ならではの希望と言えます。
ガイドの倉方氏が言うには、青山ビルの作り方は非常にユニークだそうです。ホンダ級の世界的な大企業であれば、著名な建築家やデベロッパーに丸投げしてしまうことも珍しくはありません。しかし、青山ビルは建築家の名前が前面に出ていません。まったく建築家が関わっていないわけではなく、施工は建築家・椎名政夫氏の統括の下、大手建築事務所とハザマ組が組んで進められたそうです。
とはいえ、椎名氏は、個人の邸宅を創るのが得意。また、ホンダ側にもチームが用意され、さらに創業者である本田宗一郎氏と、それを経営面で支えた藤沢武夫氏も、相当に細かく口出ししたそうです。こうした体制が、宗一郎氏の想いを色濃く反映した理由になっているのでしょう。
巨大な樽に続いて赴いたのが、殺風景な地下2階の倉庫。そこにはびっしりと水や食料、災害時に必要な備品が積まれていました。青山ビルに勤めるホンダ社員約1600人が3日間暮らすだけでなく、必要であれば周囲の住民のために提供できるだけの物資を用意しているとか。万一の災害時には、これらの食糧などを使って、青山ビルの前の道路からセットバックしてできた広場で、炊き出しをすることも考えられているそうです。
また、青山ビルは、万一の災害への対応を、強く考えられているのも特徴です。青山ビル程度の高層ビルの場合、2つの非常階段が義務づけられるのに対し、青山ビルはビルの四隅の3つに非常階段を設置しています。さらに、万一、窓ガラスが割れても、ガラスの破片が落下しないように、各階にバルコニーが設置されています。これなら地震などでガラスが割れても、青山ビルの前の歩行者に被害が及ぶことはありません。
ガイドである倉方氏は「こうした災害を想定した建築は、安全を重視するモビリティを創る会社ならではの点と言えます」と説明します。食料などの備蓄は、今では珍しくありませんが、青山ビルができた1985年当時は相当に画期的でした。また、1985年当時は全面ガラス張りのビルが流行していたところ、それに反してバルコニー付きとしました。オフィスビルとしてバルコニーは不要ですし、スペース効率的にも無駄です。しかし、ホンダは安全性を重視して、それらを設置しているのです。
シビックみたいなビルを作りたい
燃費の良さのように省エネが特徴のビル
さらに倉方氏が言うには「青山ビルはシビックみたいな建築を」と作られたとか。設計グループが、どんなビルがホンダらしいかを検討した結論が「シビックみたい」であったというのです。
ビルの設計時の80年代前半は3代目「シビック(通称・ワンダーシビック)」の時代です。その「シビック」の特徴は、MM思想(マンマキシマム、メカミニマム:人の空間は最大に、機械は最小に)を採用したところ。そして、青山ビルには、その思想を建築に取り入れたというのです。
それを聞いてから建屋を見ると、確かに青山ビルはエレベーターホールなどメカニカルなスペースがまとめられて小さくなっており、人が使うオフィス・スペースは大きくとられています。オフィス空間では、柱もスペース部分に出ないように配慮されていますし、照明や空調も天井内に収められていました。また、エレベーターホールの照明は絞られ、薄暗くなっています。これは使わない部分は抑えて省エネにするのが狙い。「シビック」は燃費の良さ=省エネも特徴であり、まさに「シビック」のような建物となっているのです。
そして、ツアーの最高潮に盛り上がったのが最上階にある応接室です。本社らしく、各界の貴賓を接遇するスペースです。1986年に英国のチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日したときには、パレード直前の休憩所として活用されたそうです。
見るからに質の良さそうなソファやじゅうたんが使われていましたが、これ見よがしな豪華な装飾はありません。モダンでありながらも、落ち着いており、品の良さを感じさせてくれます。権威的なものを嫌った本田宗一郎氏と、趣味人として知られた藤沢武夫氏の2人の個性を反映する部屋のように見えます。
この応接室において倉方氏は、ホンダ本社ビルの歴史を振り返ります。ホンダの東京本社として1960年に最初に作られたのが東京の八重洲でした。その後、70年代に入って本社移転が計画され、一時的に原宿に本社機能を移転。倉方氏いわく「原宿は当時も今も流行の街であり、そうした流行を感じられる場所として青山が選ばれたのでしょう」と説明します。丸の内などの官庁街に行かずに、青山を選んだのも庶民派であり、流行を大切にするホンダらしい選択です。
2030年の新社屋ビルがどうなるのか
期待が持てそう
また、「1階のウエルカムプラザから2階の本社受付に向かう階段は、まるで結婚式場のステージのよう。このワクワクする感覚も特徴でしょう。大衆性と知性が調和したデザインです。この青山ビルは、ホンダが作った建築。これができたホンダは、ただの大企業じゃありません」と倉方氏。そして最後に「次のビルは、どうなるかわかりませんが、この青山ビルを上まわる物ができることを期待します」とツアーを締めくくりました。
庶民的であり、モビリティのように建築する。創業者、本田宗一郎氏の思想がしっかりと反映した建築、それがホンダ青山ビルであることが、非常に理解できた1日でした。