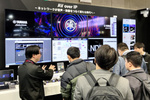1985年をピークに売上が下がる
原因はAT互換機の出現
以上のように、IBMはラインナップを増やしていったわけだが、売上はどうだったかというと、1981~1987年の売上推移は下のようになっている。
| 機種/年度別売上台数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM-PC | PC/XT | PC/AT | 合計 | |||
| 1981年 | 2万台 | 2万台 | ||||
| 1982年 | 14万台 | 14万台 | ||||
| 1983年 | 40万台 | 10万台 | 50万台 | |||
| 1984年 | 87万台 | 28万台 | 6万台 | 121万台 | ||
| 1985年 | 48万台 | 56万台 | 36万台 | 140万台 | ||
| 1986年 | 28万台 | 55万台 | 35万台 | 118万台 | ||
| 1987年 | 6万台 | 22万台 | 26万台 | 54万台 | ||
| 合計 | 225万台 | 171万台 | 103万台 | 499万台 | ||
データの出典は“Creating Strategic Leverage” by Milind M. Lele
これにPC Jr.やConvertible PCを加えれば、軽く500万台を突破しているわけで、仮に平均小売価格を全部まとめて3000ドルと仮定しても、7年間で150億ドルもの売上になっている。PC Jr.の失敗ぐらいでは揺るがなかったのはこのためである。
もっとも売上のピークは1985年であり、その後徐々に売上は落ちているのもわかる。理由は簡単で、PCクローンの出現である。
連載488回でも触れたが、IBM-PCの開発にあたってはオープンスタンダード戦略がとられた。どのくらいオープンだったかというと、ハードウェアの全回路図とBIOSのソースコードが、Technical Reference Manualとして完全公開されているほどだった。
IBM-PC/ATの場合、“IBM PC AT 5170 Technical Reference 1502494”の表紙が青ということでBlue Bookという名前で知られているが、これをご覧いただくとわかるが、必要な情報がすべて網羅されて掲載されている。
ただこのBIOSをそのままコピーすると著作権違反になる(実際、これをやってバレて訴えられた会社が複数ある)ため、これが他社の参入を防ぐ障壁になっていたわけだが、まずCOMPAQが自社向けに互換BIOSを開発して製品を出荷、次いでPhoenixが外販用の互換BIOSの販売を始めた結果、1985年以降もPC市場は急速に拡大していくものの、そこに占めるIBMの売上が次第に落ちていくのはある意味仕方がない。
間が悪いことは重なるもので、こうした新しい競合に対応していかなければならないという時期に、ESDはDon Estridge氏を失った。ここからESDは方向性がずれ始める(次回に続く)。

この連載の記事
-
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -
第853回
PC
7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -
第852回
PC
Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -
第851回
PC
Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -
第850回
デジタル
Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ -
第849回
PC
d-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現 -
第848回
PC
消えたTofinoの残響 Intel IPU E2200がつなぐイーサネットの未来 -
第847回
PC
国産プロセッサーのPEZY-SC4sが消費電力わずか212Wで高効率99.2%を記録! 次世代省電力チップの決定版に王手 - この連載の一覧へ