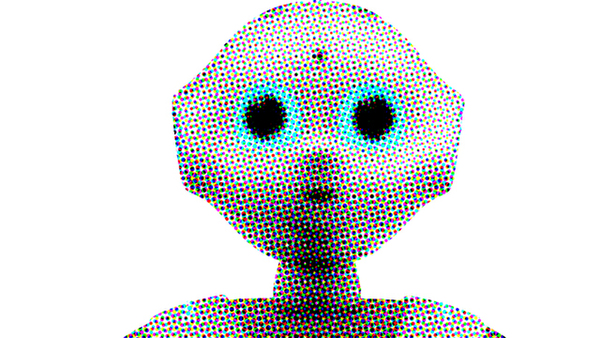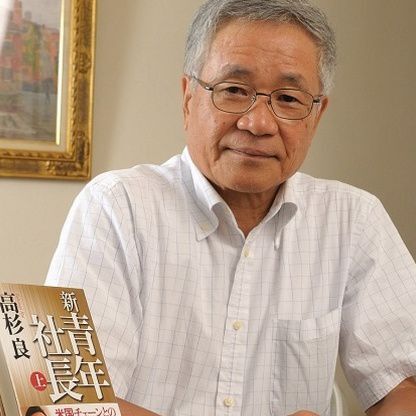レオナルド・ディカプリオ、渡辺謙が主演の映画『インセプション』は、他人にアイデアを植え付ける(inception:動機付け)話だ。誰かに強制されるのではなく、自分から進んで実行する。その動機を夢の中で植え付ける、という設定の作品で、単なるSF映画としても見られるし、WebデザインやWebマーケティングで駆使される手法のように、北風を吹かすのではなく、太陽で照らすことで消費者の行動を制御するような表現であふれかえる現代社会の、ある種の風刺とも理解できる。
出版社のWeb部門に籍があると、同業他社の人との情報交換の場でも、どうしても話題は電子書籍になる。「A社がB社に作家の○○さんの作品を提供するように持ちかけたらしい」とか、「部長が妙にやる気なんだけど、とても儲かるとは思えない」とか、困惑する業界、混乱する現場の風景は、かつてのレコード業界もそうだったのかな、といった想像にもつながり、複雑な心境だ。
そんなとき、弊社が9月10日に刊行する『ルポ電子書籍大国アメリカ』(大原ケイ著、743円)という新書の存在を、TwitterのまつもとあつしさんのRTで思い出し、新書編集部に無理をいって刊行前の見本を入手、読んでみた。自社本で恐縮だが、著者である大原ケイ氏の立ち位置はニューヨーク在住の出版エージェントということで、出版社とはやや異なる視線で電子出版を見ており、IT系ジャーナリストともブロガーとも別の角度から電子書籍を眺めている、という印象だ。

|
|---|
| ルポ 電子書籍大国アメリカ |
成果主義にしても、金融サービスの自由化にしても、Web 2.0にしても、日本人は何かの問題に直面すると、その原因を「アメリカでは当たり前に受け入れられているのに、日本では正確に受け入れられていない概念や制度」に求め、社会を変えるほどの大ブームを起こし、あっという間に熱が冷めてしまうことが多い。個人的には電子書籍についてもそんな臭いを感じていて、「ロマンスとSFこそ、電子書籍が伸びてマスマーケットが苦戦しているジャンル」といった本書の記述を読むと、「アメリカではすべてのジャンルで電子書籍が伸びていて、紙はなくなる勢い」といった話は、電子書籍を普及させたい側によるインセプションだとわかる。
グーグル(新興勢力)対米出版業界(旧勢力)という構図で語られたグーグルの「Google ブックス」については、テクノロジーやマーケティングではなく、人間関係として解説しているのが新鮮だった。訴える側の全米出版社協会理事長と訴えられる側のグーグルのプロジェクトリーダーは大手出版社のランダムハウスで上司と部下の関係だったそうで、対立して拗れた、というよりは旧知の仲同士がお互いの立場で落とし所を探るために司法の場に持ち込んだ、という見方を示している。出版エージェントやアドバンスなど、米国の出版事情についてもきちんと説明していて、米国の事情を知らず、焦って電子書籍戦略を組み立てているようでは、何が現実で、どの青写真が誰の利害に基づいて描かれているのか、わからなくなる、と感じた。
さて、「電子書籍」に踊らされる出版業界の面々に冷静になってもらうにはどうしたらいいだろうか。部長の枕元にそっと『ルポ電子書籍大国アメリカ』を置いておけば、電子書籍への過大な期待を諦めて、現実に見醒めてくれるだろうか。