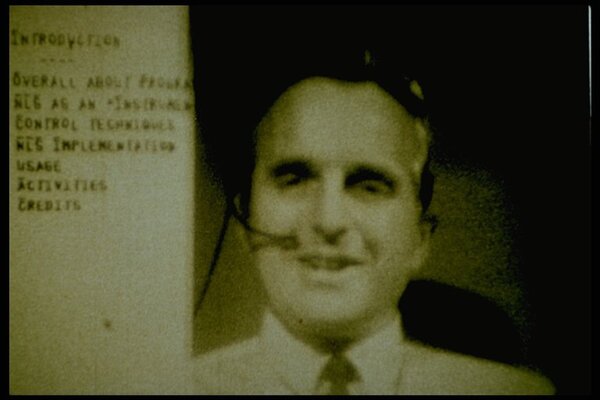ダグラス・エンゲルバート
私のヒーローは、ダグラス・エンゲルバートである。彼が存在しなかったら、自分自身も存在しなかっただろうと思うほど、自分にとってかけがえのないヒーローなのである。
伝説的デモンストレーション
1968年、米国サンフランシスコで開催された国際会議FJCCで、彼は「NLS」という画期的なオフィス情報システムのデモを披露した。現在我々が日常的に利用しているハイパーテキストやアウトラインプロセッサー、マルチウィンドウ、グループウェア、そしてマウスなど、モダンコンピューティングの基礎となる数々の発明を40年も前に生み出し、実際に稼働するシステムを聴衆の前で実演して見せたのである。
このデモの聴衆の中に、パーソナルコンピューターの父と言われるアラン・ケイがおり、強いインスピレーションを受けたというのはあまりにも有名なエピソードだろう。
ダグラス・エンゲルバートの偉業は、コンピューター技術とその応用を研究する世界中の研究者に多大な影響を与えた。1998年に彼がコンピューター分野では最高の賞であるチューリング賞を受賞したとき、HCI(Human Computer Interactions)の研究コミュニティーに属する研究者のみならず、彼の発明の恩恵にあずかる世界中の人々が心から受賞を喜んだものだった。
天才を超えられぬ40年間
FJCCでのダグラス・エンゲルバートによるライブデモの映像※をMITの授業で紹介すると、今なお学生は一様に驚きを見せる。40年もの前にこれだけのアイデアが生まれ、実際にフル実装されて公開の場でライブデモが実施されたという事実──言い換えれば、その後の40年間、天才ダグラス・エンゲルバートの発明に比べると特筆すべき進歩がほとんどなかったという事実にショックを受ける。
※ 伝説的とも言える、ダグラス・エンゲルバートによる1968年のFJCC(Fall Joint Computer Conference)でのデモ映像は、米スタンフォード大学のウェブサイトでアーカイブ化されている http://sloan.stanford.edu/mousesite/1968Demo.html
彼の偉業に感謝の意を表するためには、彼の発明したマウスの改良研究を行うのではなく、彼が'50~'60年代に挑戦したように、それまで存在しなかったまったく新しい流れを作り出す研究をすることが必要だと考えた。
それが、日本で10年間進めてきたビデオ通信技術を使ったCSCW(Computer-Supported Cooperative Work=コンピューター支援による共同作業)の研究を捨て、MITメディア・ラボに移った私が「Tangible Bits」の研究をゼロから始めたひとつの理由でもあった。
(次ページに続く)

この連載の記事
-
最終回
iPhone/Mac
Macintoshを通じて視る未来 -
第28回
iPhone/Mac
テレビの未来 -
第27回
iPhone/Mac
表現と感動:具象と抽象 -
第26回
iPhone/Mac
アンビエントディスプレー -
第25回
iPhone/Mac
切り捨てることの対価 -
第24回
iPhone/Mac
多重マシン生活者の環境シンクロ技法 -
第23回
iPhone/Mac
「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演を振り返る -
第22回
iPhone/Mac
ニューヨークの共振周波数 -
第21回
iPhone/Mac
ロンドンの科学博物館で見た過去と未来 -
第20回
iPhone/Mac
アトムのスピード、ビットのスピード - この連載の一覧へ