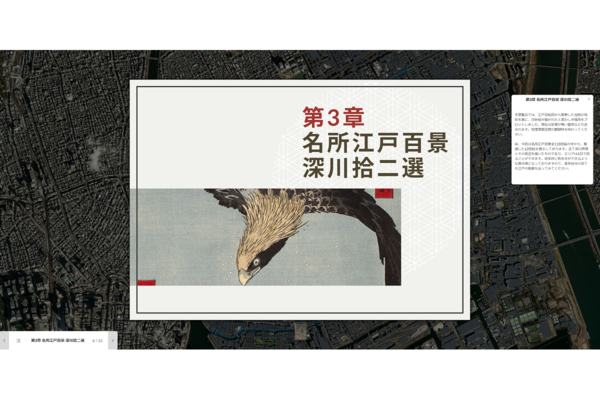「信長の野望」シリーズで特別な作品が生まれた理由。古橋大地氏×菊地啓介氏が語るデジタルツイン
「京都デジタルツイン・ラボ オンラインセミナー」レポート(前編)
提供: 京都市
2024年12月から2025年1月にかけて、京都市主催のイベント「京都デジタルツイン・ラボ」が開催された。国土交通省が手がける3D都市モデル「PLATEAU(プラトー)」を題材に、都市とデジタルツインの未来や活用法を探るオンラインセミナー、ハンズオン、ハッカソンを行う連続企画となっている。
今回は、12月8日に行われたオンラインセミナーでのトークセッション「変貌する都市とクリエイティブの未来」をレポートする。青山学院大学教授の古橋大地氏と、株式会社コーエーテクモゲームス執行役員の菊地啓介氏が登壇。デジタルツインや3D都市モデルの可能性を語った。なお本記事の後編では、データサイエンスを生かすまちづくりと、京都への活用法の模索についてのセッションも実施されている。
デジタルツインの民主化でもあるオープンデータ「PLATEAU(プラトー)」
オンラインセミナーの導入では、青山学院大学の古橋大地教授が3D都市モデルの概要、活用法を解説した。
「PLATEAU(プラトー)」は、国土交通省が多様なプレイヤーと連携して推進する、日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクト。プラットフォームデータとして3D都市モデルを整備し、誰もが自由にデータを活用できるようにオープンデータとして提供するとともに、さまざまな領域でユースケースを開発している。国が推進するプロジェクトの一環として、京都市もほぼ市内全域の3D都市モデルを公開している。
既存の地図データとの違いは、街路や建物の名称、建築年、用途などの情報までが属性として管理されていること。さらに標準化された汎用性の高いCityGML形式で提供され、誰もが自由にダウンロードし、商用利用を含めて無償で活用できるオープンデータになっている。地方公共団体の地理空間情報として公開されているこのデータは、ゲーム制作、都市計画、災害対策など幅広い分野に活用できる。
すでに、ゲーム制作用には「PLATEAU SDK for Unity」と「PLATEAU SDK for Unreal」という、ソフトウェア開発キット向けのツールも用意されている。
行政の災害対策部署やコンサルティング企業に向けても、QGISなどの地理情報システムに3D都市モデルのデータを入れられる「PLATEAU QGIS Plugin」や「PLATEAU GIS Converter」等を提供。必要な情報を一般的なGISにインポートして、都市を可視化することができる。
期待されていることは、行政、大学、企業、市民それぞれが自由にアイデアを出し合い、3D都市モデルの活用法を見出すことだ。ビジネスの創造はもちろん、利用者が各自でフィードバックを行い、データを更新していく「デジタルツインの民主化」というエコシステムの確立だと古橋氏は解説した。
ゲーム開発と3D都市モデルの未来は?『信長の野望 出陣』開発プロデューサーと対談
続いては、青山学院大学地球社会共生学部教授 古橋大地氏が聞き手となった株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 菊地啓介氏とのトークセッション。「クリエイティブ×都市データ」をテーマに、40周年を迎えた人気シミュレーションゲームシリーズ「信長の野望」の話題などを語り合った。(以下、本文敬称略)
菊地:シリーズ初のスマートフォン用位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』を2023年8月にリリースしました。自分が戦国大名になり、リアルな街を歩きながら砦を攻略して領地を広げたり、内政を行ったりして領地を拡大していく内容です。実際の名城を訪れると武将が手に入るなど、ご当地イベントも多数用意しています。地理情報という点では、Mapboxの地図システムや国土地理院のデータベースなど複数の地図情報をカスタマイズしています。
古橋:私もレベル100を目指してプレイしています。登用した武将を遠征させて領地拡大できる機能があり、海外でもゲームを楽しんでいます。2024年にPLATEAUのイベントで広島へ行ったときは、昼休みに広島城を訪れて武将を手に入れたことも。自分の行動が『信長の野望 出陣』によって最適化されています。
菊地:位置情報ゲームの醍醐味は、自分が暮らす地元はもちろん、日本全国にある素晴らしい場所を再発見できることです。歴史に触れたり、歴史ドラマの追体験を通して、旅行の楽しみを感じてほしいです。
『信長の野望 出陣』における3Dの捉え方
古橋:『信長の野望 出陣』はデジタルツインの側面を持っていると感じます。現代の地図をベースに、ある程度立体化された空間が構築されています。
菊地:どこまで3Dを取り入れるかは、ゲームデザインによって変わります。今回、戦国時代をテーマに位置情報ゲームを作るにあたり、歩いてプレイできるように道や建物は現代の地図である必要がありました。そのうえで、現代の地図に過去の重要なスポットを当てはめて使うことで戦国時代と現代をリンクさせています。また、脳の情報処理速度は限度があるため、基本的には高さの情報を排除して、区画がわかりやすいシンプルな地図に仕上げ、ピンポイントで3Dの城を建てるなど情報量を調整しています。
古橋:例えば京都は歴史が長く、時間軸を行き来できるゲームにも対応できるのでは。そのような歴史的な時間軸の意識はありますか?
菊地:検討したことはありますが、都市以外の古地図がほぼ存在しないため、日本全体で見ると難しいです。例えば京都だけというような地域に絞るなら、過去と現代をつなぐストーリーを展開させるゲームを作ることは可能だと思います。今後は生成AI技術を使って、足りない部分を補完できる可能性もあるでしょう。
京都の街と位置情報ゲームの親和性を探る
古橋:京都の街の構造について伺います。京都は今も独自の住所体系が生きていて、良い意味で歴史がある。『信長の野望 出陣』の中で京都を扱う時に、苦労したことは?
菊地:このゲームは街の区画単位で領地を広げるルールですが、日本はエリアによって区画の広さにばらつきがあります。特に京都は区画が細かく、ひとつひとつが非常に小さい。逆に最も広い北海道のある場所では、1つの区画が都市以上に大きくなることも。均一化を図るために一定の面積以上になるように複数の区画をまとめることにしましたが、それでも京都の区画は非常に小さく、実は攻略しやすい。初めて『信長の野望 出陣』を楽しむ方には、京都から始めることをおすすめしたいです。
古橋:過去に、京都で位置情報ゲームのイベントが行われたことがありましたが、街中にプレイヤーが散らばって盛り上がりを見せた。区画が非常にわかりやすく、移動しやすく、位置情報ゲームを楽しむには最適だと感じます。
菊地:京都は常に混雑しているイメージがありますが、裏通りなどは、人が少なく雰囲気のある通りがまだまだある。3Dモデルや地図データを使い、いろいろな場所に人が流入するようにすれば、混雑が緩和されるのではないでしょうか。
古橋:PLATEAUを含めデジタルツインを活用するにあたり、京都独自の魅力を引き出すアプローチに期待したい。作り手の想像力を引き出してくれる街だと感じます。
ゲームにおける主観性と客観性のバランス
古橋:『信長の野望 出陣』は、アバターに自己を投影しながら領地拡大を進めるゲーム。没入しやすいところが魅力ですが、どんなこだわりを持って作られたのでしょうか。
菊地:実は、もともとの『信長の野望』は、客観性の強いシミュレーションゲーム。主人公をプレイヤーキャラクターとして表示してそれを動かすのではなく、地図を見ながら領地拡大を目指すものでした。しかし、位置情報ゲームとして『信長の野望』を開発するにあたり、「自分がどこにいるのか」、「どこを歩いているか」を認識する必要が生まれました。主観的なゲームといえば、『Fortnite』や『Minecraft』のように自己の視点を軸に状況を克服するものが挙げられると思います。
古橋:確かに、以前の『信長の野望』は客観性の高いゲーム。今回に限って、自分の分身をフィールドに置いていることに改めて気づきました。
菊地:その通り。分身としてのプレイヤーキャラクターが、いろいろな武将や町人と交流し、全国制覇を目指す主観性が生まれています。自分の動きと地図の連動、領地の広がりの関連性を構築するにあたり、主観性と客観性のバランスを最も試行錯誤しました。
古橋:『信長の野望 出陣』はシリーズの中でも特異なゲームということがわかります。
菊地:初めて位置情報ゲームを遊ぶ人から「信長の野望」シリーズユーザーにも受け入れられるように、さまざまなエリアとのご当地コラボ、名城コレクション、歴史上に実在する強敵との対戦などのゲーム要素を加え、どんな人にも遊んでもらえるパッケージに仕上げています。実際に人が歩ける範囲には限りがあるため、武将を仲間に引き入れて遠征させるという要素も実現しています。
位置情報ゲームのゲームデザイン・世界観
古橋:『ドラゴンクエストウォーク』や『ポケモン GO』など、優れた位置情報ゲームがありますが、印象的だと思うものは?
菊地:一通り研究し、ヒットしている位置情報ゲームは、それぞれの趣旨に合うゲームデザインになっていると感じます。要素をそのまま『信長の野望 出陣』に適応させることはできませんが、これらのタイトルが位置情報ゲームを普及させた立役者であることは事実。あまりに内容が離れてしまうと、プレイヤーが理解しづらい可能性があるので、そこを意識しながら独自性を追及しています。
古橋:他のゲームと比べると、『信長の野望 出陣』は特に人間味を感じます。最初に主人公の拠点を2カ所決めますが、その範囲が本当に自分の領地になった気がしてくる。だんだん地元のプレイヤーの名前を覚えはじめ、ゲームの世界に愛着を感じるほど。
菊地:おっしゃる通りで、ゲームはプレイヤーが各自のドラマを描いて楽しむもの。自宅近くの城は絶対に守りたいとか、ご当地コラボイベント会場近くの城を攻めるとか、ゲームを通して実際の生活も豊かになります。
古橋:アバターが移動する空間も、正確に描かれた無機質な地図データではなく、たまに鳥が飛んでいたり、雨が降ったり風が吹いたりという演出が印象的です。
菊地:まさに空気感、世界観を上手に表現することがゲームへの没入感を誘います。例えばホラーゲームにおいて、リアルに描き込んだ背景や美しい幽霊を描くだけでは怖がってもらえない。光と影、空気感、少しの揺らぎを積み重ねて世界を構築することで、初めてプレイヤーの感情を動かすことができる。それはどんなゲームにも当てはまることで、ただ地図や城があるだけでは世界観は生まれません。
3D都市モデルのデータをゲームに活用するには
古橋:3次元表現を取り入れた位置情報ゲームは現時点では少ないですが、今後活用される可能性は?
菊地:まず重要なのが「そのゲームでプレイヤーに何の楽しさを提供するのか?」という目的。3次元は確実に人の興味を引くので、主観性のあるゲームの場合、建物の高さは必要になります。実際に、3D要素を加味した位置情報ゲームも開発されつつあります。開発の順序としては、京都市なら京都市の街を使ったゲームをデザインし、そこに位置情報の要素を加える方がスムーズ。既存の都市を舞台にした『Minecraft』とか『Fortnite』などもきっと面白いはず。
古橋:3D都市モデルの建物属性をはじめ、デジタルツインの公開データによって、ゲームにどんな特徴が生まれるでしょうか。意見を伺いたいです。
菊地:例えば任天堂の『スプラトゥーン』のように建物をペンキで塗りまくるゲームを、実在の都市を舞台に構築すると面白いのではないでしょうか。京都が舞台なら、裏道の土地勘がある人だけの楽しみ方もできそうです。京都は碁盤の目のように整備されているので、その特性を生かすゲームを作るとか。私なら、子どものころに地元のアーケードでケイドロをしたことがいい思い出で、それを反映した位置情報ゲームも楽しいと思います。
古橋:確かに、知っている都市や子どものころの遊びとデジタルツインを組み合わせると、自分の行動パターンとゲームの世界が連動します。高齢化社会では体を動かすためのモチベーションとして、ゲームによるアプローチは可能性がある。
菊地:歳を重ねると情報処理量が限られるため、「知っている場所」や「知っているルール」であることが遊びやすいです。
古橋:『Minecraft』のような目的のないオープンワールドゲームなど、大規模に大勢の人が集まるゲームにおいて、デジタルツインとの相性はどう感じますか?
菊地:相性はいいと思います。ただ、時間のかかるゲームを大多数の人が何種類も同時にプレイできる環境は生まれにくいので、切り口次第ではないでしょうか。
古橋:これまでの会話をまとめると、デジタルツインが持つ情報は膨大であり、ゲームのプレイヤーにわかりやすく伝えるためには主観性と客観性のバランスが重要。京都の街も含めて、より面白いゲームの組み立て方がこれから生まれそうな期待感を感じました。
菊地:PLATEAUが展開しているAWARDでも面白いアイデアが見られます。多くの人からユニークな提案が生まれることを楽しみにしています。