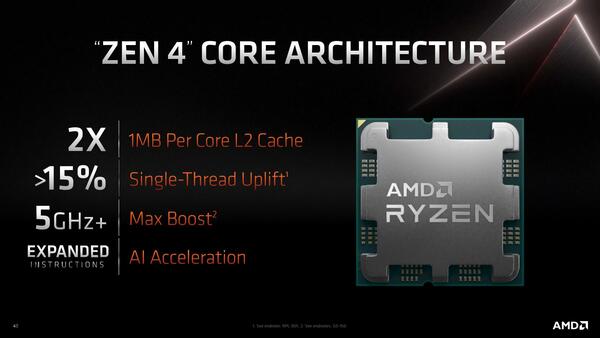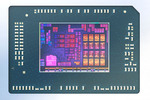6月23日、今年もオンラインでCOMPUTEX TAIPEI 2022が(南港での展示会も同時に開催されているので、オフライン併催という形態ではあるが)開催され、まず基調講演でAMDのLisa Su CEOによりRyzen 7000シリーズが発表になった。すでにKTU氏の記事が掲載されているので、もう御覧になった方も多いと思う。今回はこのRyzen 7000シリーズを少し深堀りしてみたい。
AI向け拡張命令を実装
性能の話は後にまわして、まずは下の画像にあるAI Acceleration Instructionsについて。
もともとZen 4世代ではAVX-512命令をサポートする見込み、という話は連載652回でも触れたとおりだ。なので、この延長でAVX-512 VNNIもサポートになったものと筆者は想像している。
もし新たなAI向けアクセラレーターをCPUコアとは別に搭載するならば、別に命令セットはVNNIである必要はない。連載665回で紹介したインテルのGNAのようなパターンだ。
ただこのスライドでも“EXPANDED INSTRUCTIONS”という表記をしているところから、既存のx86というかx64の命令パイプラインの中にAI拡張を施していると考えるのが普通で、となるとアクセラレーター案は現実味が薄い。
ではAI向け拡張を命令パイプラインに統合するとするとどこか? と言えば、一番現実味が高いのはSIMDエンジンである。AIプロセッサーの昨今の一連のシリーズでも紹介してきたように、とにかくAIというかCNN(畳み込みニューラルネットワーク)では、大量のデータを処理するスループット性能が必要になる。現状CPUパイプラインの中でこうした目的で実装されているのはSIMDエンジンであって、逆にSIMDエンジン以外にもう1つ、同じくらいのスループットを持つAIエンジンを持つのは無駄でしかない。
であればSIMDエンジンにAI向けの処理までやらせた方が効率が良い。そしてそのSIMDエンジンがAVX-512対応をするのであれば、VNNIを実装するのは自然な流れだろう。
ちなみにVNNIそのものにはあまり多くの命令は含まれておらず、以下の項目しかない。
- VPDPBUSD(8bit値のMAC演算)
- VPDPBUSDS(VPDPBUSDの符号付き)
- VPDPWSSD(16bit値のMAC演算)
- VPDPWSSDS(VPDPWSSDの符号付き)
したがって、実装はそれほど難しくない(むしろ容易)と思われる。

この連載の記事
-
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -
第763回
PC
FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -
第762回
PC
測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -
第761回
PC
Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -
第760回
PC
14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -
第759回
PC
プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -
第758回
PC
モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ