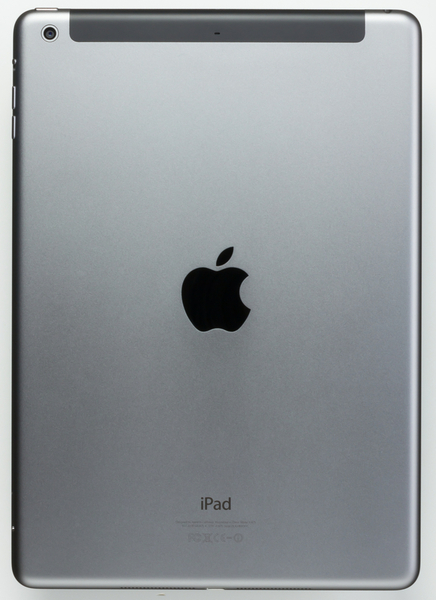旧iPadを“数世代前”に感じさせる、圧倒的進化
アップルスペシャルイベントで「iPad Air」という名前が発表されるのを見て、最初は戸惑いを覚えた。なぜ、そんな新しい名前をつけてしまうのかと。しかし、実際のiPad Airを触ってみた驚きは、それを上回るものだった。
2010年の誕生から、昨年のA6プロセッサーとLightning端子を搭載した第4世代にまで進化した9.7インチ液晶のiPadを触ってきた人間からすると、これはどうやっても同じ製品だと思うことができない。
重量はわずか469g(Wi-Fiモデル)。手に持った時に、まるで鉄板が1枚抜けたかのように感じる軽さだ。軽いを通り越して「軽すぎるんじゃないか?」と思ってしまうくらいの第一印象を持つのが、このiPad Airだ。
9.7インチの大型液晶を備えているだけに、頭に思い描く重さと、手に持った時、感じるはずの重さがあきらかに合っていない。ただし、もちろん、重量がないわけではない。1分ほど持っていると手への加重が蓄積されてきて、「なるほど、さすがに軽すぎというわけではないが、これなら長時間抱えていられる」と落ち着いた判断ができる。
ただ、重さの印象としては旧iPad(第4世代iPad)とではなく、むしろiPad miniと比較されるべきというくらいの軽さを、9.7インチという液晶サイズで実現しているのだ。
このマシンをしばらく使った後、第4世代iPadを触ると、「まるで鉛の鎧(よろい)」を着ているかのように重く感じ、アップルは1年の間にこれだけの進化を起こすのかと改めて驚かされる。
ただ製品を軽くするだけならば、おそらく去年でもできた。
しかしアップルは、例えばバッテリーの10時間駆動や、100万本近いiPhone共用アプリに加え、47万5000本のiPad専用アプリが快適に動くパフォーマンスといったものを最低条件として課し、それを崩さない中で製品開発を行なっている。
そう、iPad Airは、ただ横幅が縮まって、薄く、軽くなっただけではない。その上で、CPUには、次世代を感じさせる64bitの「A7」プロセッサーを搭載し、これから対応アプリが出てきて初めて本領を発揮するモーションコプロセッサー、「M7」まで採用している。
これによりグラフィックも含めたパフォーマンスは従来の2倍近くにまで伸びている。しかも、アップルはこういう時にCPUだけをやたら速くしたりはせず、全体のバランスを考えて進化させる。画面が大きく、CPUの処理能力が上がったら、その分、さらに高画質な映像の処理が可能になり、通信経由で再生する機会も増えてくる。ならばと、最新のIEEE 802.11ac(ドラフト)にこそ対応しなかったものの、MIMOという複数の電波を掴んで束ねて速くする技術を搭載し、Wi-Fiの通信速度も最大で2倍ほどに高速化しバランスをとっている。
これまでのiPadの進化の流れであれば、「だから、これまでと同じほどの重量とサイズ」だったのが、iPad Airでは、その流れを完全に変えてしまった。
これまでのiPadというよりは、むしろiPad miniに近い軽さを実現した。
アップルの上級副社長、フィル・シラー氏が「これだけ変われば、新しい名前を与えるに値する」と言い放ったが、iPad Airを手に持った今、それにうなずける。実際にその通りで、このiPad Airを触れた後では、旧iPadが何世代か前の製品にすら感じてしまう。