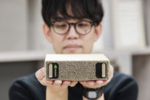DOSからWindowsへの移行で王座から陥落
大ヒットしたET4000の後継となったのが、1991年に出荷された「ET4000W32」である。基本的なコアの構造は同一だが、フレームバッファのバス幅を32bit(ET4000は16bit)に拡張して、最大4MBまでのDRAMをフレームバッファを搭載できるようにしたものだ。
ET4000W32はET4000と同じく、ISA/EISA/MCA/VLBusなどに幅広く対応していたが、その後はこれを少し作り変えた「ET4000W32p」と「ET4000W32i」に分かれる。ET4000W32pはPCIバスとVL-Busへの対応のみで、要するに32bitのホストバス向け製品だ。一方のET4000W32iはISA/EISA/MCAと、VL-Bus以外のローカルバス向けとなっている。
ET4000W32pやET4000W32iが出荷されたのは1992年の頃であるが、問題だったのは1989年当時にはバカっ速だったET4000コアも、この頃になるとそれほどでもなかったことだ。Windows 95が登場するのはもう少し後だが、この時点ではWindows 3.1とかWFW 3.11が広く普及しており、S3やATIがWindows用にバランスの取れた高速なビデオカードを出していた。
一方ET4000は、DOSでこそ超高速だったもののWindows環境ではまともなアクセラレーション機能がないこともあり、その性能をWindows上で活かすことはできなかった。残念だったのは、この頃になるとDOS上で動くゲームも、S3やATIのグラフィックスチップが持つアクセラレーション機能を、直接叩く製品がかなり増えてきていた。こうなると、よほど古いDOSゲームでもない限り、ET4000系は優位に立てなくなった。
もうひとつET4000系に欠けていたのは、RAMDACの内蔵である。1990年代に入るとローエンド機種から、RAMDACをグラフィックチップ内に統合して価格を下げる方向に進んだこともあり、RAMDACを内蔵しないET4000系は価格面でも不利だった。
MDRAM対応で逆転を狙うET6000を発表するも……
もちろんTseng Labsは、何も手を打たなかったわけではない。社内で「ET5000」相当の次世代製品を開発していたという話は聞こえてきたが、結局世の中に出なかったあたりは、何かしら問題があったのであろう。ET4000W32登場から4年後の1995年までの間、Tseng Labsからは新製品は出ないままだった。
1995年、Tseng Labsは突如「ET6000」を発表する。ET6000はMoSys社の提供する「MDRAM」(MultiBank DRAM)という、ちょっと変わったメモリーを使用する製品だった。ちなみに、MoSysはまだ存在しており、最近だと「1T-SRAM」や「High-Speed SerDes」といった、ちょっと特殊なアーキテクチャーを提供する会社となっているが、この当時はMDRAMが主力製品だった。
MDRAMはDRAMのセルこそ通常のDRAMと変わらないが(関連記事)、これを32KBずつの細かい塊(Bank)に分割して、それぞれを内部バスでつなぐという独特の構造をしていた。これにより、特にランダムアクセスの場合は複数のバンクへ同時にI/O要求を出せるため、アクセスレイテンシを短縮できるというのが売りであった。しかし、MDRAMを製造するのはMoSysのみだったし、MDRAMチップそのものがかなり大きかった関係で、ET6000シリーズ以外での採用例を誰も見たことがないという、ややキワモノなメモリーである。

この連載の記事
-
第859回
デジタル
組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -
第858回
デジタル
CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -
第853回
PC
7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -
第852回
PC
Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -
第851回
PC
Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -
第850回
デジタル
Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ -
第849回
PC
d-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現 - この連載の一覧へ