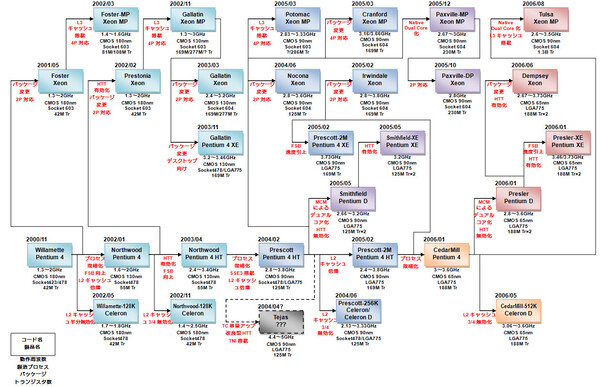CPU黒歴史第5弾は、インテルの90nm世代の話である。「Willamette」に始まり、「Northwood」でそれなりに性能と消費電力のバランスも取れて、しかも動作周波数を上げやすいということで比較的好評だった「Pentium 4」シリーズ。これに大ブレーキをかけたのが「Prescott」世代である。連載61回でも一度説明したが、まずはこのPrescottの話から始めよう。
大幅な機能拡張と高速化の工夫を
凝らしたPrescott
NorthwoodからPrescottへの改良点として、当初インテルから挙げられたのは以下のような内容であった(関連記事)。
- 90nmプロセスを利用し、さらに「歪みシリコン」を利用することで高速化を図る。
- 内部配置を大幅に見直すことでクリティカルパスを大幅に短縮し、より高速動作を可能にした。
- 1MBの2次キャッシュを搭載。
- 「PNI」(Prescott New Instruction)こと「SSE3」と呼ばれる新しい13命令を搭載したほか、既存の命令に関してもいくつか高速化を施した。
しかし、実はこれだけではなかった。というよりも、この程度の改良であれば、パイプラインが20段から31段にまで増える理由はない。Prescottは後追いの形で、以下の機能を実装していた。
- Intel VT(Vanderpool Technology)
- Intel IA32e(Yamhill Technologyの派生型、現在のIntel 64)
- Intel TXT(LaGrande Technology)
厳密に言えば、Intel TXTはPrescottや後継の「CederMill」の世代では結局サポートされなかったのだが、実装されたのはこの時期だった。これらの拡張をサポートするために、Prescottでは長大なパイプラインが実装されることになったのである。

この連載の記事
-
第781回
PC
Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -
第780回
PC
Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -
第779回
PC
Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -
第778回
PC
Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -
第777回
PC
Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -
第776回
PC
COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -
第775回
PC
安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -
第774回
PC
日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -
第773回
PC
Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -
第772回
PC
スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -
第771回
PC
277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ