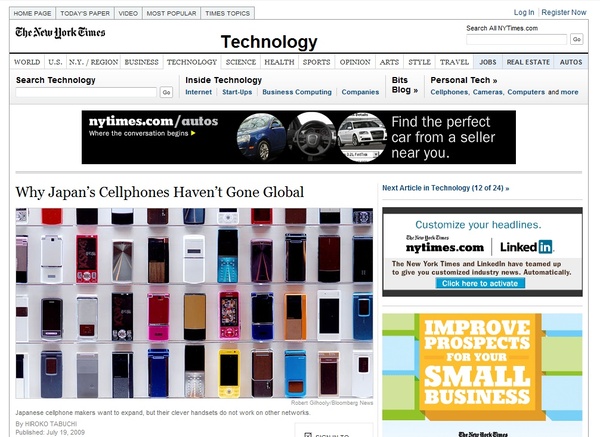世界語になった「ガラパゴス」
日本の携帯電話を「ガラパゴス」と呼ぶのはもはやおなじみだが、今では世界に通用するようだ。19日のニューヨーク・タイムズは、「日本の携帯電話はなぜグローバルにならなかったのか」と題して、ガラパゴス症候群を紹介している。
日本の携帯電話のイノベーションは驚異的だ。1999年にはEメールを、2000年にはカメラを、2001年には第3世代を最初に実用化し、2002年には音楽ダウンロード、2004年にはおサイフケータイ、そして2005年にはデジタルTVまで内蔵した。日本のスマートフォン・ユーザーは1億人でアメリカの2倍だ。
しかし日本のメーカーで本格的に世界市場で商品を売っているのは、外資と合弁のソニー・エリクソンだけ。その市場シェアは6.3%で巨額の赤字に苦しんでいる。昨年の日本の携帯電話の売り上げは前年比19%も落ち込んだ。その一部の原因は販売奨励金の廃止だが、もはや国内市場は飽和し、このままでは8社もある端末メーカーが生き残ることは不可能である。
こうした状況の中で、これまで海外事業を縮小してきた端末メーカーも方針を転換し、ふたたび海外に打って出る戦略を検討し始めている。NTTドコモの「iモード」を開発した夏野 剛氏も言うように、日本のメーカーの技術は今でも世界一だし、人材も資金も十分だ。何が無いのか、それは「決断する経営者だ」と夏野氏は5月の「アゴラ起業塾」で言った。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ