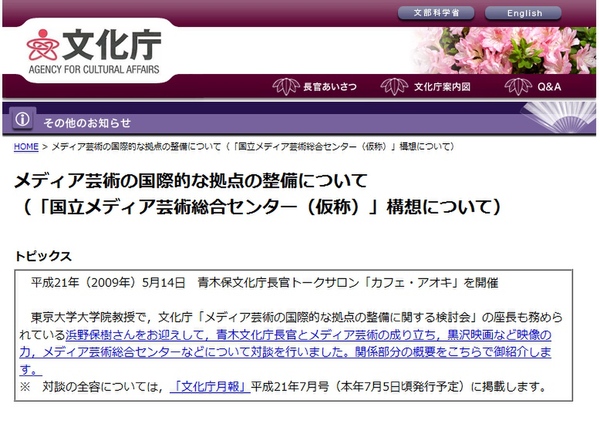「100年に1度」の大盤振る舞い
予算規模13兆9000億円という史上最大の補正予算が決まり、霞ヶ関は久しぶりに活気がよみがえっている。普段は認められない予算が、「景気対策」の名目で一挙に認められたからだ。庁舎の改築費や機材の調達費など、当初予算で落とされた経常経費が「緊急対策」として数年分一挙に認められた。
その大盤振る舞いの象徴が、民主党に「国営マンガ喫茶」と揶揄された「国立メディア芸術総合センター」だ。マンガやアニメなどを展示する国営の展示施設を117億円で建設するというが、これは4月末に有識者会合で答申されただけで、中身は何も決まっていない。青木保文化庁長官は「こういう予算がつく機会は今後50年、100年は来ないかもしれない」と発言した。「100年に1度の危機」を理由にして100年分の予算を一挙に使う、常軌を逸した予算だ。
不況は企業がリストラによって事業を効率化するチャンスだが、役所が公的資金を注入して救済することは、その努力を阻害する結果になる。その最たるものが、今回の補正予算で新設が決まった産業革新機構だ。これは官民ファンドによって民間企業に出資するもので、最大9000億円の出資枠が用意されている。出資先としては、日立製作所やパイオニア、エルピーダメモリなどが想定されている。
この手本は、2003年に設立された産業再生機構である。これは不良債権処理にともなって経営危機に直面した企業の再建を支援するために官民ファンドで出資したもので、カネボウやダイエーなどの再建を支援し、この種のファンドとしては珍しく成功したケースと評価されている。2007年に解散したが、最終的には700億円あまり納税し、国民負担は生じなかった。
しかし今回の革新機構は、再生機構とは似て非なるものだ。2003年当時は、銀行の不良債権処理が始まったばかりで、新規融資がむずかしいため、政府が一時的に支援することはそれなりの意味があった。しかし今回は、日本の金融システムは大きく傷ついておらず、超低金利で融資資金には余裕がある。こういう状況で民間から融資を受けられない企業というのは、要するに借りた金を返せない企業である。それに政府が出資すると、貸し倒れになるリスクが高い。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ