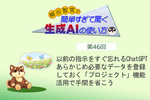物価高騰の影響を受けて、SaaSのコストもどんどん上がっている。また、生成AIの機能を使うために追加コストが必要なサービスもある。コロナ禍で増えすぎたSaaSをきちんと最適化していくためには、ユーザー企業側でも正しい目利きが必要になる。
値上がり続けるSaaS LINE WORKSの450円はやっぱり安い
最初のトピックはSaaSのお値段についてである。われわれは日々、外食や買い物などあらゆるところで物価高を意識するが、当然ながらSaaSの価格も上がっている。価格改定と言うが、基本的にはすべて値上げだ。この1年の代表的なSaaSの値上げを振り返って見よう。
・2024年4月 Google Workspaceが15~20%程度の値上げ
・2023年7月 Chatworkが4~5割の値上げ
・2023年8月 Salesforce各製品が平均9%値上げ
・2024年2月 freee、個人事業者向けの価格を25%値上げ
・2024年3月 Zoom、昨年に続き値上げ
・2024年4月 Microsoft 365が20%の値上げ
そして、この記事を書いている最中、いよいよサイボウズのkintoneの値上げも発表された(関連記事:kintoneはライトコースも1000円に 最小契約ユーザー数の変更も影響大)。為替の変動、インフラやエンジニアのコスト上昇など理由はさまざまだが、SaaSにしろ、サブスクにしろ、値上げは予告や交渉の余地もなく、一方的に通知されるだけだ。期初には予想でできないので、情報システム部や導入した現場部門はやりくりする必要がある。ここで言う「やりくり」とは使わないSaaSを解約したり、別のサービスに統合したり、安価なサービスに乗り換えることを指す。固定費のコストにメスを入れるのは、家計のやりくりの基本でもある。
こうした中、先日開催されたLINE WORKS DAYの基調講演でアピールされたのが、ビッグマックより安い月額450円という価格だ(関連記事:LINE WORKSはビッグマックより安い)。あくまで1ユーザーの月額料金なので、会社で契約すればそれなりの価格になるかもしれないが、安いのは確かだ。増田氏はビッグマックを引き合いに出したが、Slackのフリープランが月額925円(年払い)、Acrobat Standardが月額1518円、kintone(スタンダードプラン)が月額1500円(新価格は1800円へ)なので、同業のSaaSと比べても安いのである。
もちろん、重要なのはその料金に対して、どれだけの価値を得られるか?だが、この物価高時代、単純に安いというだけでメリットと感じられる企業も多いはず。実際に記事も読まれており、読者の関心の高さがうかがえる。
生成AIの利用でコストは倍に 移行するにも今後はデータが人質に
そして、もう1つ値上げのポイントとなるのが、盛り上がる生成AI機能だ。現在、多くのSaaSベンダーはやっきになって生成AIを自社プロダクトに取り込んでいるが、機能として提供された暁にはオプションとして提供されることが多い。
たとえば、Notion AIは月額10ドル、Slack AIは月額1200円が追加料金。製品によっては、ほぼ料金が倍になる。SalesforceもEinstein AIを搭載した最上位プラン(Einstein 1 Sales)は月額6万円となかなかのお値段だ。ただ、数は少ないが、AsanaやBoxのように生成AI機能を追加チャージなしで提供するベンダーもある。「もともと高いから」という声はあろうが、追加チャージなしに最新の生成AI機能を利用できるメリットは大きい。
生成AI機能の導入は、既存のLLMを使うにせよ、自社開発するにせよ、いずれにしろ開発と運用にかなりコストがかかる。こうしたコストはユーザー側に転嫁されるわけだが、ユーザー側も便利そうだからといって飛びつくのではなく、きちんと使いこなし、価値を得られるかどうか見定める必要があると思う。
今後もSaaSの最適化は重要になっていく。重要なのは単純にコストを減らすだけでは、得られるメリットをきちんと定量的に図り、継続的に最適化を図っていくことだ。利用度やメリットで階層化したり、予算プールをあらかじめ設定する、ユーザーの浸透度をKPIにしたり、ユーザー企業も知恵を絞っている。最適化を日常的に進めていけば、新しいプロダクトにチャレンジする余裕も生まれるはずだ。
こうした中、SaaS管理サービスのニーズはますます高まっていくだろう(関連記事:情シスが向き合うSaaSとデバイス管理の課題 ジョーシスとマネーフォワードiが語り合った)。可視化のみならず、最適化のアイデアやベストプラクティスも含めて、プロダクトのセンスが問われる分野だと思う。
SaaSのロックインとデータポータビリティの課題
お値段の話題とともにトピックとして挙げたいのは、SaaSのロックインに関する話題だ。先日、「SAPPIRE 経費精算」を手がけるMiletosが実施したSaaSロックインに関する調査発表では、今のSaaSに不満があるのは75%に上るが、69%はベンダーロックインがあると答えている(関連記事:今のSaaSに不満があるのは75% でも69%はベンダーロックインの状況)。最大の障壁は、移行コスト。ユーザーデータはもちろん、内部規定、監査項目、承認階層、経費種別、勘定科目などの企業ごとの複雑な項目設定も、移行を戸惑わせる要因だという。
ただ、この調査結果を見て思ったのは、ロックインがあるかどうかは別として、システムの移行はそもそも難しいという点だ。SaaSの場合、データ自体はユーザーのものだが、データベースは事業者が管理するサービスに組み込まれている。データはユーザーのものだが、移行できるかどうかはひとえに事業者次第だ。エキスポートしたCSVファイルを手作業で移行するのが正しいのか? 過去の取材では、ヘビーリフトな移行作業を避けるべく、「そもそも移行しない。ゼロから導入する」と判断した企業も多い。
また、前述したSaaSの値上げも「ほとんどのユーザーは定着しているため、値上げしても解約は少ない」という前提で行なわれている。実際に解約率が少ないため、事業的にプラスになっている指標を公開している事業者もある。AIでの利活用を前提とすれば、今後SaaS事業者はAIで得た知見や価値を定着のためのデータを武器として使う。ユーザーからすればデータが「人質」にとられたら、他システムへの移行はますます難しくなるという話になる。
その点、先日取材したサイバーセキュリティクラウドは、マネージドセキュリティを提供しつつ、データ自体はAWSに保存するという選択肢を提供しており、ユーザーフレンドリーだと思った(関連記事:脱WAF屋を実現したサイバーセキュリティクラウド プラットフォーマーの肩に乗る強み)。また、APIを活用して、ユーザーデータを積極的に活用できる環境の整備も必要だ。SaaSのビジネスでも、こうしたデータのポータビリティを前提とした仕組みが今後重要になると思う。
大谷イビサ

ASCII.jpのクラウド・IT担当で、TECH.ASCII.jpの編集長。「インターネットASCII」や「アスキーNT」「NETWORK magazine」などの編集を担当し、2011年から現職。「ITだってエンタテインメント」をキーワードに、楽しく、ユーザー目線に立った情報発信を心がけている。2017年からは「ASCII TeamLeaders」を立ち上げ、SaaSの活用と働き方の理想像を追い続けている。

この連載の記事
-
第119回
ITトピック
もう「マサカリ」は恐れないで AI時代は失敗の共有こそ次につながる -
第118回
Team Leaders
AI確定申告の気運高まる 申告者はチェックして、あとは「告る」のみへ -
第117回
ITトピック
生成AI時代の露払いとしてAlexaの果たした役割は大きい -
第116回
Team Leaders
その日、オレは思い出した 場所と時間に囚われていた社員総会を -
第115回
ITトピック
生成AIでアプリを作ったらSaaSを解約できた話 -
第114回
ITトピック
旅の途中で金沢のSORACOM UGに参加したら、地方勉強会の良さを改めて体感できた話 -
第113回
ITトピック
AIが商品を選び AIが店を切り盛りする -
第112回
TECH
ドワンゴサイバー攻撃で改めて認識したい「皆さん他人事じゃないです」 -
第112回
ネットワーク
IoTはオワコンじゃない 10年目のソラコムイベントで見た熱狂 -
第111回
ITトピック
スピッツの曲に見た「人の価値創造」 及川さんの話、刺さりすぎです -
第110回
エンタープライズ
PC管理はもう勘弁 Windows 365 Linkへの関心に情シスの叫びが聞こえる - この連載の一覧へ