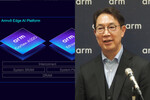利用者の本音が飛び出した「SORACOM LoRaWAN Conference 2017」
低速・長距離・省電力なLoRaWANが実現する、ちょっと先の未来
2017年02月09日 11時30分更新
活用にはLoRaWANの特性を知り、データ取得方法を工夫することが必要
後半2セッションは、いずれもPoCキットを使った実証実験に取り組んだ企業を招いてのパネルディスカッションとなった。1本目のパネリストは、M2Bコミュニケーションズ 取締役 渡辺 誠氏、ウフル IoTイノベーションセンター 竹之下 航洋氏、ファームノート デバイス開発マネージャー 阿部 剛大氏。最初にPoCキットを使って各社が行なった検証について紹介。
M2Bコミュニケーションズは、LoRaデバイスの試作に取り組んだ。加速度センサーと物理センサーを併用してバッテリーだけで3年間稼動する地滑りセンサーなどを実際に制作し、展示ブースでも公開していた。「920MHz帯はアンライセンスドバンドと言われているが、これは通信免許が不要という意味。デバイスは技適を通過したものしか使えず、海外のLoRaデバイスを購入して勝手に使用できる訳ではない」と、デバイス面での注意点を挙げていた。

M2Bコミュニケーションズ 渡辺 誠氏
ウフルはLoRaデバイスを使った社内備品管理のシステムを試作。備品にビーコンを取り付けることで、備品の場所、それを使っている人の移動をトラッキングしてみたという。「SORACOM Air for LoRaWANはデバイスからデータが送り込まれるパターンがサービスで作り込まれているので、Web屋でもIoTサービスに参入できる」と魅力を語る一方で、「3GのSORACOM Airが安価なので、デバイスを200個くらい使わないとSORACOM Air for LoRaWANのコストメリットが出ない」とも指摘した。

ウフル 竹之下 航洋氏
ファームノートは、十勝の牧場で牛にデバイスを取り付けて、個体の動きをトラッキングした。これまでは総体としてしか把握できていなかった牛の個体ごとの動きの違いがわかり、「今後は咀嚼回数から食事状態や健康状態を把握したり、フィーダーの稼働状況をモニタリングしたりしてみたい」と更なる検証に向けた意欲を語った。

ファームノート阿部 剛大氏
パネルディスカッションでは、ソラコムの事業開発マネージャー、大槻 健氏がモデレーターを務めた。欲しいデータの取り方について尋ねたところ竹之下氏は、「LoRaで送れるデータ量はとても小さいので、本当に欲しい情報を間接的に取得する工夫が必要」だと答えた。たとえば会議室の利用状況を知りたければ、人感センサーではなく単純な照度センサーを使い、明かりが付いていれば使用中とみなす。とにかく単純で小さなデータを使う工夫が必要だと言う。また、デバイスからデータが届くまでの遅延は1秒程度なので、シビアなデータでない限りタイムスタンプはサーバー側で付与することにすれば、時刻データも不要と割り切れる。このあたり、何のデータが必要で、何を妥協できるかがサービスの作り込みで重要なポイントになるのかもしれない。
超省電力でバッテリーのみで長時間使えるのもLoRaの魅力のひとつだが、実際に使ってみてどの程度の駆動時間が欲しいと感じたか、という問いへの各社の答えも興味深かった。デバイスメーカーの視点から渡辺氏は、「10年使えるものを目指したいが、顧客には5年を目安にと伝えている。最適な通信頻度を探ることで、実際の稼動期間を伸ばせるのではないかと考えている」と語った。竹之下氏はクラウドサービスとして提供することを前提に、「そもそもクラウドサービスが10年も生き残るかということ自体も疑問。そう考えると、コンシューマ向けサービスではあえて電池寿命を短く設定するのもありかもしれない」と回答。牛の実証実験を行なっている阿部氏は「取り付けや取り外しが大変なので、牛の商品価値がある7年は付けっぱなしで済むようにしたい」と、検証現場に特化した答を返していた。