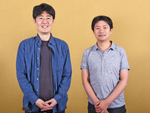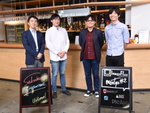産業用ドローンメーカーとして国内で高いシェアを持つエンルート(enRoute)。今回はさくらインターネットの田中邦裕社長、高火力コンピューティング担当の須藤武文さんとともに、エンルートの伊豆智幸社長にインタビュー。起業の経緯や、最近注力している機械学習とドローンの関係までをディープに語ってもらった。
ラジコン好きが講じて、ドローンメーカーを興すまで
「小さい時からラジコンが好き。ラジコン屋を始めたいなと思ってた」
エンルート社長である伊豆智幸さんの一声目で、エンルート立ち上げの経緯はほとんど語り尽くされたと言っても過言ではない。そう。伊豆さんのラジコン好きが高じた結果、国産ドローンを製造するエンルートは生まれたのだ。
「小学生のときはヒモが付いている『ユーコン』を校庭でブンブン振り回してた」という伊豆少年だったが、その後、好きが講じて電子工作系にシフト。大学卒業後は計測器メーカーだった横河ヒューレット・パッカードに就職し、その後は19年近くサーバーやワークステーションのマーケティングを担当。思い返せば、順風満帆のIT業界でいい目を見てきた世代だったという。一方で、ラジコンの自作は趣味として長らく続けており、サーボモーターやバッテリなどの部品を使って、自身のオリジナルの機体を作っていた。

エンルート代表取締役社長 伊豆智幸さん
その後、2000年過ぎから、サイトビジネスで海外のラジコン商材の輸入を手がけ始める。「ちょうどラジコンの動力源がエンジンから電動にシフトし始めた頃。リチウムポリマーバッテリやネオジウムを使ったブラッシュレスモーターが模型用に出回り始めたけど、当時のショップは電気のことをあまり知らなかった。僕は電気もわかったので、専門性と目利きでモーターやバッテリを輸入して、販売していたら、けっこう軌道に乗り始めた」(伊豆さん)とのことで、2006年にいよいよ脱サラ。自身の夢だったエンルートを起業する。「ずっと遊びだったので、今度は自分で設計して、デザインして、製品化して、遊ぶモノを作りたかった」と伊豆さんは語る。
ラジコンからドローンへという流れも自然な流れだった。「フライトコントローラーや送受信機などは基本的に既製品があるので、それを組み合わせてオリジナルの機体を作ればよい。大量生産の機種とは異なる、たとえば橋にぶつかっても壊れないドローンを作ることにした」とのことで、中国の工場をベースに産業用のオリジナルドローンの開発を手がけることになる。
埼玉県のふじみ野にあるエンルートの本社は、そんな伊豆さんの「遊び場」と言えるようなスペース。ドローンというとマルチコプターというイメージが強いが、車型のドローンや船型のドローンもある。まるでプラモデルを作る作業場がそのまま巨大化したようなワクワクするスペースだ。

作業場に並ぶドローンの試作機に田中社長も興味津々
エンドユーザーの声を聞いて、オリジナルのドローンを提案する
エンルートのドローンは用途に応じて、プロペラの種類や、カメラやセンサーの有無などを選択するオーダーメイドの製品になる。とはいえ、空間認識の優れたMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)のおかげで、ドローン自体の設計はきわめてシンプルだ。「飛行機やヘリコプターって大きさや形が変わると設計に手直しが必要なんだけど、電子制御のマルチコプターってモーターにプロペラを付けておけば基本的に飛ぶ。1kg持ち上げるのに、何W必要かの計算も机上だけでできる」(伊豆さん)とのことで、コンサルティングもしやすいという。
とはいえ、受託仕事はやらない。「仕様書がそうだから、それ以上のものは作らない。口を開けて、お金が入ってくるのを待っている。そんなビジネスはあまり好きではないので、あくまで提案型です。お客様の要件に対して、こうしたら喜んでくれるんじゃないかという専門家としてのソリューションを考えます」と伊豆さんは語る。「橋を点検したい」「農薬を散布したい」「資材を運びたい」など、さまざまな顧客のリクエストを聞き、適した機種や運用法を提案していく。ここにラジコン時代から培ってきたノウハウが活きてくるわけだ。
国内でもドローンを手がける業者は数あれど、エンドユーザーと直接話して、機体の開発から運用提案までできるところはエンルートくらいしかない。「この分野ではダントツで日本一だと思っています」と伊豆さんは語る。
「たとえば、1時間動作して、10kgのモノを運びたいみたいな相談を受ける際も、1台でやろうとすると、どれくらいの機体が必要になるのかお客様にアイデアがない。だから、こうした場合はコンパクトな機種を使って、複数台を分散して運んだ方がいいと提案します」(伊豆さん)。
NDAベースの契約が多く、公開できないことがほとんどだが、精密農業や僻地での物流、災害時の測量など採用事例は多種多様だ。たとえば、精密農業と呼ばれる分野では、農薬の散布、収穫予測、虫食いの状態把握などにエンルートのドローンが使われ始めている。「今までデータを収集していないので、データからどのような価値を得られるかを考えるのは、これからのフェーズ。農家の方々が持っている経験値を数値化して、専門家じゃなくてもピンポイントで適切な農薬が散布できる世界を実現していきたいですね」と伊豆さんは語る。