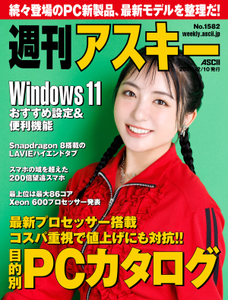「このプロジェクトのゴールは? 最終的にどんなことをやるのか?」という問いに対しては、「自分たちで決めてくれ、と思っています。これまでの資本主義や働くことに対して、社会に疑問が出ている時代。お金をもらえる仕事ともらえない仕事の定義もあいまいです。案外、素人っぽいものにお金が支払われるかもしれない。利益もオレたちのもの、って感じではなく、オープンになればいい」と語る安田さん。
実際に、これまでエントリーした人は一人も断っておらず、選考は一切なし。「むしろ自由にほかのニートを誘って、参加させてあげてほしい」(安田さん)と呼びかける。
新しい価値をニートが生むかもしれない?
若新さんは「今までニートは無能な人、不景気で仕事がないから増えてきた、などと国が支援する対象だったけど、本当は彼らは恵まれた『貴族』。既存の9時-5時の仕事に就かなくてもいいので、趣味みたいなことをしているだけ。でも今は趣味かもしれないけど、将来それらは何か価値を生むかもしれない」と期待を語る。
「ルールはみんなで考える」「固定給なし、搾取なし」「儲かったら、みんなが納得できるように分ける」ということ以外は、説明会終了後も方向性について語られていないビジネスモデルだが、2人はあくまで支援にとどまり、目標設定は今後集まったニートたちに任せるということだ。
「経験則から、彼らはコントロールしないことでうまくいくと思う。実験的なプロジェクトなので今後どうなるかわからないが、もしうまくいったら全国にモデルを広めたいというのはある。札幌とか福岡とかで、それぞれ会社を作ってもいい」(若新さん)。
エントリーシートを見る限り、IT、ネット関連の人材も多いようだが、彼らには「枠組みを超えた働き方をしたい」という願望があるようだ。だからこそ、利益が出るかどうかわからないプロジェクトに集まってくる。
「ITスキルがあれば、会社に属さなくてもそこそこ生きられるかもしれない。でも、自分たちが承認される場を共有して何か大きなことをしたい、という気持ちがあるのではないか」と若新さんが言うように、サラリーマン中心社会ではマイノリティの彼らニートがスキルを生かし、既存の社会に風穴をあけるような試みができるのか――。9月に設立される予定の会社組織で、その答えが見えてくるかもしれない。