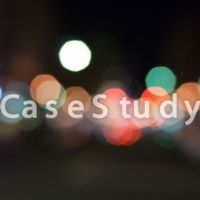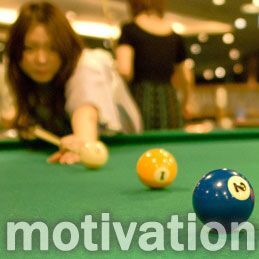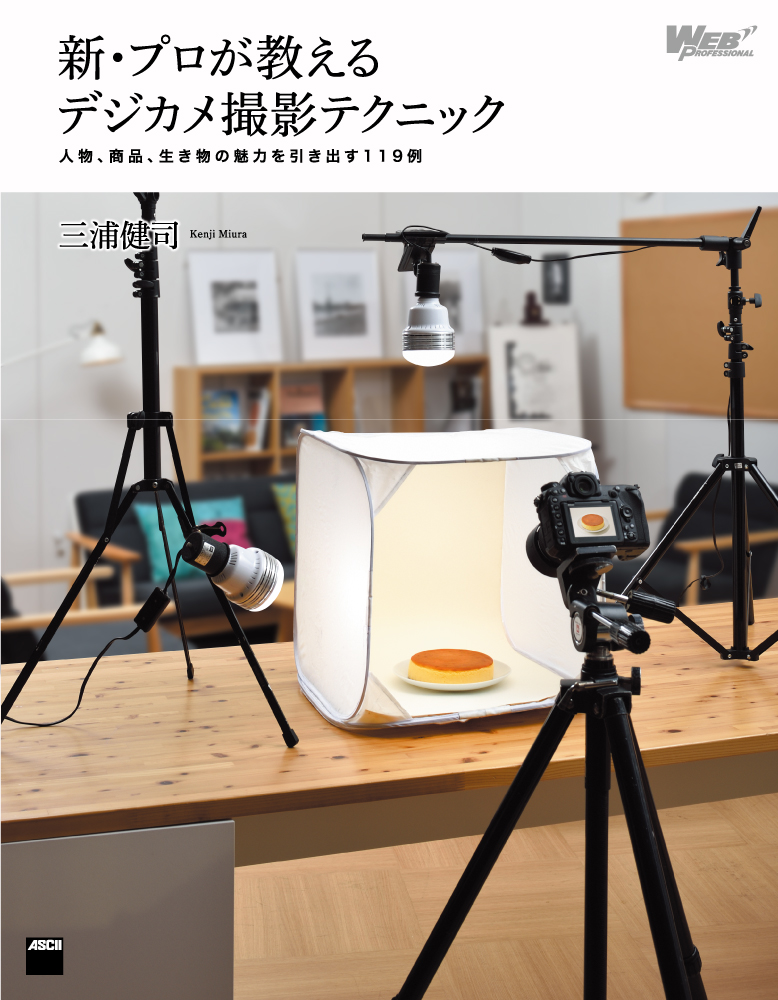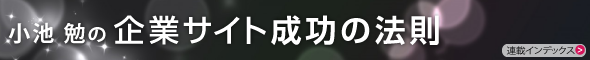
|
|---|
FacebookなどのSNSを多くの企業が活用し始めている一方で、SNSにまだ手を出しかねているところもあります。理由のひとつに、社会に対する責任感が挙げられるでしょう。SNSは顧客と直接つながる重要なチャネルであり、始めたからには運用を継続していく責任が伴います。今回は、企業のポリシーを守りつつ、SNSを継続していくための運用法について述べます。
SNSはもともと個人がつながるツール
企業SNSの運用で忘れてはいけないのは、SNSは企業サイトと異なり、「友達」「知り合い」との個人的なコミュニケーションが原型となっている点です。そのため、「距離感の近い、お客様と企業のフレンドリーな関係」が生まれ、企業のファンを作ることもあれば、反対に炎上(問題化)することもあります。
キャンペーンサイトであればキャンペーンが終わった時点で更新を終えてしまえばいいわけですが、企業SNSはいったん始めてしまえば、継続していく責任が生まれます。
継続を前提に企業がSNSを運用していくには何が必要なのでしょうか?
1人運用体制での長期運用は厳しい
プランナーである私が伺った企業の中には、SNSのスタート時に「担当者が1人いれば運用できる」と安易に考えているケースが結構ありました。結果、すべてを背負わされた担当者が、通常業務のほかにSNSを運用するはめになり、にっちもさっちもいかなくなっている例も珍しくありません。
前回(連載 第10回)書いたように、企業SNSは「企業の顔」となるため、始める前にしっかりとした準備が必要です。具体的には、企業としての人格(キャラクター)、ポリシー、ターゲット層、伝えたいテーマを決め、どのように運用していくかを計画しなければなりません。
それらをすべて担当者1人に任せてしまうのは、荷が重すぎるといえるでしょう。だからこそ、必要になのは体制作りであり、「SNSの編集チーム」を作ることだと考えます。
「編集チーム」と表現したのには理由があります。雑誌や書籍の制作には、「編集」というスタッフが関わっています。編集者の仕事とは何でしょうか。編集者は、読者のいる市場を探し、売るためのコンセプトを考えます。そしてライターやカメラマン、デザイナーと協力しながら、1つの企画として作り上げていきます。
つまり、1つの企画を完成させる裏には「編集」を中心としたチームがいるのです。さらに、編集者は長期的なスパンに立ち、次号、次々号を想定してチーム全体を動かしていきます。
このような体制が確立されているから、定期的に雑誌を発行できるのです。
SNS的「編集」が企業とユーザーを結ぶ話題を生み出す
雑誌の体制を企業SNSに置き換えて考えてみましょう。
SNS担当者は、現場を取材したり文章を書いたりして、発信する情報を作ります。編集者は、常に「会社としての情報発信」を意識して、俯瞰した立場から運用に関わります。SNS担当者と編集者は「会社の顔」を意識しながら、編集会議を重ねて企業SNSの方向性を考え、発信する情報を相談し、掲載するタイミングを決めていきます。
つまり、編集者が関わることによって、「SNS担当者」「編集者」そして「企業(会社の顔)」という三角構造が生まれるのです。
SNSであるからには、発信した情報に「いいね!」やコメントが付けられます。質問や疑問のコメントに返事をしたり、評価の高い記事には続編を作ったりと、正しい誘導やネタの切り替えも必要になってきます。そのような臨機応変な対応も、チームで取り組むことで対処しやすくなるでしょう。
とはいえ、突然「雑誌の編集部のような体制を作る」といわれても困るでしょう。会社の中で編集チームを作るとすれば、編集長の役割をその部署のリーダー(たとえば部長など)にお願いして、少しずつ体制を固めていけばいいでしょう。リーダーには、企業での経験や知見を活かして編集方針を決めたり、豊富な人脈を生かして他の部署から協力をもらったり、情報モラルのオンブズマンとして積極的に活躍してもらいましょう。
SNSの運用にまだ慣れないうちは編集長とSNS担当者が1人ずつではなかなか考えが広がらないかもしれません。その場合は、部署の他のメンバーにも、ひとりの編集者として編集会議に参加してもらうといいでしょう。
SNS担当者と編集者とで立場は違っても、ユーザーの心をつかんでファンを拡大する目的は同じ。チームの目的は、発信する情報のチェックだけではなく、「楽しく効果のある企業SNSを作るため」であることを忘れないようにしたいものです。