WindowsDNA(Distributed interNet Applications Architecture)による先進ソリューションを業種別に紹介する“WindowsDNA
Conference 98”が、赤坂プリンスホテルで3日まで開催される。“WindowsDNA”とは、マイクロソフト社が推進する“3階層型システムモデル”。同モデルは、ユーザーインターフェース機能を稼動するクライアント層、ビジネスロジック部分を稼動するアプリケーション層、データベースを稼動するデータ/ストレージ層で構成される。初日は、サプライチェーンマネージメントの最新情報を紹介。2日目は、製造、設計、流通の各ソリューションの最新動向を紹介し、3日目は、金融システム進化の方向性や、インターネット、デリバリーチャネル、規制緩和、電子証券取引などの最新動向を紹介する予定となっている。
1日の午前中は、マイクロソフト(株)常務取締役の長谷川正治氏が“マイクロソフトのバリューチェーン戦略”というテーマで、慶応大学ビジネススクール助教授の國領二郎氏が“オープンネットワーク上における新しいバリューチェーンの構築”について、フューチャーシステムコンサルティング(株)代表取締役社長の金丸恭文氏が“金融・流通・製造ビックバンのインパクト”について講演した。
“Value Chain”というシステムを持つことが最も重要な出発点
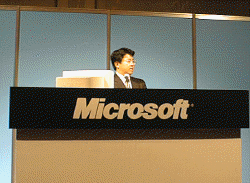 |
|---|
| マイクロソフト(株)常務取締役の長谷川正治氏 |
長谷川氏は、まず「システムは、変化に対応できるようにしていかなければならない」と述べた。マイクロソフトは、サプライチェーンマネジメントを取引に関わるすべての企業の参加が必要という一歩踏み込んだ視点から捉え、これをバリューチェーンとしている。
同氏は、人間の神経系のように、デジタルの世界にも知識や情報の出し入れ、危機や予測していないものへの対応をできるようにしていかなければならないという。今までの資源は、人、物、金であったが、これからは人(社員)、プロセス(業務の仕方)、パートナー(顧客ベース、パートナーベース)であり、ここでさまざまな取引がなされる。すなわち、あらゆる産業システムと情報システムの連携が必要不可欠であり、これをどのように統合していくかが課題であるとしている。
ビジネスロジックとプレゼンテーションの部分をいかに早く作るかが鍵である。また、リアルタイムでデータを消費者から供給者サイドまでいかに速く行き来できるようにするかがポイントだという。ここでは、企業の規模が絶対的な強さではなく、“Value
Chain”というシステムを持つことが最も重要な出発点になるのではないだろうかと同氏は述べた。
現在、同社の企業間システム連携の共通基盤“VCI(ValueChain
Initiative)”には、全国で約80社の企業が参加しており、データリンクのインフラ基盤を確立し、グローバルに大・中・小企業間のリアルタイムデータ交換を支援している。
常時接続できるインフラが必要
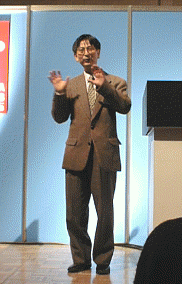 | 慶応大学ビジネススクール助教授の國領二郎氏 |
|---|
國領氏は、すべての機器が相互に連携の取れる仕組みが必要であるという。ネットワークを自由に繋ぎ合わせることができて初めて、多用な個人や企業の知恵が結合し、それを編集して価値を付けていくことができるという。同氏は「2000年までに、競争原理のもとで、全国で月額1万円未満で、毎秒64Kbit以上のアクセス回線にし、ベスト・エフォート型定額サービスを利用できるようにしなければならない」と提言している。情報ネットワーク進展による消費者動向の変化が、企業競争優位を確立するビジネスモデルを変革させることについて述べた。
非参入分野を決めることが大切
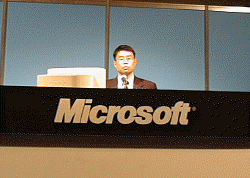 |
|---|
| フューチャーシステムコンサルティング(株)代表取締役社長の金丸恭文氏 |
金丸氏は、21世紀は顧客サービス力の競争になっていくということを述べ、IT投資の考え方や非参入分野を決めることが大切など、実際の経験に基づいた講演を行なった。
ネットワーク環境が強化され、産業構造が変わってくるにつれて、DNAはビジネスシステムにとって不可欠なものとなってくるだろう。


















































