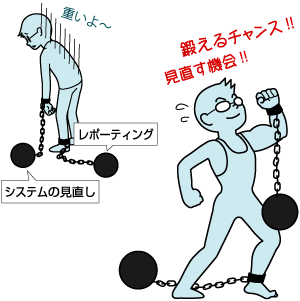2009年3月の日本版SOX法の施行に伴い、その準備にあわただしいエンジニアも多いのではないでしょうか。著者の周りにも内部統制に関わる準備を経験している社内SEがいます。彼らはそれまで属人的にシステム開発と運用を行なってきたため、改めてシステムを整理する必要に追われ、忙殺されているようです
内部統制を実現するには、情報システムそのものやIT部門の業務の見直しだけでなく、他部門──たとえば経理部門のシステム──やそれに関連する各業務システムの見直しが必要です。つまり結局は会社のITシステム全体の見直しが必要になると言えるでしょう。すると、業務の割り出しに関する部門間の共同作業があったり、作業の透明性を保ち正確性を維持させるために作業のノウハウや「勘どころ」までも文書化しなければならないなど、とてつもない労力がかかります。これらはエンジニアである皆さんにとっては“つまらない”作業かもしれません。
しかし、このようにITシステム全体への意識を迫られるこの期間は、エンジニアにとって自分が所属する会社全体、ひいては社会全体と自分の役割との関係を今一度考え直す絶好の機会と捉えるべきです。エンジニアというものは、通常その業務の専門性から、目前の事柄に集中して問題を限定的に捉えることには長けていますが、あるコンテクストの中での相対的な関係に関しては、考えない、考えられないという傾向にあると言えます。けれども、全体との関係を振り返ることで「技術というものが会社を含めた社会の要請のもとに始めて成立している」ということを、改めて実感するはずです。そして、それはつまり自己の業務のあり方を見直す契機ともなるでしょう。この「再認識」により、これまでとは異なった次元での仕事のやり方や計画の立て方ができるようになります。それはエンジニアとしての進化です。
具体的に身に付くスキルで言えば、レポーティングを視野に入れた開発スキル──たとえば、運用時にパフォーマンス(日々の運用の状況)をレポートすることを念頭に入れて、きちんと管理されているシステム開発をする──などができるようになるでしょう。これは、全体における自分の役割が明確になる中で「開発とは、関係者に対して運用状況を明確に説明することまで含む」と考えられるからこそ身に付けられることなのです。
たとえ日本版SOX法がなくても、ITがより社会インフラとして社会に深く関わっていく過程で、このようにエンジニアが進化していくことは当然求められるものです。日本版SOX法を単なる負担として捉えるのではなく、責任を持って実行することができれば、社会からの進化の要請に応えられるエンジニアと言えるでしょう。
Illustration:Aiko Yamamoto

この連載の記事
-
第13回
ビジネス
最終回 オフショア時代を生き残るエンジニア -
第12回
ビジネス
第12回 はじめに“辞め時”を考えておくべき~出口戦略~ -
第10回
ビジネス
第10回 あらゆる問題の原因をつきとめる~切り分け~ -
第9回
ビジネス
第9回 よいマッシュアップへと導くキホン中のキホン -
第8回
ビジネス
第8回 成長のチャンスを逃がしてませんか?~現場の機会を考える~ -
第7回
ビジネス
第7回 革新的なサービスを生む源~インターフェース~ -
第5回
ビジネス
第5回 テクニックは人に見せないと!~コードレビュー~ -
第5回
ビジネス
第6回 世にあふれるビジネスノウハウに混乱するな!~KISS~ -
第4回
ビジネス
第4回 自分のことってわかってる?~生産性を考える~ -
第3回
ビジネス
第3回 しっかり稼げてヤリガイあり~新インクリメンタル型開発~ - この連載の一覧へ