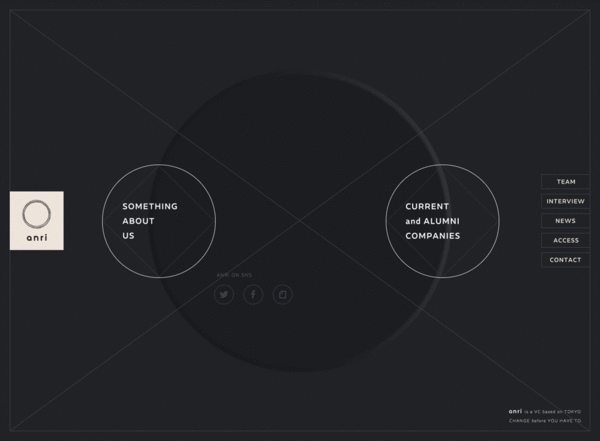誰もやりたがらない大学発スタートアップの”どシード期”にとことん投資 日本のエコシステムの周回遅れを取り戻すために必要な要素とは
ANRI パートナー 鮫島 昌弘氏インタビュー
この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」(外部リンクhttps://ipbase.go.jp/)に掲載されている記事の転載です。

ANRI パートナー 鮫島 昌弘氏
鹿児島県出身。東京大学修士課程卒業後、三菱商事株式会社に入社。その後、東京大学エッジキャピタル(UTEC)にて、大学発の技術ベンチャー企業への投資及び投資先企業の成長支援業務に従事。2017年にANRIに参画。
独立系ベンチャーキャピタルのANRIは、シード企業への投資に特化し、2012年の設立以降、これまで4つのファンドを設立し、累計350億円規模を運用している。草創期の1号、2号ファンドではラクスルやUUUMなど”IT系スタートアップ”を中心に投資してきたが、2017年の3号ファンドからは、量子やバイオ・ヘルスケア、ロボティクスなど幅広いテクノロジー領域の大学発スタートアップの支援にも力を入れている。同社のディープテック投資領域への拡大は、IT系スタートアップの集まる「渋谷村」と、ディープテック系の「本郷村」の双方のナレッジを共有することによる相乗効果を狙うものだ。
鮫島氏は、この3号ファンド設立の2017年から大学発スタートアップの担当パートナーとしてANRIに参画。起業以前の大学の研究者のもとへ赴き、技術シーズの発掘、チームの組成といった準備段階からサポートしている。
「スタートアップの経営という観点では、IT系は大学発に比べて2、3周は進んでおり、知見が蓄積されています。どのタイミングでどのようなチーム構成にするべきか、上場までの資本政策のグランドデザインをどう描くか、といったベンチャー経営のノウハウを大学発ベンチャーにも応用したい、と考えています」(鮫島氏)
人や知財をはじめ、日本から生まれる大学発スタートアップのさらなる成長で求められる要素が何かを伺った。
起業家同士の横のつながりを作り、IT系の経営ノウハウを大学発スタートアップで活かす
ANRIは2018年にインキュベーション施設「ネスト本郷」をオープンし、大学発スタートアップ間での交流促進にも取り組んでいる。本郷の場合、”村”を形成するためのつながりが足りていなかった。同じ東大出身の起業家であっても、専門分野や学年が違えばコミュニケーションをとることは意外と少ないという。
「メンバー間のもめ事などのトラブルが起きても、投資家にはなかなか打ち明けにくい。こうした施設があることで、創業期メンバーが横のつながりを持ち、同級生感覚で悩みをシェアして自分たちで解決策を見つけてくれます」(鮫島氏)
ANRIは、渋谷にもインキュベーション施設「Good morning building by anri」を持ち、渋谷のIT起業家を本郷に招いて勉強会を開くなど、2拠点の起業家同士の横のつながりを深める活動もしている。
「大学発スタートアップのシード期に投資するのは、普通に考えれば、時間がかかり、リスクも大きい。しかし、投資するVCがいないからこそ、僕らがやらなければならない。僕らが困難なシード期を支え、大学発スタートアップの数を増やし、技術を社会実装することで、日本の科学技術立国としての底上げを担いたいという使命感です。一方、ファンドを運営するうえでは、エントリーのバリエーションが抑えられ、成功すれば大きなリターンが期待できるという経済的インセンティブもあります。
じっくりと時間をかけるべきところは待ちつつも、一方で、初期に適切なメンバーを入れて、適切なタイミングでしっかり投資をすれば、仮にこれまで20年かかっていたことが10年、早ければ7〜8年まで短縮できるでしょう。とはいえ、実際の成果が見えてくるにはもう少し時間がかかりそうです」
技術的なブレークスルーと知財の担保が投資対象となる
大学発スタートアップにおける課題の一つに、大学との知財権の交渉で問題が顕在化するケースがある。
「大学によって、特許やライセンスの取り扱いが異なり、とくに地方大学は過去にライセンス交渉の実績がないため、時間がかかり、スタートアップのスピード感に対応できていない部分があります。権利範囲についても、大学側は特許の出願数にこだわりがちで、質の面で抜けやもれがあることが多い。大学TLO(技術移転機関)のKPI設定を、数ではなく質に変えていくべきという危機感を感じています」と鮫島氏は指摘する。
大学側にしてみれば、国からの運営交付金が年々減少する中、自助努力で経営してなくてはいけないという事情もあり、ここ数年は、過度なストックオプションや売り上げフィーを要求されるなど、スタートアップに不利な契約内容を提示されるケースも増えている。とはいえ、創業期のスタートアップに負担を強いることで成長の足枷となり、本来持っていた潜在的な価値を毀損してしまっているケースが出るのではないか、という懸念がある。
ANRIでは、グローバルのライセンス交渉や特許紛争の経験がある弁理士と相談しながら、大学側との交渉のサポート行なっている。
研究に重点を置いたスタートアップの場合、起業後も大学との共同研究を継続するケースも多々ある。大学側が権利を主張し過ぎると、共同研究自体が難しくなりかねない。さらに、ライセンスアウト後にスタートアップが大学との関係を完全に切ってしまうと、中長期的には大学側にとっても不利益になってしまう。
大学側も知財予算が潤沢にあるわけはないため、PCTによる海外出願においても各国出願の費用が足りず、海外で勝負できる新たなビジネスが生まれにくい要因にもなっている。
「例えば、民間で十分な実績のある弁理士で構成された『スーパーTLO』のような機関ができればいいのではないかと思っています。『Nature』や『Cell』などトップジャーナルに論文を出しているような先生の知財は、本来もっと戦略的に国として注力してもいいと思います。既存の垣根を超えたスーパーTLOにしっかり管理してもらう形が理想です。技術的なブレークスルーと、しっかりとした知財が担保されれば、投資を行うVC側としてもありがたいです。あとはそこにフルタイムのメンバーを入れてチームを作れれば、かなりの成長が見込まれます」(鮫島氏)
大学発スタートアップに不可欠な社会的なニーズ
鮫島氏がシーズを持つ研究者とコミュニケーションを取るのは起業前の段階で、発明が知財化されていないことも多い。では、どこを評価して投資先を選んでいるのか、その条件を聞いてみた。
「社会的なニーズがあるかどうかが大事です。例えばソナス株式会社の場合、起業前からすでに『その技術を使いたい』という大手企業側からの声がありました。大学の先生方のピッチにありがちなのが『既存の製品よりも数%改善する』といったものですが、ユーザー候補となるの企業からすれば、数%の性能向上のために信頼性の高い既存の製品からスタートアップの製品に切り替えよう、とはなかなかいきません。大学の研究段階で、『企業が高いお金を払ってでもその製品を買いたい』というニーズがあることがスタートアップ化するかどうかの強い目安になります」(鮫島氏)
投資家や企業に技術を対してアピールするのであれば、技術そのものだけではなく、その技術が世の中にどのような価値をもたらすのか、技術の普及によってどんな未来があるのかまで踏み込んで語ってほしい、とのこと。
現在の大学発スタートアップの盛り上がりはポジティブな面もある半面、安易に起業数だけが増えてしまうことへの懸念も感じているそうだ。
「大学の先生を続けながら、2足のわらじでスタートアップを兼務するのは危険です。トップがフルタイムでしっかりと会社にコミットしなければ、ほかのメンバーはついてきてくれません」
研究者が兼務する形でのスタートアップでは、進めていた事業が途中でうまくいかなくなると、もう1足のわらじである大学の研究に専念してしまい、スタートアップとしての経営がおろそかになるパターンも往々にしてあるという。大学の職務を続けるのであれば、外部から経営者を登用するか、自身が経営に関わるにしても、フルタイムの共同経営者を立てたほうが成功の可能性が高まる。
どこからチームを連れてくるかも課題だが、ANRIの場合、ここに起業のノウハウをもったIT系スタートアップ起業家などをアサインすることも想定しているという。また、前述したネスト本郷のようなコミュニティも、人材を醸成するための舞台となる。
シーズがあり、そこから生まれる企業の数が増えてきたら、次に足りないものは何なのか。鮫島氏は、日本の大手企業によるスタートアップへの適正な価格でのM&Aが増え、早期のEXITが出てくることを挙げる。そのためには、成長初期からの大企業との連携も欠かせない。
「大企業が初期のユーザーになってくれるとありがたいですね。量産化できればコストが下がり、次のスケールアップができます。日本の大企業は、日本のスタートアップへのM&Aにも積極的になってほしい。日本の大学発スタートアップは米国と比べて同水準の技術レベルだとしても企業価値は10分の1ほどしか評価されていません。大企業は日本のスタートアップの技術をきちんと評価して、自社のサプライチェーンや次世代の事業の根幹のひとつとして取り込むなり、もっと活用するべきではないでしょうか」
M&Aにより早期にEXITできることで、よい循環が生まれ、起業家の質も上がってくる。10年単位での長期のEXIT見込みのため、これまで日本の大学発スタートアップを投資対象として外していた投資家からも、十分なリターンが回収できる見込みが出てくれば、投資も進んでくる。
「大企業と投資先との事業提携やM&Aの交渉の話をうまく進めるのもVCの役割のひとつ。ANRIとしても、大企業のトップ層と一対一で話ができるような関係を築いていくことが目標です」