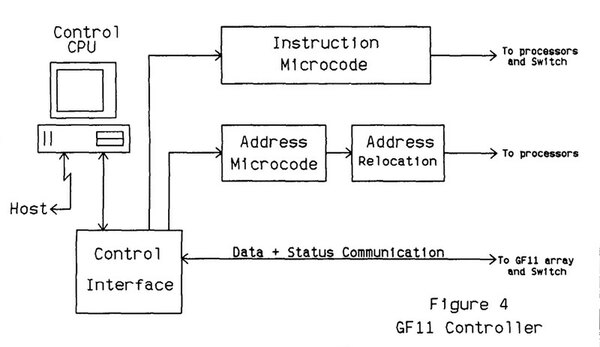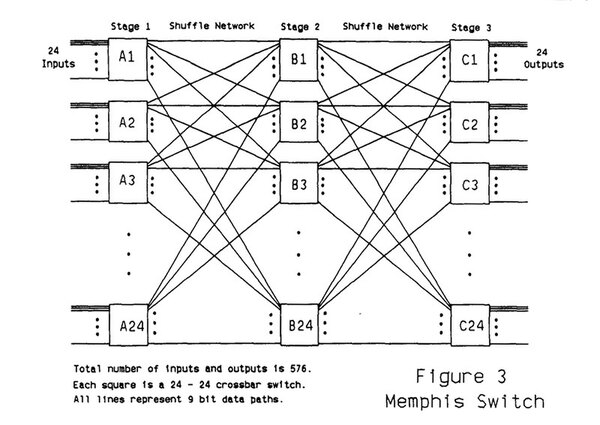プロセッサーの動作を制御する
Central Control
このような構造から、GF11はプロセッサーあたり20MFLOPSの演算性能になる。これを512プロセッサー動作させれば10240MFLOPS、スペアも全部使って576プロセッサー動作にすると11520MFLOPSという演算性能になるわけだ。
ただWTL1032/1033は本当に、レジスターに値を入れて何サイクルか待つと結果がレジスターに出てくる「だけ」のものなので、細かい実行制御や、そもそもどのデータに対して演算を行なうか、といったことは外部で制御する必要がある。
これを行なうのがCentral Controlのブロックである。ちなみに個々のプロセッサーにはSRAMおよびDRAMも搭載されており、SRAMは短期記憶、DRAMは長期記憶という使い分けになっていた模様だ。
WTL1032/1033以外の回路はFairchildのFAST TTL Logic ICで構成され、レジスターファイルはFairchildの100K ECLが利用された。レジスターファイルのアクセス時間は12.5ナノ秒(80MHz)となっている。
ちなみにCentral Controlからは200bit(当初は180bitと記述されていたが、拡張されたらしい)のマイクロコードの形で各プロセッサーの動作制御が行なわれた。
マイクロコードは、576個のプロセッサーすべてにブロードキャストする形になっており、その意味ではMPP(超並列システム)ではあってもMIMDではない。すべてのプロセッサーが同じマイクロコードを受け取って、同じ処理を行なうからである。Central Controlは当初はIBM PC/ATで実装していたようだ。
演算の高速化のために搭載された
Memphis Switch
プロセッサーとつながる“Memphis Switch”の内部構造が下の画像である。それぞれのスイッチは24入力、24出力(入出力幅は9bit)になっており、これを24個並べると576ポートになる計算だ。
ただこのままではストレージを接続できない。これもあってか、当初は512+64プロセッサーという構成を予定していたが、後にはプロセッサーの数を512+54の566に減らし、代わりにストレージを10個接続している。
各スイッチはLSI LogicのセミカスタムCMOSで製造されたチップを利用しており、1つのスイッチには18個のチップが利用された。つまり3段のMemphis Switch全体では、1296個のチップが使われていた計算になる。
Memphis Switchの目的は、演算の高速化である。例えば行列演算などでは、転置(行方向と列方向を入れ替える)がしばしば要求される。メモリー中のデータに対して転置をかけるとオーバーヘッドが大きいが、GF11の場合はMemphis Switchで転置を実行できるので、計算が容易になる。
ちなみに3段もの構成ではあるが、大抵のアプリケーションでは1段ないし2段で必要な並べ替えができると考えていたようだ。並び替えだが、Memphis Switchそのものは1024種類の構成をプリロードしておくことが可能で、200ナノ秒で構成を切り替えられるとされていた。
システム全体で言えば、およそ40万個のチップで構成された。576個のプロセッサーは20本の19インチラックに収められ(これには空調と電源も含まれる)、これとは別にMemphis Switch用に19インチラックが5本利用された(ただしうち2本は純粋に配線が通っているだけ)。Central Controllerはラック2つで、システム全体ではおよそ200KWの消費電力となっている。
余談になるが、プロセッサーボードは合計で660枚オーダーされ、うち440枚がデバッグをしてインストール、40枚が予備に回され、55枚が破棄されたとか。なかなか大変な話である。
話を戻すと、性能/消費電力比は57.6KFlops/Wで、これはQCDOCの51.7KFlops/Wよりも優れている計算になるが、QCDOCは倍精度の浮動小数点演算での数字なのに対し、GF11は単精度浮動小数点演算なので、同列に比較はできない。
とはいえ、10GFLOPSクラスのマシンが1985年の時点で稼動を始めることになり、ここから物理学者の出番となった。
1989年に、D. Weingarten博士と共同で作業していた物理学者のJ.C.Sexton博士が発表した“The Status of GF11”という論文によれば、比較的早期からGF11の性能を引き出せたとある。
GF11用のCコンパイラを利用してQuenched QCDを計算した際には、ピーク性能の80%を利用でき、ガウス=ザイデル法を利用した反復計算ではピーク性能の90~95%を利用できたとしている。
とはいえ、まったく独自のアーキテクチャーで構築された、しかも世界で唯一の計算機だけに、ソフトウェアは全部自分たちで記述する必要があり、これには相応の時間がかかる。
GF11は基本単精度演算のみだが、解くべき問題のサイズを大きくしていくと、一部で倍精度が必要になったり、WTL1032/1033には搭載されていない平方根や逆数平方根、指数/対数/三角関数/乱数などの特殊演算など、いろいろソフトウェア面での対応が必要になった。
さらにはQCDの演算の中には3×3の行列演算が含まれるので、この対応(GF11は基本偶数回の演算を前提にしている)も必要だった。

この連載の記事
-
第864回
PC
なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -
第863回
PC
銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -
第862回
PC
「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -
第861回
PC
INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -
第860回
PC
NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -
第859回
デジタル
組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -
第858回
デジタル
CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -
第857回
PC
FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -
第856回
PC
Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -
第855回
PC
配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -
第854回
PC
巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ