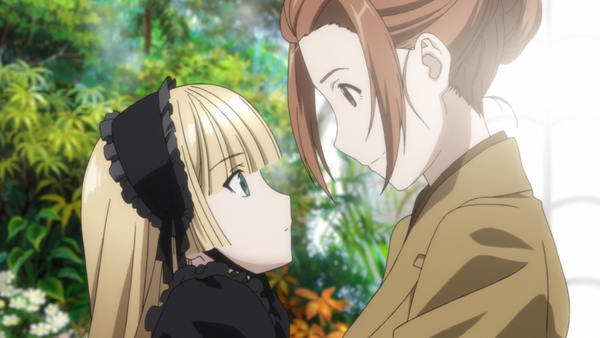アニメ「GOSICK―ゴシック―」難波日登志監督へのインタビュー後編(前編はこちら)。「カオスを再構築」というヒロインの言葉をキーに、転機を迎えつつある日本と、日本のアニメが積み重ねてきた歴史について考えていく。ヨーロッパと異なる、日本独自の“再生”“復興”感とは何なのか。
あらすじ

1924年、長い歴史を誇る西欧の小国・ソヴュール王国。東洋の島国からの留学生・一弥は、貴族の子弟たちが通う名門「聖マルグリット学園」にやってきた。一弥はある日、学園の図書館塔の一番上にある植物園で、人形のように美しい一人の少女と出会う――
「GOSICK―ゴシック―」 公式Webサイト
難波日登志監督について
1960年生まれ。新潟県出身。演出家。テレコム・アニメーションフィルム、東京ムービー、グループ・タックを経てフリーに。「ダッシュ!四駆郎」で初監督。主な監督作品に、「HEROMAN」「ぼのぼの」「YAT安心!宇宙旅行」「グラップラー刃牙」などがある。
©2011 桜庭一樹・武田日向・角川書店/GOSICK制作委員会
―― 前回、「GOSICK」を作るにあたって軸にしたのは“人同士の絆”とうかがいましたが、世界観としてはどんなことを軸とされましたか?
難波 「GOSICK」の舞台設定は、1924年のヨーロッパにあるソヴュールという架空の国ですが、その時代のヨーロッパというところでは、街並みとか建物などの背景を、できるだけ忠実に再現できたらと思っていました。チェコの街・プラハと、オーストリアのウィーンを取材したんですけれども、実際に現地に行ってみると、日本人が考える以上にヨーロッパの大きさ、歴史の深さというものが感じられました。特に、プラハは「GOSICK」が持つ世界観を表現するのにぴったりでした。
©2011 桜庭一樹・武田日向・角川書店/GOSICK制作委員会
―― プラハのどんなところが「GOSICK」的だと感じましたか。
難波 「GOSICK」では、ヨーロッパの1つの時代を抽出するのではなくて、長い年月をかけて積み重なって育ってきた、重層的な歴史を表現したいなと思っていたんです。プラハは東と西の交わる分岐点で、異なる文化圏のもの同士が重なるところも良かったです。プラハの街には、古い時代から今に至るまで、様々な時代の建築物が建ち並んでいるんですね。戦争で何回か壊されているんですが、それを復興するとき、今までの歴史を忘れることなく、以前のままの形で建てている。そうしたことを繰り返し行なってきたおかげで様々な様式の建物が残っている。それに、ヨーロッパの歴史が地層のように積み重なった、重層的な歴史が感じられる雰囲気になっているのかなと。
―― 日本とは違いそうですね。
難波 ええ。プラハだけでなくヨーロッパ自体もそうだと思うんですが、一度壊れたものと同じものをもう一度「再現」しながら作っていく、というところは日本にはないですよね。日本の場合は、何かが壊れて再建するときには、同じものを作り直すのではなく、まったく新しいものに作り替える。ヨーロッパが「再現」なら、日本は「再生」だろうと思うんです。
―― 「再現」と「再生」ですか。プラハと日本で、なぜそんな違いがあるんだと思いますか。
難波 ヨーロッパの人は、自分の国が過去から積み上げてきた伝統を大事にする人たちで、日本は、昔のことはあえて忘れようとする、そういう気質の違いなのかなと思うんですけれども。もちろんどちらが良いということではなくて、違いなのだと思います。
©2011 桜庭一樹・武田日向・角川書店/GOSICK制作委員会

この連載の記事
-
第56回
アニメ
マンガ・アニメ業界のプロがガチトークするIMART2023の見どころ教えます -
第55回
アニメ
日本アニメだけで有料会員数1200万人突破した「クランチロール」が作る未来 -
第54回
アニメ
世界のアニメファンに配信とサービスを届けたい、クランチロールの戦略 -
第53回
アニメ
『水星の魔女』を世に送り出すうえで考えたこととは?――岡本拓也P -
第52回
アニメ
今描くべきガンダムとして「呪い」をテーマに据えた理由――『水星の魔女』岡本拓也P -
第51回
アニメ
NFTはマンガファンの「推し度」や「圧」を数値化する試みである!? -
第50回
アニメ
NFTで日本の漫画を売る理由は「マンガファンとデジタル好きは重なっているから」 -
第49回
アニメ
緒方恵美さんの覚悟「完売しても200万赤字。でも続けなきゃ滅ぶ」 -
第48回
アニメ
緒方恵美さん「逃げちゃダメだ」――コロナ禍によるライブエンタメ業界の危機を語る -
第47回
トピックス
『宝石の国』のヒットは幸運だが、それは技術と訓練と人の出会いの積み重ね -
第46回
トピックス
『宝石の国』が気持ちいいのは現実より「ちょっと早回し」だから - この連載の一覧へ