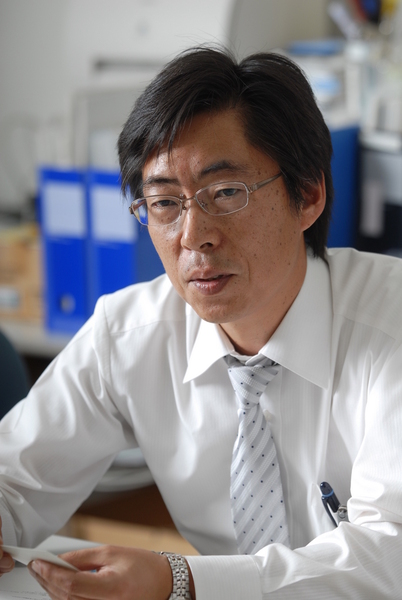医、歯、薬、保健医療の4学部と大学院で構成される昭和大学は、2008年に再構築した学内学術情報系ネットワークにフォーティネットのUTM(Unified Threat Management)機器を導入。ファイアウォール、アンチウイルス、IPS、そして検疫ネットワークなど、複数のセキュリティ機能をフルに活用している。
安全で止まらない
ハイパフォーマンスなネットワーク
昭和大学は国内では有数の私立の医系総合大学で、東京都品川区の旗の台キャンパスを中心に、洗足、横浜、富士吉田の各キャンパス、大学附属病院やクリニックなどで構成される。現在、学部学生数が約3000人、病院勤務の職員を含めた教職員が約5500名となっており、学生より教職員のほうが多いという構成になっている。
こうした同大学における教育・研究用ネットワークの運営を一元的に行なっている部署が、2000年に組織化された総合情報管理センターである。総合情報管理センターでは、設立時から教育・研究用ネットワークの再整備を進めてきたが、いくつもの課題に立ち向かう必要があったという。
1つめの課題は、利用者の増加と多様化である。学生が1年間寮生活を行なうという富士吉田のキャンパスでは、2005〜2006年に学生向けのネットワーク整備が行なわれてきた。一方、本部機能を持つ旗の台キャンパスのネットワークは教員の研究利用から発展してきたという経緯や校舎が古いこともあり、一部を除いて講義室のネットワーク整備が遅れていた。しかし、教材のマルチメディア化や国家試験対策などの整備が進んだことで、教員・学生の持ち込みPCの利用が増加してきた。さらに「2010年度より薬学部でも共用試験が本実施されることから、対象となる4年生が同時にCBT(Computer Based Testing)を受けられることなど、授業で利用できるネットワーク環境整備が急務でした」(井上氏)という事情もある。
だが、これに対して2000年に構築したネットワークでは対応に限界があった。「基幹装置系における相対的なスループット低下、非冗長構成ゆえのネットワーク停止への懸念など解決すべき課題がありました」(井上氏)とのことである。信頼性と同時接続に対するパフォーマンスは必ず満たさなければならない要件であった。
そしてもう1つの課題は、情報セキュリティである。「いくつもの附属病院を擁する医療系大学である以上、情報セキュリティの確保は絶対にやらなければならないものでした。もちろん、アプリケーションでもいろいろ試みはあるのですが、今回はネットワークレベルでもきちんとセキュリティを盛り込もうと考えました」(井上氏)。とはいえ大学という環境である以上避けられない持ち込みPCでは、過去にワームが拡散するなどの苦い経験もある。こうしたセキュリティ面でのリスクを軽減するためには、あらゆる脅威に対抗できるセキュリティ対策が必要になるわけだ。
(次ページ、「シンプルな管理とセキュリティが考えられたUTM」)

この連載の記事
-
第58回
ビジネス・開発
モノタロウのデータ活用促進、秘訣は“縦に伸ばして横に広げる” -
第57回
ビジネス・開発
“物流の2024年問題”を転換点ととらえ社内データ活用を進める大和物流 -
第57回
ITトピック
米の銘柄をAIで判定する「RiceTag」 検査員の精度を実現する試行錯誤とは? -
第56回
ビジネス・開発
ノーコードアプリ基盤のYappli、そのデータ活用拡大を支えるのは「頑丈なtrocco」だった? -
第55回
ビジネス
国も注目する柏崎市「デジタル予算書」、行政を中から変えるDXの先行事例 -
第54回
IoT
“海上のセンサー”の遠隔管理に「TeamViewer IoT」を採用した理由 -
第53回
ネットワーク
わずか1か月弱で4500人規模のVPN環境構築、KADOKAWA Connected -
第52回
Sports
IT活用の「コンパクトな大会運営」20周年、宮崎シーガイアトライアスロン -
第51回
ソフトウェア・仮想化
DevOpsの成果をSplunkで分析&可視化、横河電機のチャレンジ -
第50回
ソフトウェア・仮想化
テレビ東京グループのネット/データ戦略強化に「Talend」採用 -
第49回
Team Leaders
おもろい航空会社、Peachが挑む“片手間でのAI活用”とは - この連載の一覧へ